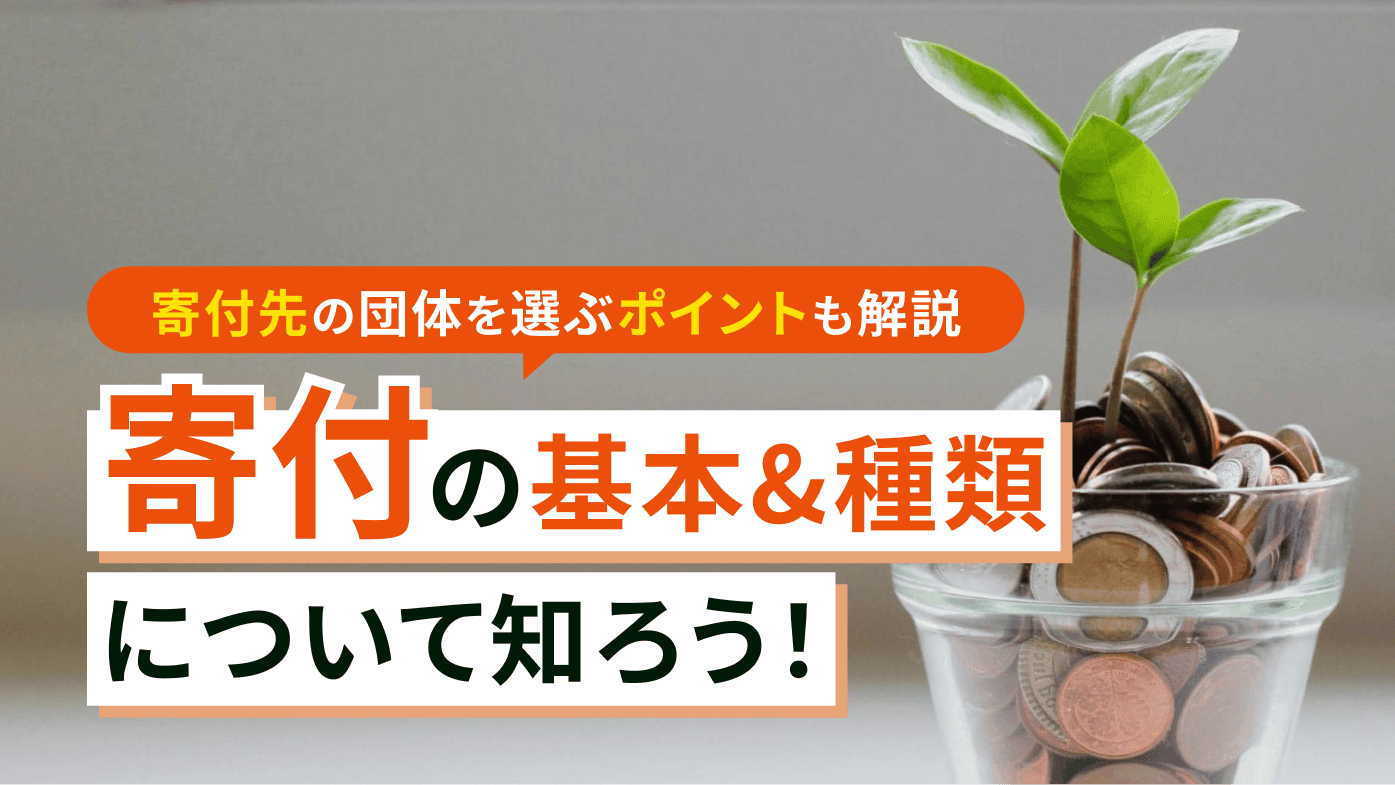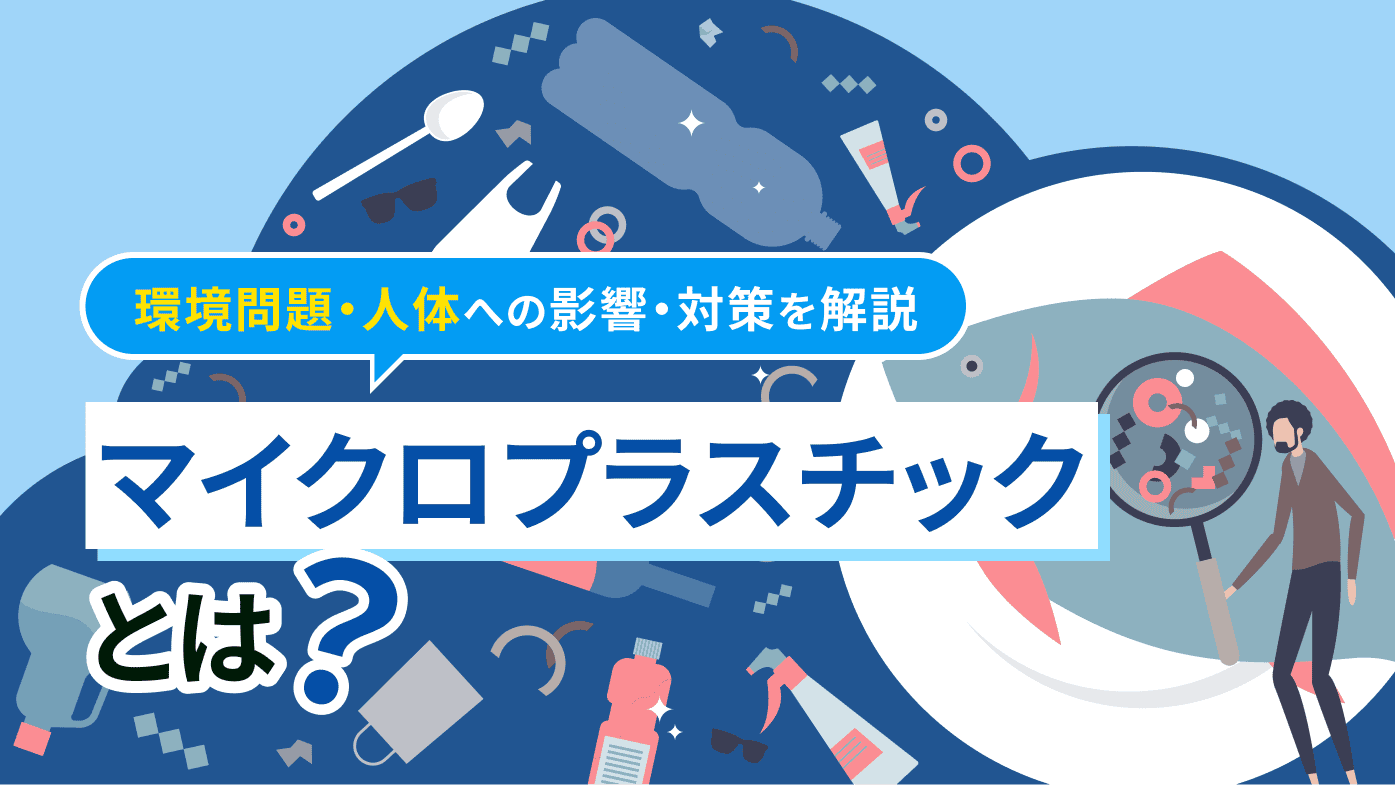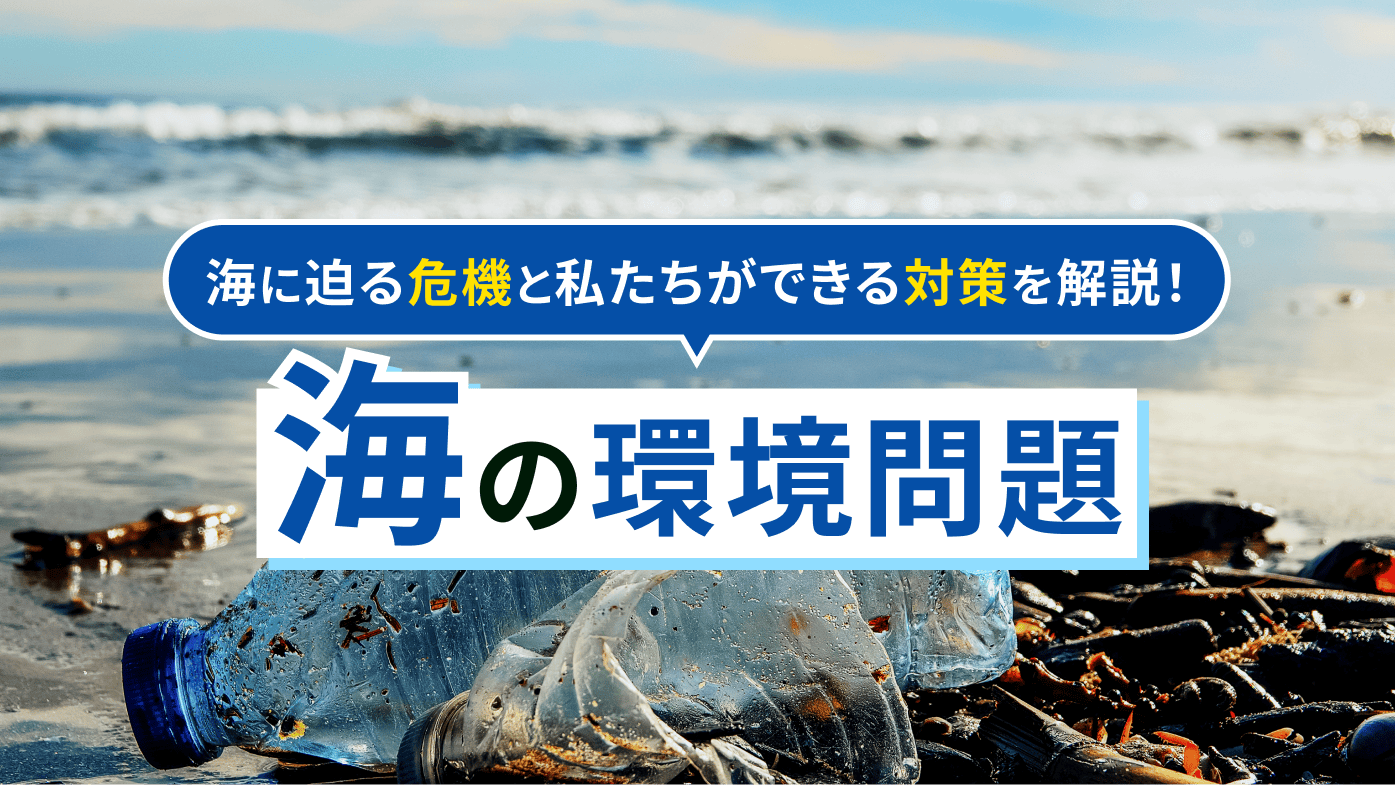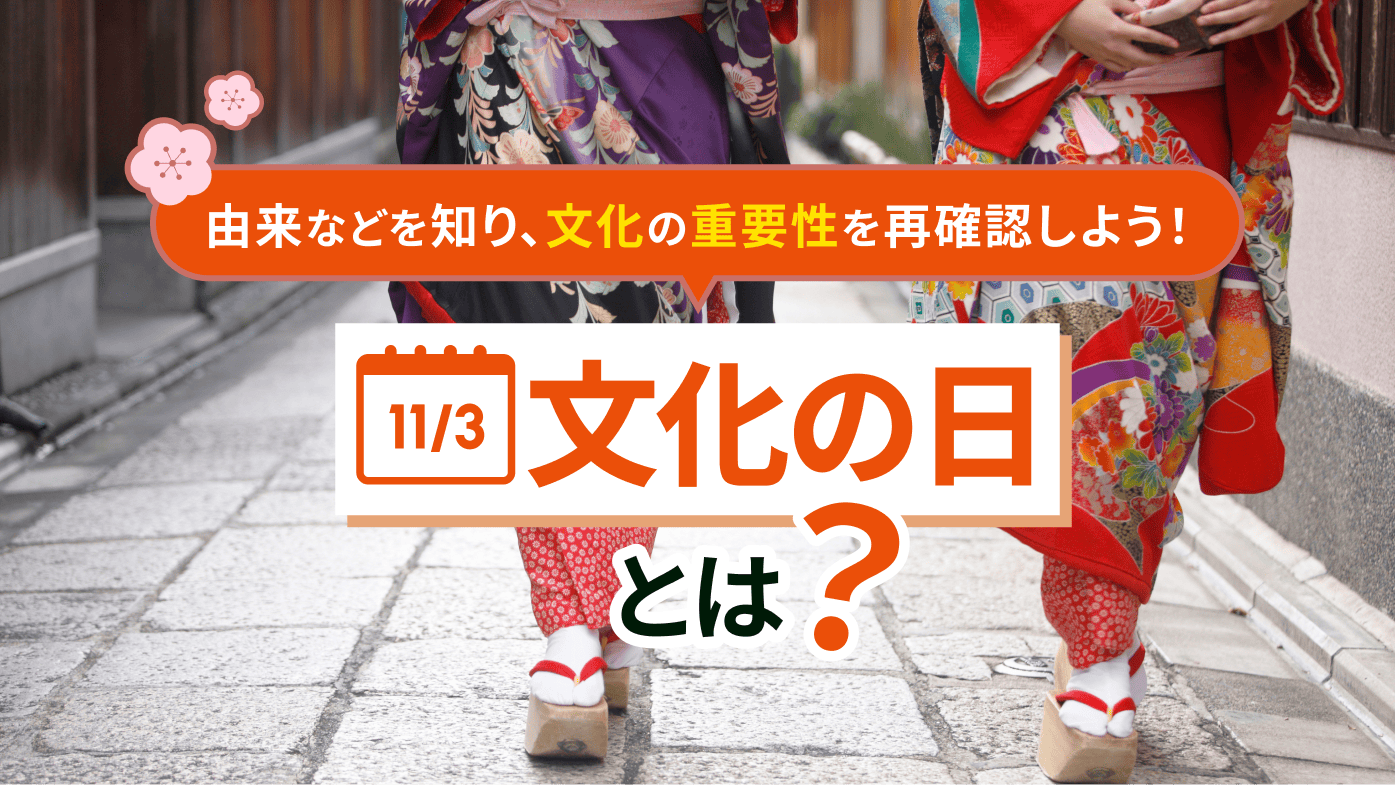
2025.09.02
文化の日とは?由来や何をする日かを知り、文化の重要性を再確認しよう!
文化の日とは、11月3日に定められている国民の祝日です。
しかし、「具体的にどういった日なの?」「何をするのがいいのだろう」と思っている方もいるのではないでしょうか。
本コラムでは、文化の日の由来と歴史、おすすめの過ごし方について、詳しく解説します。
目次
11月3日は文化の日

11月3日は文化の日であり、日本の祝日です。しかし、その由来や歴史については知らない方も多いでしょう。
ここでは、「文化の日はどのように生まれたのか」また「どのような意味が込められているのか」などをわかりやすく解説します。
文化の日の由来と歴史
文化の日は、1948年に「国民の祝日に関する法律」によって毎年11月3日に定められました。日付は日本国憲法が公布された日である1946年11月3日に由来しています。
11月3日は明治天皇の誕生日でもあります。そのため、文化の日が定められる以前も、明治時代には「天長節※」、大正時代以降は「明治節」という名で大切にされてきました。
戦後、日本国憲法の公布日が11月3日になったのは、翌年5月3日の施行に合わせて、ちょうど半年前にあたる日を選んだ結果です。偶然にもその日は、かつての祝日「明治節」にあたる日でした。
この日は、日本の文化や芸術を称えるさまざまな行事が全国で開催されています。
※ 天皇誕生日を指す言葉
文化の日の意味や意義は?
文化の日は、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」という趣旨のもと制定されています。これは平和主義を原則としている日本国憲法の公布日が、文化の日の由来であるためです。
この日は文化面の功績を称え合う日でもあり、国家規模の表彰が行われています。
そのほか、自治体などが主催する各種イベントが全国各地で開催されています。
多くの人々がさまざまな文化に気軽に触れることは、ひいては学術や芸術など文化活動のさらなる発展へとつながり得ます。このことこそが、文化の日の大きな意義だといえるでしょう。
文化の日に開催されているイベントを紹介

11月3日は文化の日であり、この日を中心とした11月1日から7日までは「教育・文化週間」と定められています。教育や文化への関心と理解を深め、より充実させることを目的に設けられました。
期間中は全国各地で多彩なイベントが開催され、大人から子どもまで学びと楽しみを共有できます。ここでは、文化の日に開催されるイベントを紹介します。
文化勲章の親授式(東京)
文化勲章の親授式とは、天皇陛下が直接、文化勲章を受章者に授与する儀式です。毎年11月3日の文化の日に、皇居の宮殿「松の間」で執り行われます。
式では天皇陛下から受章者に文化勲章が手渡され、内閣総理大臣から栄誉を正式に証明する勲記(くんき)といった文書が渡されます。親授式のあと、受章者とその配偶者は天皇陛下への拝謁(はいえつ)が許され、陛下から直接お祝いの言葉を賜るのが慣例です。
受章者の功績や式典の様子は、毎年ニュースなどを通じて広く発信されています。
文化施設の無料開放(全国各地)
文化の日を中心に、全国各地の美術館・博物館・水族館などの文化施設で無料開放イベントが実施されています。
例えば、国立西洋美術館(東京都)や東京国立近代美術館(東京都)、松戸市立博物館(千葉県)など、数多くの美術館や博物館を無料で利用できることもあります。
美術館や博物館以外にも、兼六園(石川県)などの文化財指定施設が無料開放の対象となることもあります。
地域の文化祭や芸術祭(全国各地)
全国各地では、地域の特色や文化を楽しむための文化祭や芸術祭が毎年盛大に開催されています。
例えば、神奈川県で行われているイベント「かながわ県民文化祭」では、文化の日を中心とした9月から12月に、県民がさまざまな文化活動に触れ合える環境を整えています。
また、福岡県では10月から12月にかけて「ふくおか県芸術文化祭」を開催しています。演劇や伝統芸能など魅力あふれる催しを多数展開しているのが特徴です。
こうした取り組みは地域住民の交流にもつながっており、多くの方々が新たな文化や芸術の発見を楽しんでいます。
文化の日は何をする日?おすすめの過ごし方

文化の日を楽しむ方法は、イベントに参加する以外にもさまざまあります。
ここでは、文化の日のおすすめの過ごし方を6つ紹介します。興味の持てるものがないかを探してみてください。
博物館や美術館に出掛ける
文化の日は、博物館や美術館などの文化施設で芸術や文化に触れる良い機会です。
文化の日や教育・文化週間には、さまざまな施設で特別展の開催や無料開放などが行われます。
普段は博物館や美術館などに足を運ばない方も、この機会に訪れることで、新しい発見や学びが得られるかもしれません。
子ども向けのワークショップやバックヤードツアーなどを実施する施設もあり、家族で楽しめるのも魅力です。
気軽に文化とふれあいながら、感性や知識を育む一日にしてみてください。
神社や仏閣に参拝する
文化の日には、日本の歴史や伝統のある神社仏閣を訪れてみるのもおすすめです。
神社仏閣は建築や庭園などの随所(ずいしょ)に日本文化が息づく空間です。散策するだけでも、日本特有の美意識や禅(ぜん)の思想、建築様式の歴史などに触れられます。
座禅、滝行などの体験を実施しているところもあるので、文化の日にチャレンジしてみるのも良いでしょう。
また、親子連れにも神社仏閣はおすすめです。神社の参拝時には、鳥居のくぐり方や参道の歩き方などさまざまな作法があります。子どもにとって、自然に学びが広がる体験ができるでしょう。
伝統工芸品の工房や展示に出掛ける
文化の日には、伝統工芸の工房やギャラリーを訪れてみたり、百貨店などで開催される伝統工芸展や企画展に足を運び、職人の技と美の世界を体験したりするのもよいでしょう。
伝統工芸品は、古くから受け継がれてきた技術や技法を用いて、主に手作業で製造される工芸品です。それぞれの地域で受け継がれてきた伝統工芸品は、日本の文化の奥深さを感じさせてくれます。
職人の作業風景を間近で見られる工房やギャラリーのほか、ものづくり体験ができる施設もあります。実際に手に取ったり、話を聞いたりすることで、職人の技術や文化的背景への理解が深まるでしょう。
工房へ足を運ぶのが難しい場合は、もう少し気軽に楽しめる選択肢として、百貨店で開かれる伝統工芸展や企画展もあります。日本各地に根づく伝統の技に触れることで、地域の文化や美意識の豊かさを再発見できるでしょう。
歌舞伎を鑑賞する
歌舞伎は、江戸時代初期に生まれた日本独自の演劇で、400年以上の歴史を持つ日本が誇る伝統芸能です。音楽、舞踊、演劇の要素が融合した総合芸術であり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。
歌舞伎の特徴は、基本的に男性俳優のみで演じられるところです。子役の場合など例外はありますが、女性の役も「女方(おんながた)」と呼ばれる男性俳優が演じます。
役者が感情の高ぶりを表現するために一瞬動きを止め、特定のポーズを取る「見得(みえ)」も歌舞伎を象徴する表現の一つです。
歌舞伎を見に行く際はぜひこのような伝統的なポイントもチェックして、楽しんでみてください。
現代では従来の古典作品だけでなく、流行作家が台本を手がけたり、アニメや漫画作品とコラボして舞台化を行っていたり、歌舞伎を見たことがない方でも親しみやすいものとなっています。
相撲を観戦する
相撲は、まわし※1を締めた力士が、土俵の上で力と技を競う伝統的な格闘技です。起源は古く、神話や「古事記」「日本書紀」にも相撲の原型ともいえる記述があります。
江戸時代には庶民の娯楽として発展し、独自のルールや伝統を守りながら、現在も「国技」として広く親しまれています。
近年ではSNSの活用やメディア露出によってファン層を拡大しています。江戸時代から変わらぬ姿を見せてくれる相撲は、日本の文化を知るのにぴったりな伝統文化でしょう。
大相撲本場所※2は年6回開催され、11月場所は11月中旬以降の開幕です。文化の日を少し過ぎてはしまいますが、迫力満点の相撲をぜひ生で観戦してみてはいかがでしょうか。
※1 相撲をとるときに、力士が腰に身に着けるもの
※2 日本相撲協会が主催する大相撲の公式な定期興行
着物を体験してみる
文化の日には、着物を実際に身に着けてみるのはいかがでしょうか。
着物は、日本の伝統的な衣服であり、奈良時代にはすでに原型が存在していました。現在の形の着物が定着し始めたのは、平安時代だといいます。
現代では着物を普段から着用することは減っていますが、だからこそ貴重な体験になり得ます。
着物が手元にないという方は、着付け体験やレンタルがおすすめです。無料で体験を実施している着付け教室もあれば、数時間単位で借りて街の散策を楽しめるレンタルショップもあるので、気軽に楽しめるでしょう。
文化について学ぼう!公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがメンバーで協力し合い、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「いろいろな文化に触れてほしい」や「楽しみながら社会について学んでほしい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
イオン チアーズクラブで開催された活動
ここでは、イオン チアーズクラブでこれまでに実施してきた活動内容の一部をご紹介します。
阿波踊りの歴史の振り返りと実演体験
イオン徳島チアーズクラブでは、徳島の伝統芸能である阿波踊りについて、歴史と体験を通して理解を深める活動を行いました。
阿波踊りの歴史学習と踊り体験を実施しましたが、メンバーたちは現在の阿波踊りとは異なる昔の踊りの様子や、使われていた鳴り物について学びました。
特に阿波踊り体験は、メンバー全員が積極的に参加し、笑顔で楽しむ様子が印象的でした。
フードアルチザン(食の匠)について学ぶ体験ツアー
「フードアルチザン(食の匠)」をテーマにした活動が、2023年8月に第1回目、2024年1月に第2回目と行われました。
「フードアルチザン(食の匠)」活動は、「地域の食文化を守る活動をしてほしい」というお客さまの声に応え、2001年から繰り返し取り組んでいる活動です。
今回の体験は、熊本県八代市の晩白柚(ばんぺいゆ)農園で行われました。
第1回目の活動では、メンバーたちは、柑橘類の一つである晩白柚の実を保護し、品質を高めるための「袋がけ」作業を体験しました。
第2回目の活動では、8月に袋がけをした晩白柚の成長を観察し、生産者の方からお話を伺い、晩白柚について学びを深めました。
また、クイズを交えながら、晩白柚の生産量日本一を誇る熊本県八代市の魅力を再発見できました。
沖縄の文化体験ツアー
首里城公園(沖縄県)にて、沖縄県への支援金1億円の贈呈と、「イオン チアーズクラブ首里城復興支援ポスターコンクール」受賞作品の表彰式が同時に行われました。
表彰されたメンバーたちは、沖縄の文化を学ぶツアーに参加し、首里城見学などを行いました。
メンバーはガイドさんによる首里城の説明を熱心に聞いており、沖縄の伝統文化を学習できました。
この他にも、イオン チアーズクラブではさまざまな活動を行っています。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、文化の日について解説しました。
文化の日は、日本国憲法が公布された11月3日を国民の祝日としたものです。
文化の日には、美術館や博物館が無料開放される場合があったり、各地で伝統工芸展が開催されたりするため、日本の文化に触れる良い機会でもあります。
この日をきっかけに、日本の魅力にあらためて目を向けてみてはいかがでしょうか。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。