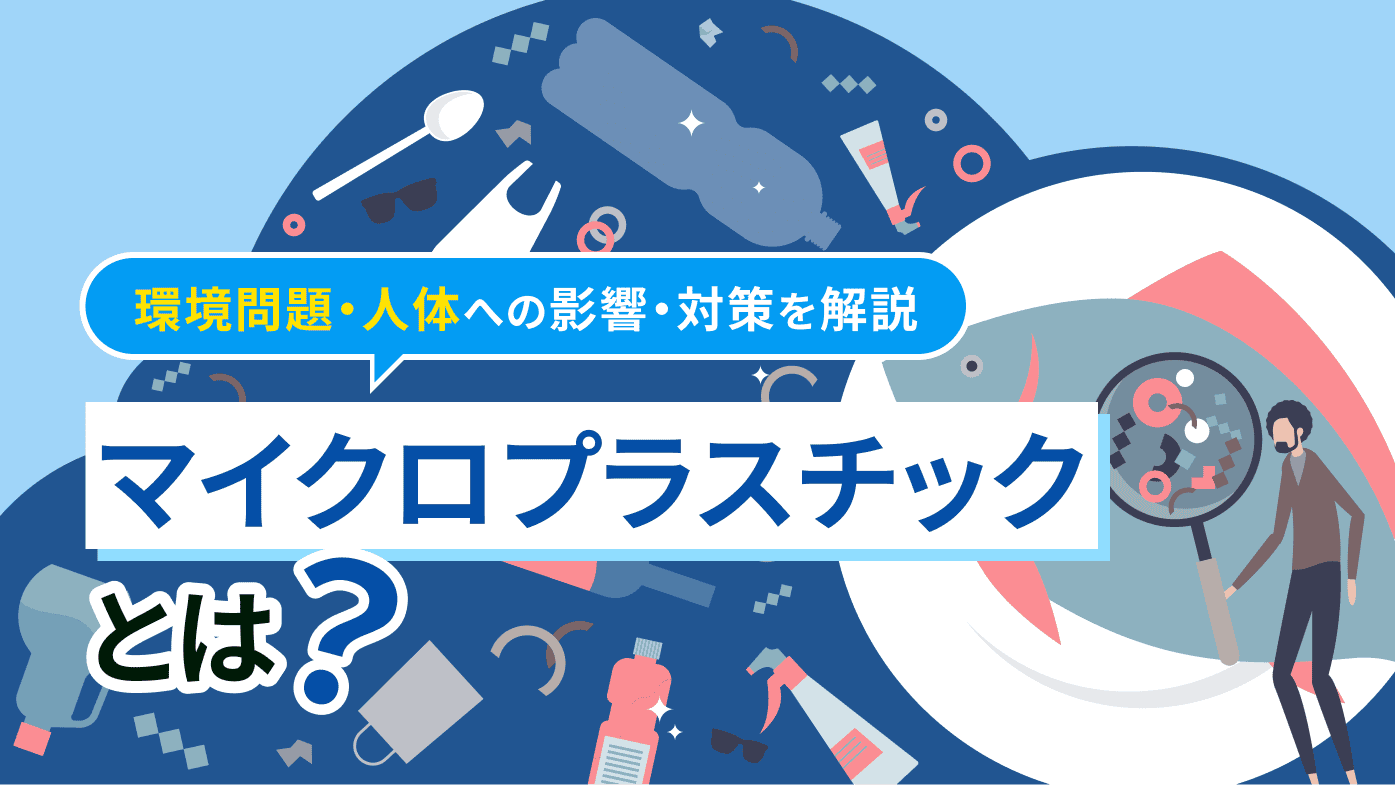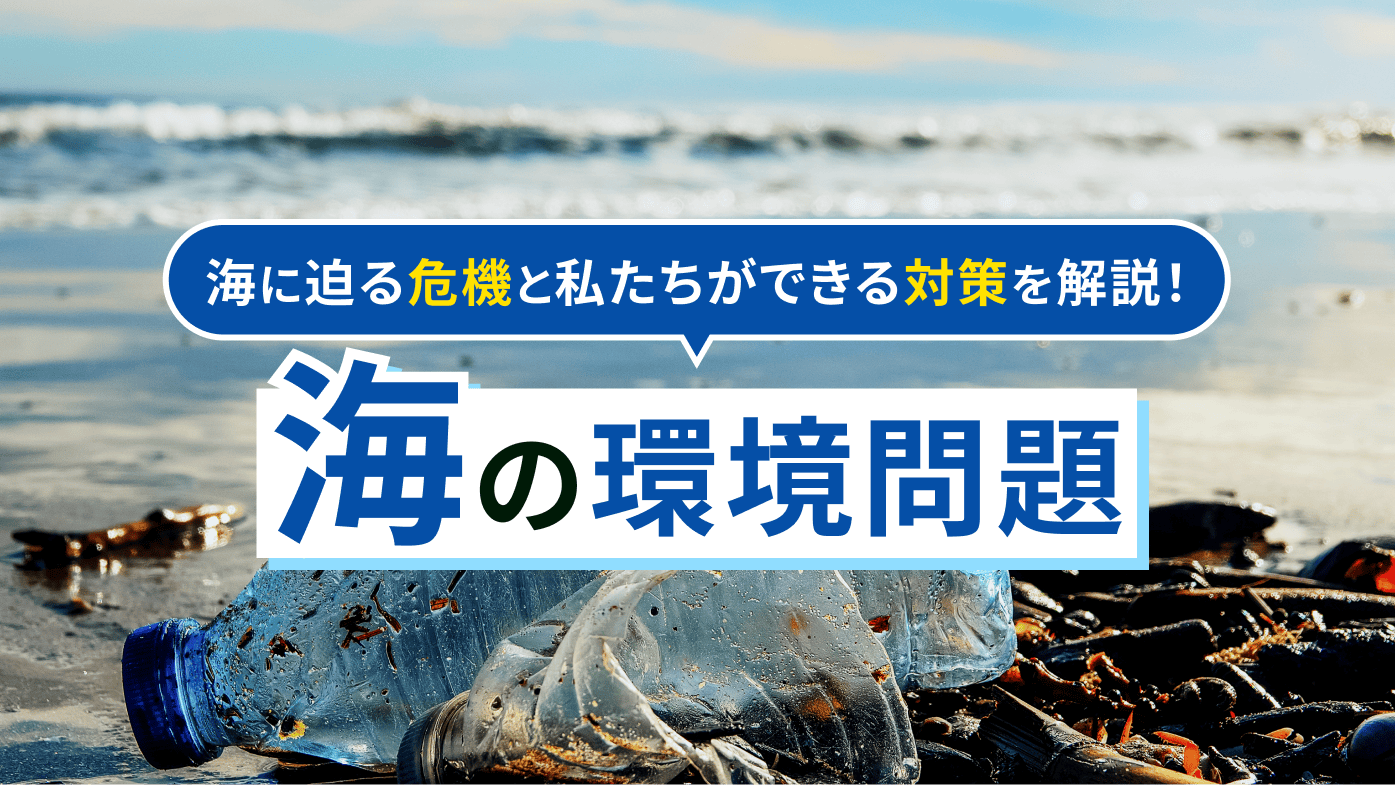2025.10.28
地域活性化とは?重要視される背景と問題、3つの成功事例を紹介!
地域活性化とは、地域に住む人たちが主体となって地域の魅力や課題に取り組み、地域全体を元気にしていくための活動です。
近年、日本では少子高齢化や東京圏への人口集中などの問題があり、その解決策の一つとして地域活性化が注目されています。
本コラムでは、地域活性化が求められる背景や、問題の詳しい内容、そして地域活性化のメリットや成功事例について解説します。
目次
地域活性化とは?

地域活性化とは、地域の人々が地域のために積極的に活動し、持続可能な社会を作るための取り組みを総称したものです。
例えば、地域ごとの特産品や資源を生かした事業の育成、インフラ整備、地域内外への情報発信など、地域の魅力を引き出し、地域経済の発展や住民の生活向上を目的としています。
また、地域活性化は地方創生につながる取り組みとしての大切な役目もあります。
地方創生とは、地域の人口減少をストップし、将来にわたって活力のある日本社会の維持を目的とした一連の施策です。
各地域が地域活性化に取り組めば、結果的に地方創生につながるとされています。
地域活性化が重要視されている背景・問題

地域活性化が重要視されている背景・問題には、日本が抱える「少子高齢化の進行」や「東京圏※への人口集中」があります。
ここではそれぞれの背景と問題について解説します。
※ 南関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)
少子高齢化
少子高齢化とは、日本の総人口から若年齢者の割合が減少する「少子化」と、高齢者の割合が相対的に増加する「高齢化」が、同時に進行している状態です。
つまり「子どもが少なく高齢者が多い社会」になっているということです。
日本の総人口は、2008年をピークに年々減少しています。
さらに、厚生労働省の人口動態統計(2023年)※1によると合計特殊出生率※2は1.20と過去最低水準を更新しており、少子化が深刻化していることがわかります。
また、15-64歳の生産年齢人口(生産活動を中心となって支える人口)も減少しています。
その一方で、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%、2054年頃には75歳以上の人口が全人口の約25%に達すると予想されている状態です。
少子高齢化が進むと、働き手が減少することで経済活動の成長が低下する可能性や、高齢者を支える介護や医療の現場でも人手不足が深刻化する可能性もあります。
※1 出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的としたもの
※2 15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの
東京圏への人口集中
東京圏の人口集中とは「東京圏に住む人々が増えている状態」です。
総務省「住民基本台帳人口移動報告(2024年)」によると、東京圏は29年連続で転入超過(転入者数が転出者数を上回っている状態)が続いており、2024年の転入超過数(転入者数-転出者数)は13万5843人と前年より9328人増加しました。
また、国外からの転入(外国人を含む)も合わせた「社会増加」※が東京都など20都道府県で確認されており、なかでも東京都の社会増加数は14万548人と非常に多い状態です。
東京圏は交通や商業施設、職場へのアクセスなどが整備されているため、地方に比べ利便性が高いと感じる人も多く、依然として人が流入しやすい環境が整っています。
しかし、人口が集中すると交通混雑や過密化による感染症のリスク、災害時の被害拡大などさまざまな問題も生じやすいのが現状です。
他にも、若者が都会へ出ていくことによって地域経済・産業の担い手不足やコミュニティ維持が困難になるなどの問題が起こります。
※ 転入者数が転出者数を上回っている状態
地域活性化のメリット

地域活性化の取り組みが重要視される背景には、上記のように少子高齢化や東京圏への人口集中といった問題があります。
こうした課題の解決策のひとつとして、地域活性化が「地域を元気にし、人口減少を食い止める手段」になるのではないかと考えられているのです。
ここでは、地域活性化の代表的なメリットを2つに分けて解説します。
雇用の創出
地域の特産品を活かした新しいビジネスや、観光開発が行われることによって地元の人々の仕事が増えます。
例えば、農産物・水産物を加工して付加価値を高める6次産業化※は、農家や漁業者だけでなく、加工や流通、販売にかかわる人材も必要とするため、雇用が創出されます。
※ 農業者(1次産業)が、農畜産物の生産だけでなく、製造・加工(2次産業)やサービス業・販売(3次産業)にも取り組むこと(6次産業の6は、1次産業の1と2次産業の2、3次産業の3をかけあわせた(1×2×3=6)という意味)
経済の活性化
地域活性化が行われることで、地域内で循環するお金が増え、経済が活性化していくことが考えられます。
国は地域経済を活性化させるための取り組みを行なっています。
総務省が行なっている地域密着型の創業・新規事業を支援する「ローカル10,000プロジェクト」や、地域経済を支える「特定中小企業集積」として指定された地域の中小企業が、新たな技術開発や新商品開発、販路開拓等を実施する際に補助金・低利融資・優遇税制等の支援が受けられる制度「地域産業集積活性化法」などがあります。
これらの取り組みにより地域に根付いた事業が成長すれば、経済が活性化していくと考えられます。
地域活性化の成功事例を3つ紹介

地域活性化にはさまざまなメリットがあります。
しかし「実際に、地域を活性化させるためにはどうしたら良いのか」「どのような成功事例があるのかが知りたい」という方もいるでしょう。
ここでは、地域活性化の成功事例を3つ解説します。
青森県田舎館村(いなかだてむら)の田んぼアート
青森県田舎館村は、田んぼをキャンバスに見立てる「田んぼアート」を実施し、地域活性化を成功させています。
1993年に村おこし事業として始まった田んぼアートは、技術向上により現在では7色の稲を使った芸術性の高いアートが作られています。
もともと、田舎館村は海や山もなく観光資源と呼べるものが少ない村でした。
ただ、田舎館村は昔から稲作が盛んな地域であったため「稲作で何とか地域おこしができないだろうか」と地域住民たちは考えていたようです。
そんなとき、古代米といわれている紫色の葉の稲「紫大黒」と黄色の葉の稲「黄大黒」を田んぼや畑に農作物を植え付けて栽培する現場を見た人がいました。
そして「食用の緑とあわせ三色の稲を使って田んぼに文字と絵を書いてはどうか?」と発案したことが田んぼアートの始まりです。
2012年からは入館料を徴収することで、収益にもつながっています。さらに、2016年度には観客数が延べ34万人になり、2017年には第11回産業観光まちづくり大賞で観光庁長官賞を受賞しました。
2016年からは「冬を楽しむ!雪と遊ぶ!」を目的として冬の田んぼアートも始まり、大人も子どもも楽しめるイベントを実施し、多くの人々を楽しませています。
北海道日高町の「COLD HIDAKA」
北海道日高町では、2015年から大自然と極寒の環境を活かして、町のブランディングを成功させています。
日高町は寒さが厳しい地域で、そんな地域ならではの趣向を凝らしたイベントを検討しました。
そして、寒さを最大限に生かした極寒10種競技「COLD HIDAKA」を企画し、スノーフラッグス(雪上で旗を奪い合う競技)や人間カーリングなどユニークな競技を実施しています。
秋田県五城目町(ごじょうめまち)浅見内(あさみない)のお互いさまスーパー
秋田県五城目町の浅見内集落では、地域住民が主体となって「みせっこあさみない」を運営し、地域活性化を成功させています。
五城目町は、地域内の商店がなくなってしまい「地域住民の買い物が困難になってしまった」という問題を抱えており、解決のために、浅見内活性化委員会が年に数回「買い物バスツアー」などの活動を行っていました。
しかし、日常的な買い物が困難という問題の解決に至らず、どうしようかと地域住民たちが考えた結果、みんなで運営を始めたのがお互いさまスーパー「みせっこあさみない」です。
スーパーは、日用品や生鮮品の販売など日常的な買い物はもちろんのこと、軽食コーナーや交流スペースを設けて地域住民の交流の場を設けています。
また、地域住民が主体となって運営することで、一人ひとりが活躍する場を生み出したという点でも地域活性化に大きく貢献しています。
地域活性化を成功させるために私たちができること

地域活性化にはさまざまなメリットがありますが、「いまいち案が浮かばない」「地域のために私たちができることは?」と悩んでしまう方もいるでしょう。
ここでは、地域活性化を成功させるために私たちができることを解説します。
地域の特徴を見つける
地域が持つ独自の特徴を活かすことは、地域の魅力を引き出し、外部へ発信するうえで欠かせない要素です。
特産品や文化・歴史といったものは、地元の人にとっては当たり前でも、地域外の人から見れば「新鮮で貴重な体験」となる場合が多々あります。
そのため、地域活性化を進めるための第一歩として、地域の人々が独自の資源や特徴に気づくことが大切です。
そして、発見した特産品はSNSで紹介したり、知り合いに勧めたり、贈り物として活用するなど、さまざまな方法で広めてみましょう。
こうした情報発信がきっかけとなり、地域への関心を高めるとともに、観光や地元経済の活性化につなげることができます。
地元に根付くものを魅力的に見せ、楽しんでもらう工夫を重ねることで、地域が持つ価値を際立たせて多くの人を呼び込む好循環を生み出していくのです。
地域のイベントや活動に参加する
地域活動に参加することは、社会貢献としての意義があるだけでなく、地域を盛り上げ、活性化につながる大きな原動力になります。
伝統文化を活かした催しや地域の清掃活動などの地域のイベントや活動に対して、主催者側として企画や運営に携わるのはもちろん、参加者として参加するだけでも十分に貢献でき、人々との交流を通じてコミュニティの絆が深まるのが大きな特徴です。
さらに、清掃活動で美しい街並みを保てば、その地域の印象もより良くなり、観光客や移住者を呼び込みやすくなります。
地域の人々とのつながりが強まれば、新しいアイデアや取り組みが生まれやすくなり、結果として、地域全体がより暮らしやすく、魅力的な場所へと変わっていくでしょう。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがメンバーで協力し合い、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「子どもを自然と触れ合わせたい」や「楽しみながら環境や社会について学んでほしい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
「イオン チアーズクラブ」で開催された活動
ここでは、イオン チアーズクラブでこれまでに実施してきた活動内容の一部をご紹介します。
阿波踊りの歴史の振り返りと実演体験
イオン徳島チアーズクラブでは、徳島の伝統芸能である阿波踊りについて、阿波おどり会館で歴史を学びました。
メンバーは、昔の踊りの様子や使われていた鳴り物について学んだり、踊り体験ではリズムにのって踊ったりと終始楽しそうな表情でした。
メンバーにとって、小さいころから身近にあった阿波おどりですが、知らなかったことも多く、阿波おどりの深さを感じることができる貴重な体験となりました。
熊本県産 晩白柚(ばんぺいゆ) 収穫体験ツアー

イオン チアーズクラブ熊本・大津の2クラブでは、合同で熊本県産 晩白柚の収穫体験ツアーに参加しました。
テーマは「フードアルチザン(食の匠)」※で、晩白柚農園での袋掛け作業やクイズを通じて、日本一の生産量を誇る八代市(やつしろし)の魅力を再発見しました。
熊本県八代市は、晩白柚の生産量日本一を誇るところで、メンバーは八代市と晩白柚の魅力を余すことなく学び、体験できる貴重な機会となりました。
※ 日本の食文化を支える食材や技術といった伝統そのものを、日本各地の地域の方々と保護・保存する活動
この他にも、イオン チアーズクラブではさまざまな活動を行っています。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、地域活性化について解説しました。
地域活性化とは、人口減少や高齢化が進む地域を活性化させ、持続可能な社会を実現するための取り組みです。
地域の経済や文化を盛り上げる行動は、地域だけでなく日本全体の活力を維持するうえでも重要といえます。
地域の資源や特徴を知り、魅力を積極的に発信し、イベントや活動に参加するなど、一人ひとりができることは多くあります。
私たち自身が地域の魅力に気づき、応援する行動を増やしていくことが、地域活性化の大きな一歩となるでしょう。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。