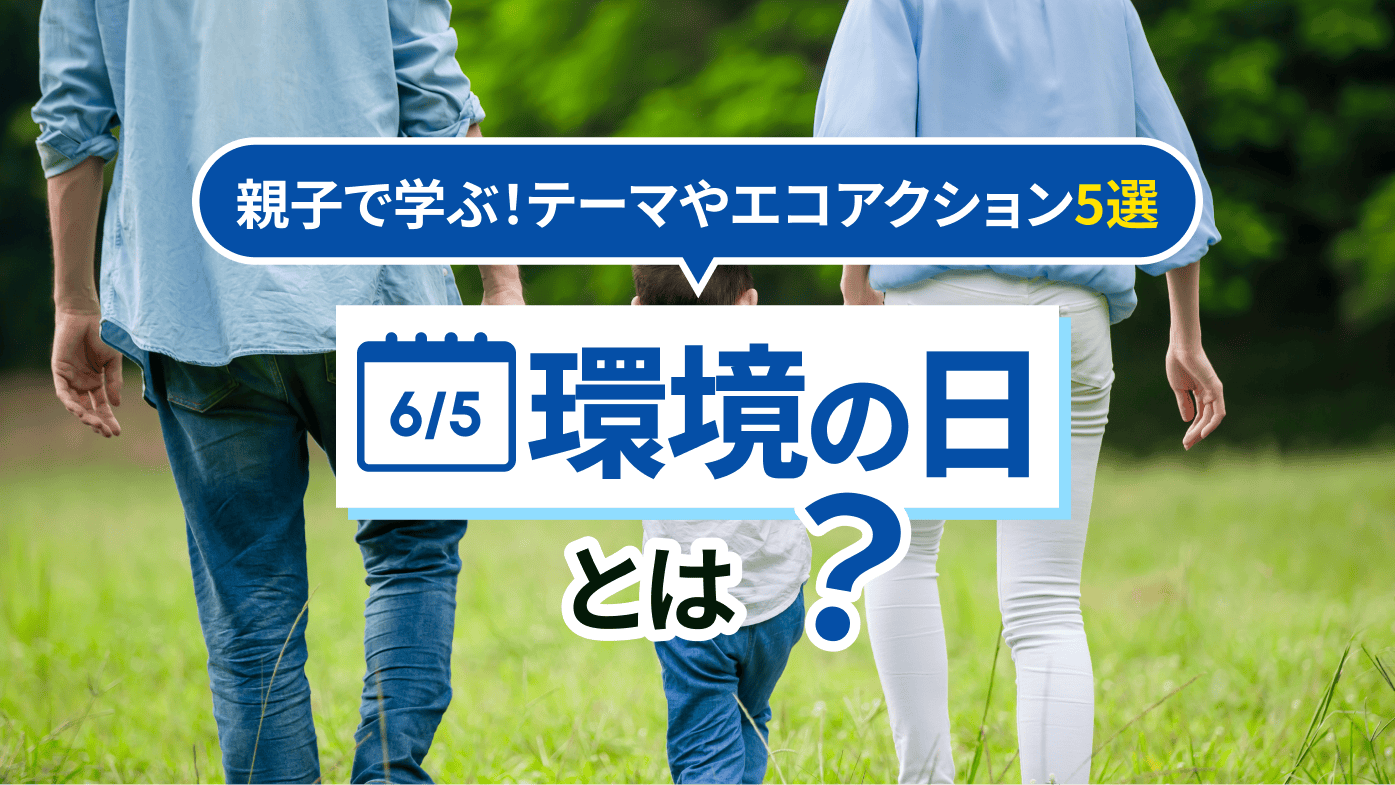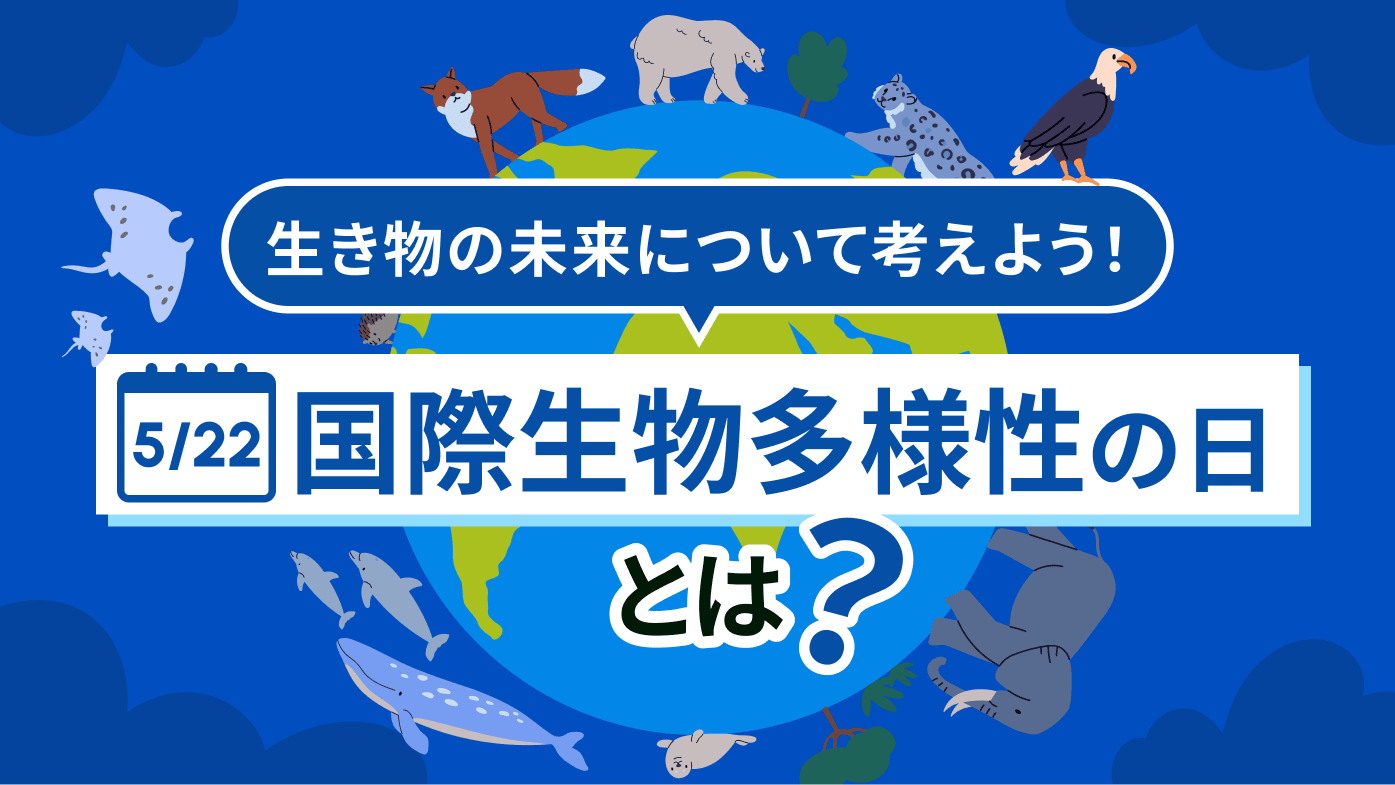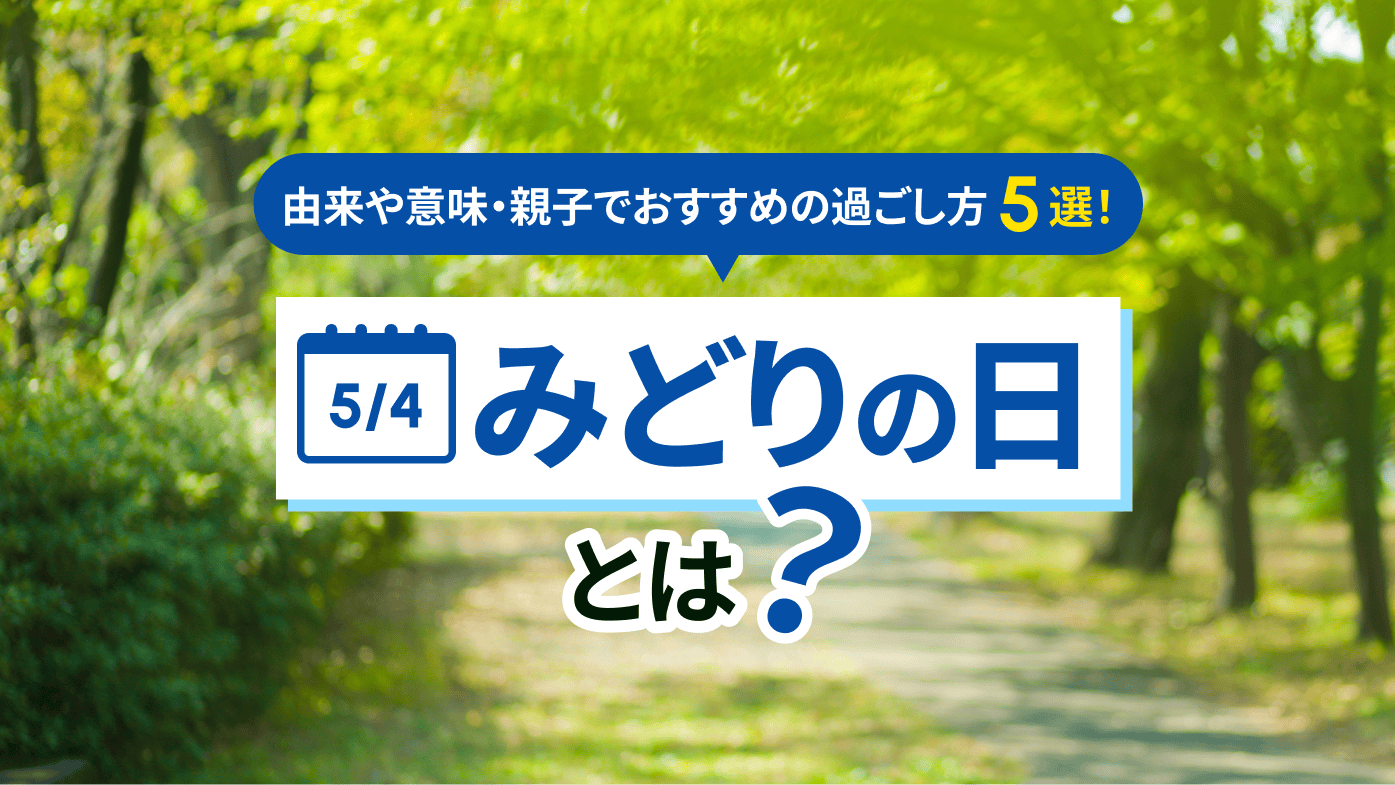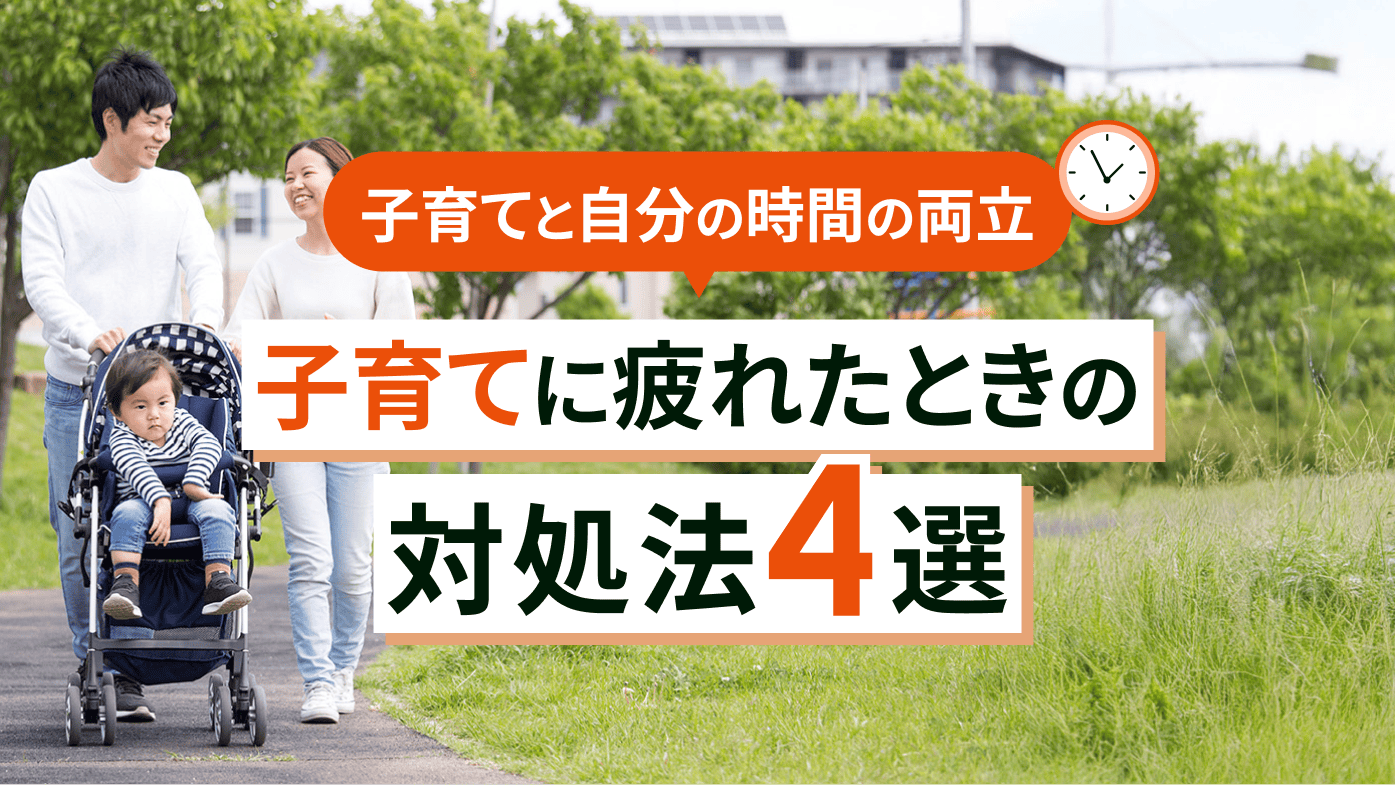
2025.05.08
【子育てと自分の時間の両立】子育てに疲れたときの対処法4選
「子育ては楽しいけれど、疲れてしまったな」「どうしてこんなに疲れてしまうんだろう」とお考えの方へ。
親になると子育て以外にも、家事や仕事などやることが多く、自分のことまで手が回らないことがあります。
本記事では、子育てに疲れてしまう原因や、疲れてしまったときの対処法について詳しく解説します。
目次
子育てをする親がさまざまな原因で疲れを感じている

子育ては、楽しさや喜びを感じられると同時に、様々な大変さを伴います。
内閣官房こども家庭庁設立準備室が1,372人の20~49 歳の男女に対して行った「子育てをして負担に思うこと」についての調査を見てみましょう。
「子育てをして負担に思うことがあると答えた人」の割合
| 子育てをして負担に思うこと | 負担に思っている人の割合(%) ※複数回答可 |
|---|---|
| 子育てに出費がかさむ | 55.6 |
| 自分の自由な時間がもてない | 46.0 |
| 子育てによる精神的疲れが大きい | 43.1 |
| 子育てによる身体的疲れが大きい | 42.6 |
| 子どもが病気のとき | 33.0 |
こちらの調査は実際には子育てをしていない方も調査対象に含まれているため、参考情報となりますが、負担に思うこととして特に多かったのが「子育てに出費がかさむ」という声です。
衣食住に関する費用はもちろんのこと、成長すると教育費など様々な費用がかかり、負担になります。
他にも、子どものお世話は24時間365日続くことで「自分の時間がもてない」という声や「子育てによる精神的・肉体的疲れが大きい」という声もありました。
また、子どもが成長してからも、保育園や幼稚園などから「熱が出た」と連絡が来てお迎えに行き、看病するために仕事を早退やお休みしなければならないときもあります。
このように、子どもが病気の時など、これまでのように仕事をすることができず、子育てならではの大変さを感じる親も多いようです。
危険信号をチェック!それって育児うつかも

子育ては大変とわかっていても、毎日自分の時間が削られていくと「悲しい」「やる気が出ない」「眠いのに眠れない」など心身に不調が出てしまいます。
これは単に身体が疲れているだけでなく、心が疲れてしまっているサインかもしれません。
ここで、うつ病の可能性をチェックする11の項目を一緒に見ていきましょう。
うつ病を疑うサイン
- 悲しい気持ち、憂鬱な気分、沈んだ気分である
- 何事にも興味がわかず、楽しくない
- 疲れやすく、元気がでない
- 気力や意欲がなく、集中できない感じがする
- 眠ろうとしても寝付けず、朝は早く目が覚めてしまう
- 食欲がわかない
- 友だちや家族など人に会いたくないと感じる
- 夕方よりも朝方の方が気分、調子が悪い
- 心配事が頭から離れない
- 失敗や悲しみ、失望から立ち直れない
- 自分を責めたり自分には価値がないと感じたりする
引用:厚生労働省
あくまで参考例ですが、チェックに当てはまる項目が多い場合や、なおかつ2週間以上続いている場合は育児ストレスによるうつ病を発症している可能性があります。
「最近心身が疲れている」「物事をネガティブに考えてしまう」といった症状を感じる場合は、無理をせず、病院に相談するのがおすすめです。
子育てで一番疲れるのはいつ?

一般的に、0歳児と2歳児の子育ては、特に疲れやすいと言われています。
理由として、「0歳児は24時間体制の育児で睡眠不足に陥りやすい」「2歳児はイヤイヤ期に突入するので精神的なストレスが急増する」といったことが挙げられます。
新生児期、特に生後3ヶ月頃までは、赤ちゃんが寝ている時以外は常に世話が必要で、親はゆっくり休む時間を取ることが難しく、ストレスが大きく溜まってしまいます。
一方、2歳頃は、子どもが自分の気持ちを伝えられるようになるため、何でも「イヤ!」と拒否するイヤイヤ期が始まる時期です。
この時期は、親にとっての修行期間とも言われ、大変さを実感する親が多いと考えられます。
子育てに疲れてしまう原因とは?

子育ては、大きな喜びを感じると同時に責任と負担を伴うため、多くの親が子育て中に疲れを感じてしまうのも当然のことと言えるでしょう。
子育ての疲れの原因には以下のようなものがあります。
- 睡眠不足
- 自分の時間が取れない
- 抱っこによる腕や腰の痛み
- 子育て・家事の両立が大変
それぞれ、具体的に解説していきます。
睡眠不足
子育て中の親が最も苦労していることには、睡眠不足が挙げられています。
新生児期から生後3ヶ月頃までは、赤ちゃんの睡眠サイクルが整っていないため、授乳やミルクのために数時間おきに起きなければならず、親の睡眠不足が深刻化しやすいです。
赤ちゃん自身も寝たり起きたりを繰り返しているため、親はまとまった睡眠時間を確保することが非常に難しい時期といえるでしょう。
また、一般的に赤ちゃんの夜泣きは生後6ヶ月頃に始まり、1歳半頃に落ち着くといわれています。
夜泣きは何をしても泣き止まなかったり、やっと寝かしつけたと思ったらすぐにまた起きて泣き始めたりするため、親はまとまった睡眠を取ることができずに心身ともに疲弊してしまうのです。
自分の時間が取れない
子育て中は子ども中心の生活になるため、自分の予定通りにいかないことが多く、常に子どものペースに合わせて予定を変更しなければいけません。
そのため、事前に予定を立てていても急に変更になったり、子育てに付きっきりになったりして、自分の時間を持つのが難しく、疲労も蓄積しやすくなるでしょう。
また、小さな子どもがいる家庭ではどこかにぶつかったり、危険なものを触ったりしないように常に注意を払う必要があり、安全面への配慮も欠かせません。
ハイハイやつかまり立ちを始めると、転倒や落下などの危険も増えるため、親はますます目が離せなくなり、ゆっくり休む時間を持つのが難しくなるのです。
一人で育児を担っている場合、パートナーが自由時間を楽しんでいるのを見て「自分だけ好きなことができない」という不公平感を感じ、不満が募ることもあります。
抱っこによる腕や腰の痛み
子育て中は、子どもを抱っこする機会が非常に多くなります。
特に新生児期は、一日中抱っこ紐や腕で抱っこしていることも珍しくありません。
このような状況が続くと、腕や腰に負担がかかり、肉体的な疲労を感じやすくなります。
また、子どもが成長して体が大きくなっても、抱っこや高い高いをせがまれることがあります。
体重が増えるにつれて抱っこする負担も大きくなるため、抱っこをするだけでも親はへとへとに疲れてしまうのです。
子育て・家事の両立が大変
親は、子どもの世話に加えて、食事の準備や掃除、洗濯などの家事もこなす必要があります。
さらに、仕事をしている場合は、育児と仕事の両立もしなければなりません。
子育てと家事、そして仕事までを両立させようとすると、どうしても自分のための休息時間が削られてしまい、心身ともに疲れてしまいます。
子育てに疲れたときの対処法4選

毎日頑張っているのに、うまくいかないことばかりで疲れてしまう…そんな風に感じている方も多いのではないでしょうか。
子育てに疲れたときに試してほしい対処法を4つご紹介します。
- 夜泣きは赤ちゃんからのサイン!気持ちに寄り添ってあげよう
- 「疲れにくい抱っこの仕方」を覚えて実践してみよう
- 24時間気を張らず、1日数分は「休む」と決めてみよう
- 子育て支援イベントに参加してみよう
それぞれ、具体的に解説していきます。
夜泣きは赤ちゃんからのサイン!気持ちに寄り添ってあげよう
赤ちゃんの夜泣きは、赤ちゃんが「寝たいのに起きてしまった」「おむつが汚れていて気持ち悪い」「お腹がすいた」など、何かを伝えようとしているサインです。
また、赤ちゃんはまだ睡眠リズムが整っておらず昼夜の区別がついていないため、夜中にうまく眠れずに泣いてしまうこともあります。
そのため、夜泣きが始まったら、まずはおむつの汚れや空腹など赤ちゃんの身体的な不快の原因を取り除いてあげられるか確認しましょう。
母乳育児の場合、授乳のリズムが整っていれば、授乳することで赤ちゃんが寝入りやすくなります。
特に、添い寝の状態で授乳すると、そのまま寝てくれることが多いようです。
授乳以外の方法としては、ママの乳首代わりになるおしゃぶりや、柔らかいぬいぐるみや毛布などを与えてみるのも効果的です。
ただし、乳児期に柔らかい毛布などを与える際は、顔が覆われることによる窒息の危険性があるため、寝入るまで絶対に目を離さないように注意し、寝たらすぐに回収することが大切です。
他にも、添い寝をしたり、おひなまきで赤ちゃんを包んであげると、ママのお腹の中にいた時のような安心感を得て、落ち着いて寝てくれることもあります。
おひなまきは股の部分がきつく巻かれていると、股関節脱臼(だっきゅう)のリスクが高くなるといわれています。
おひなまきをする際は足が自由に動けるように、ゆるく巻くようにしましょう。
それでも夜泣きが続く場合は、寝かしつけようとするのではなく、一度赤ちゃんをしっかり起こしてみるのも最終手段として有効です。
なぜならば赤ちゃんが浅い眠りから完全に目覚めきれず泣き続けている可能性もあるからです。
ここまで紹介したことを試してみたり他にも対策をしても、赤ちゃんが泣き止まないことがあるかもしれません。
赤ちゃんの夜泣きでイライラしたり焦ったりすると、その気持ちが赤ちゃんに伝わってしまうかもしれません。
夜泣きは赤ちゃんの成長とともにいつかなくなっていくものなので、おおらかな気持ちで赤ちゃんに寄り添ってあげることが大切です。
「疲れにくい抱っこの仕方」を覚えて実践してみよう
子どもを抱っこする際、猫背や反り腰の姿勢になりやすいです。
そのため、子どもと体がうまくフィットせず、余計な力が必要となり、腕や腰に負担がかかりやすくなってしまいます。
抱っこするときは、背中を伸ばしたイメージで脇を締め、肘を体につけた状態で子どもとの密着面積を広く保つようにすることで、重さが分散されて疲れにくくなります。
また、子どものお尻がおへそより少し高い位置にくるように意識すると、反り腰を防ぐことができます。
さらに、片方の腕だけに負担がかからないよう、左右の腕を交互に使うように工夫することも大切です。
手のひらや手首、腕の力だけで抱っこすると、肩こりや手指のしびれ、腱鞘炎(けんしょうえん)の原因となる場合があるので注意が必要です。
抱っこ紐の活用もおすすめで、抱っこ紐を使うと、子どもの体重を肩や腰全体で支えることができるため、腕への負担を軽減できます。
24時間気を張らず、1日数分は「休む」と決めてみよう
子育ては24時間体制ですが、子どもがおもちゃで遊んでいる時や昼寝をしている時など、1日に数分でも良いので意識的に休憩時間を取り入れることが大切です。
「この時間は休む」と決めたら、ベビーベッドや周囲に危険な物がないスペースで子どもを遊ばせ、子どもに目が届く範囲でストレッチをしたり、読書をしたりするなど、短い時間でもリフレッシュするようにしましょう。
子どもが成長すれば、数時間お昼寝をしたり、夜ぐっすり寝てくれるようになるので、もう少しの辛抱です。
どうしてもまとまった休憩時間を取りたい場合や、子どもの顔を見るとイライラしてしまうという罪悪感がある場合は、ベビーシッターや、一時預かり(一時保育)の利用を検討してみましょう。
また、パートナーとの協力や、様々なサービスの活用など、周囲の協力を得ながら、上手に息抜きをすることが大切です。
子育て支援イベントに参加してみよう
子育てが思い通りに進まなかったり、誰からも褒められなかったりすると、イライラしてしまうのは当然のことです。
そんな時は、誰かと話すことでストレスを軽減できることがあります。
子育て支援イベントなどに参加すると、子育てに関する専門家のセミナーを受講したり、専門家に子育てや仕事との両立について相談したりすることができます。
また、親子で楽しめるイベントも開催されているので、気分転換にもなるでしょう。
専門家や同年齢の子を育てるママ・パパと話す中で、効率的な家事・育児の両立方法など、役立つ情報を得られる可能性も高まります。
また、子育ての悩みや喜びを共有できるだけでなく、お互いに励まし合うことで「子育てを頑張ろう」という前向きな気持ちを取り戻すこともできます。
他にも、地域のサークルや、幼稚園・保育園などでママ友やパパ友を作り、定期的にコミュニケーションを取るのもおすすめです。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン すくすくラボ」について
公益財団法人イオン1%クラブでは、0歳から3歳までの子どもとその家族を対象とした子育て支援活動「イオン すくすくラボ」を運営しています。
子育ては、一人で抱え込まず、周囲の協力を得ながら楽しむことが大切です。
同活動では、子育てに詳しい講師によるセミナーやお悩み相談会、親子で楽しめるふれあい遊びなどを実施しており、子育て世帯に寄り添った活動に取り組んでいます。
これらの活動を通して、「イオン すくすくラボ」は子育て家庭を支援し、地域社会の持続的な発展に貢献することを目指しています。
まとめ
本コラムでは、子育てに疲れてしまう原因や、疲れたときの対処法を4選解説しました。
子育てを頑張っている方の多くは、子どもの世話だけでなく、家事や仕事も両立しているため、疲れを感じやすい状況にあります。
中には、子どもが可愛いと思いつつも、時にはイライラしたり、悲しい気持ちになったりして悩む方もいるでしょう。
子育ては「一人の人間を育てる」という大きな責任を伴うものであり、疲れてしまうのは当然です。
疲れた時は、意識的に自分の時間を作るように心がけ、家事を少しでも楽にする方法がないか、周りの人に相談してみましょう。
また「最近体調が優れない」「元気が出ない」など精神的に疲れているな、と感じたら、心のSOSサインかもしれません。
子育てで悩んだり、疲れたりしたときは無理をせずに、地域の支援やサポートを利用しましょう。
一時的に子どもを預けて、病院で医師に相談することも考えてみてください。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域発展の貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
公益財団法人イオン1%クラブでは、地域社会の持続的な発展を目指し、0歳から3歳の乳幼児や未就学児とそのご家族を対象に、育児に関する深い知識を持つ講師によるセミナーやお悩み相談会等を行い、地域の子育て世代をサポートする「イオン すくすくラボ」も運営しています。
また、小学校1年生から中学校3年生までの子どもたちが環境に関する様々な活動を行う「イオン チアーズクラブ」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、お子さまの成長に合わせたさまざまな活動も行っています。
ぜひ下のURLからご覧ください。