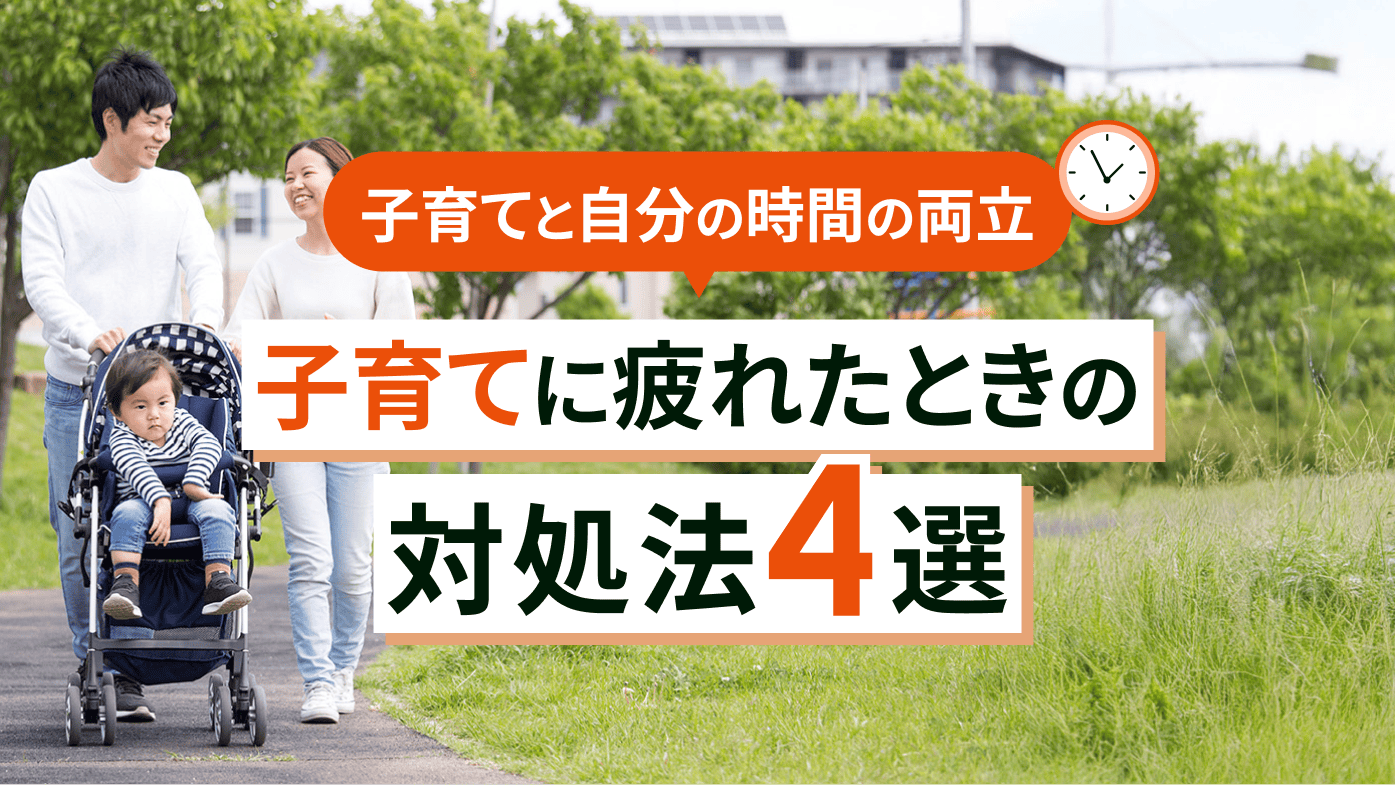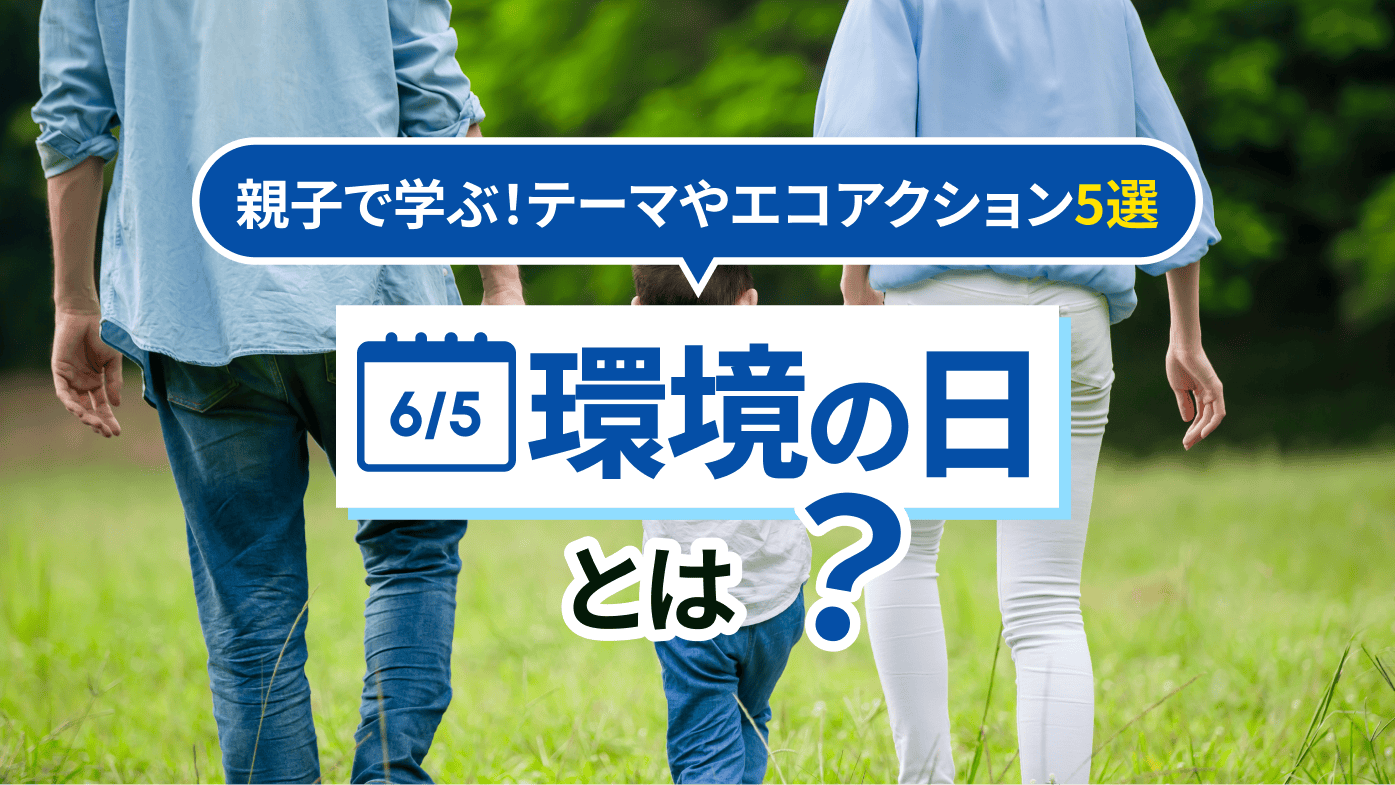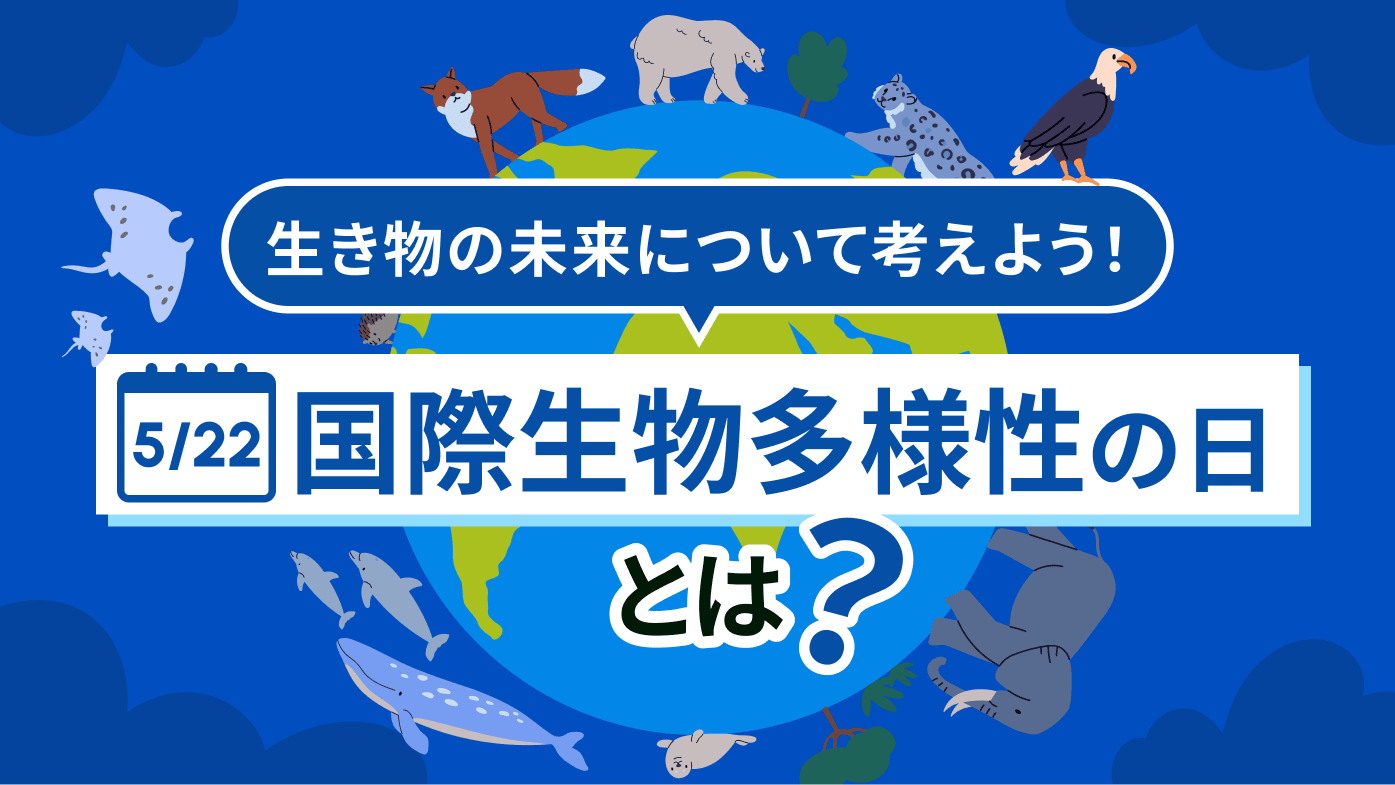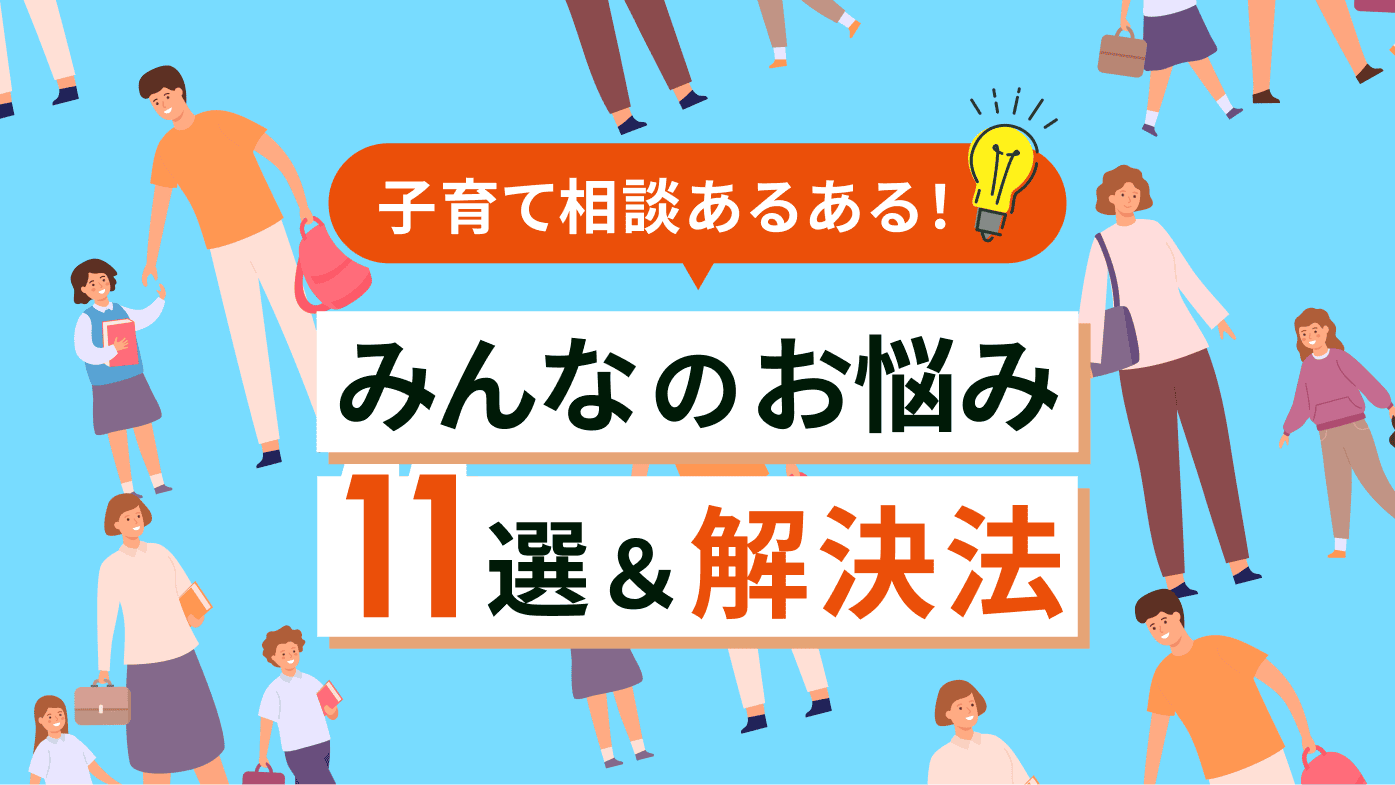
2025.05.13
子育て相談あるある!仕事との両立などみんなのお悩み11選と解決法
「子育てって悩みがつきもの」「みんなも悩んでいるのかな?」とお考えの方へ。
毎日子育てを頑張る親は、子育てに家事、仕事とさまざまなことで悩みを抱えているケースも多いでしょう。
本記事では、よくある子育ての悩みとその解決法を解説します。
目次
- 子育てで多くの親が悩みを抱えている
- 悩み1:子育てにどれだけのお金がかかるかわからない
- 悩み2:仕事と育児の両立ができるか不安
- 悩み3:パートナーが育児に参加できない・意見が合わない
- 悩み4:赤ちゃんの夜泣きにどう対応したらいいかわからない
- 悩み5:子ども中心の生活で自由な時間を持てない
- 悩み6:子どもとの接し方がわからない
- 悩み7:幼稚園・保育園に入れるか不安
- 悩み8:他の子どもとの差が気になる
- 悩み9:子どものイヤイヤ期にどう対応すれば良いかわからない
- 悩み10:食べ物の好き嫌いが多い
- 悩み11:きょうだいの育て方がわからない
- 公益財団法人イオン1%クラブ「イオン すくすくラボ」について
- まとめ
- 公益財団法人イオン1%クラブについて
子育てで多くの親が悩みを抱えている
子育ては楽しいと感じる一方、子どもを育てる中で、様々な悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
文部科学省の調査によると、子育てにおいて悩みや不安を感じている人の割合は、男性が61.8%、女性が76.4%という結果が出ており、多くの人が悩みを抱えていることがわかります。
では多くの親が子育てで抱えている悩みについて、具体的にどんな悩みがあるのか紹介していきます。
悩み1:子育てにどれだけのお金がかかるかわからない

子どもを持つ親にとって金銭的な問題は大きな悩みの種です。
子育てをするためには衣食住にかかる費用もありますし、教育費もかかります。
たとえば、幼稚園や保育園〜高校までの教育費は、公立と私立では大きな差があります。
下の表は、幼稚園から高校までの教育費平均(公立・私立)です。
| 幼稚園から高校までの教育費用の平均※ | |
| 幼稚園から高校までの教育費平均 (すべて公立の場合) | 約251万円 |
| 幼稚園から高校までの教育費平均 (すべて私立の場合) | 約1,218万円 |
また、教育費がかかるタイミングは一定ではないため、毎月の教育費にプラスでまとまった費用が必要になる月が出てくるケースも考慮しなければなりません。
そのため、教育費や生活費を含めた子育て費用がどのくらいかかるのか、事前に想定するのが難しいと感じる親も多いでしょう。
対策
子育てにおけるお金の悩みは、多くの親が悩みを抱える問題です。
特に、初めての育児ではトータルでの費用感がイメージしにくいこともありますよね。
「どのくらいのお金を貯蓄すれば良い?」「どんな制度を利用すれば良い?」と悩む親も多いでしょう。
経済的な対策としては、児童手当や保育料補助、各種支援制度の活用、家計の見直し、そしてこども保険(学資保険)※1を活用した貯蓄などが挙げられます。
国や自治体の代表的な制度としては、以下のようなものがあります。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 出産育児一時金 | ・出産した被保険者(保険に加入している人)と被扶養者(保険に加入している人に扶養されている人)に支給される一時金 ・健康保険の被保険者・被扶養者なら、一律50万円※2を受け取ることができる |
| 出産手当金 | ・出産のために会社を休んだ際に支給される手当 普段の給料の約2/3が支給される ・健康保険出産手当金支給申請書を用意し、必要事項を記入する ・医療機関の証明欄があるため、出産した病院で記入してもらう必要がある ・勤務先が必要事項を記入後加入先の健康保険組合へ提出してくれる場合が多い |
| 幼児教育・保育の無償化 | ・次に該当する子どもの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無料になる - 3歳児から5歳児までの子どもは、世帯の所得に関わらず無料 - 0歳児から2歳児までの子どものうち、住民税非課税世帯は無料 |
| 乳幼児に係る医療費の援助 | ・乳幼児や子どもが医療を受けた際に発生する自己負担額の一部または全部を、自治体が助成してくれる制度 ・助成方法には「現物給付」と「償還払い」があり、現物給付の場合は病院での支払いが不要、償還払いの場合は一度自己負担して、2~4か月後に払い戻しを受ける |
| 児童手当 | ・児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給されるお金 ・3歳未満は月額1万5,000円(第3子以降は3万円) ・3歳以上から高校生年代までは月額1万円(第3子以降は3万円) |
| 高等学校等就学支援金 | ・国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件(世帯年収が590万円未満の場合と、590~910万円未満の場合で支給額が変動※3)を満たす世帯の生徒に対して、 授業料に充てるため、国から支給されるお金 ・「課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額」で算出された額を支給(家庭によって異なる) |
| 高等教育の修学支援新制度 | ・世帯年収や資産の要件を満たしており、進学先で学ぶ意欲がある子どもたちの進学を支援する制度 ・授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する |
これらの制度や支援について詳しく知りたい場合は、お住まいの市役所や区役所の窓口に相談することをおすすめします。
他にも、お金に関する幅広い知識を有するファイナンシャルプランナー(FP)に相談できるサイトの利用もおすすめです。
※1 教育資金を貯めていける貯蓄性を備えた保険。あらかじめ決めた時期に、金額を学資金として受け取ることができる。
※2 2025年3月時点での情報
※3 世帯の構成によって変動する可能性もあります。
悩み2:仕事と育児の両立ができるか不安

家庭の状況によって異なりますが、産後は会社の育休を利用したり、子育てがある程度落ち着いたら再就職しようと考えていたりと、仕事と育児の両立も悩みの材料になります。
しかし、復職をしても子どもが小さいうちは病気にかかりやすく、幼稚園や保育園から急なお迎えの連絡が来たり、仕事を早退や休まなければならなかったりすることも多いです。
このような状況で、仕事と育児の両立に大きな負担を感じている親が多くいます。
対策
親は子どもが生まれると「子育ても大切だけれど、仕事も大切」「どうやって両立すれば良いだろう」と悩んでしまうケースも多いでしょう。
「子どものため、家族のためには仕事をしなければいけないのに、いままでよりも収入が減ってしまった」という親も多いかと思います。
子育てと仕事の両立に悩む親は非常に多く、人それぞれさまざまな制度の活用をしたりしています。
子育てと仕事の両立の負担を軽減するためには、会社にどのような制度があるかを確認し、活用することも検討しましょう。
特に以下のような制度は、子育てする家庭にとって助かるものとなるでしょう。
| 種別 | 制度 | 概要 |
|---|---|---|
| 法律が定めている制度 | 子の看護休暇制度 | ・小学校就学前の子どもが病気やけがをした場合に、従業員が看護を目的に取得できる制度 ・原則として子ども1人につき年間5日(対象となる子どもが2人以上の場合は10日)取得できる |
| 育児時間の制度 | ・1歳未満の子どもを育てる女性が、法定の休憩時間とは別に、育児のために1回30分の休憩を1日に2回取得できる制度 ・雇用形態は問わず、育児時間を申請できる | |
| 育児休業制度 | ・原則1歳未満のこどもを養育するための休業制度 ・育児休業は法律が定めている制度であり、勤務先の就業規則に育児休業に関する定めがなくても取得できる | |
| 短時間勤務制度 | ・子育てや介護などの両立支援を目的に「育児・介護休業法」で定められた制度 ・3歳未満の子どもを養育する従業員は、一定の条件を満たせば所定労働時間を6時間までとする権利がある | |
| 勤務先によって申請できる制度 | フレックス勤務制度 | ・従業員自身が仕事を始める時間と仕事を終えて退勤する時間を、自由に設定できる制度 ・必ず出勤する必要がある「コアタイム」と、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」がある※4 |
| 在宅勤務制度 | ・自宅に居ながら働く制度 ・必要に応じて週に数回出社するように取り決めている場合も含まれる |
例えば、フレックスタイム制度を利用すれば、子どものお迎えの時間に合わせて勤務時間を調整できます。
短時間勤務制度を利用すれば、子育てに集中する時間を増やすことができるでしょう。
また、パートナーや両親に協力を得たり、食洗機や洗濯乾燥機、ロボット掃除機などの家電製品を導入したりして家事の負担を軽減することも有効です。
制度や協力を賢く活用することで、子育て時間の確保だけでなく、自分の時間を取ることにもつながるため、心身的な負担の軽減にもつながります。
利用できる制度や周囲の協力を上手に活用して、子育ての時間を確保するだけでなく、自分自身の時間も大切にしましょう。
※4 コアタイム:1日の中で、必ず出勤していなければならない時間帯
フレキシブルタイム:コアタイムの前後数時間にあたる、自由に出退勤できる時間帯
悩み3:パートナーが育児に参加できない・意見が合わない

子育てにおいて、気軽に物事を相談できる相手がいることは重要です。
しかし、パートナーの仕事が忙しいなどの理由で育児に参加できない家庭もあります。
また、実際に子育てに参加する機会が少ないと子どもの成長に関しての認識が異なり、お互いの意見が合わないというケースも考えられるでしょう。
他にも「自分の子どもはこう育てたい」など、理想とする子育てプランがある場合も同様でパートナーと意見が合わず心身の疲労が溜まるという悩みを抱える方もいます。
対策
「パートナーが仕事で忙しく、なかなか子育てに協力してもらえない」「子育てに関する意見が合わなくて辛い」というお悩みは多くのご家庭で聞かれます。
このような状態になると、片方の親が一人で育児を担わなければならず、心身ともに疲れ果ててしまうという状況も考えられるでしょう。
こういった場合は、パートナーの仕事の状況や会社の制度、利用できる支援などを活用しつつ、夫婦で協力体制を築いていくことが大切です。
パートナーの仕事が忙しいなどの理由で育児に参加できない場合、まずはパートナーが勤めている会社で、子育て支援に関する制度が利用できるかどうかを確認してみましょう。
「育児休業制度」は性別を問わず利用できますし、企業が「両立支援等助成金制度」※を導入している場合、子育て支援に対する社内での制度を完備している可能性もあるでしょう。
他にも、国ではパートナーが出産直後の男性に対して休暇取得を促進し、男性の家事や育児への参画を促す「さんきゅうパパプロジェクト」など、パートナーが子育てに参加しやすくなる制度や取り組みを行っていますので、ぜひ市役所などで確認してみてください。
また、必ずしもパートナーと意見を合わせなければいけないということはありません。
大切なのは、お互いが子どものことを思っての意見であるということを理解することです。
まずは、相手の意見をしっかりと聞き、そのうえで自分の意見も伝え、お互いが納得できる方法を探していくことが大切です。
どうしてもお互いの意見が合わず、悩む場合は同年代のママ・パパや、子育て経験があるママ・パパはこんなときどうしたのかを相談してみると良いでしょう。
また、子育てカウンセラーなどプロの意見を聞いてみる方法もあります。
※職業生活と家庭生活を両立できる雇用環境整備に取り組む事業主を支援する制度
悩み4:赤ちゃんの夜泣きにどう対応したらいいかわからない

赤ちゃんが夜中に何度も泣くと、親は十分な睡眠を取ることができず、心身ともに疲れてしまいます。
赤ちゃんの夜泣きも日によって異なり、まるで火がついたように激しく泣き続けることもあり、親は対応に苦労するでしょう。
何をしても泣き止まない時、なぜ泣いているのかがわからない時、親は不安と焦りでパニック状態に陥ってしまうこともあります。
夜泣きは、子育てにおける大きな負担の一つといえます。
対策
赤ちゃんの夜泣きは「どうして泣くんだろう」「親が見落としていることがあるのかな」「体調が悪いのかな」など、不安と心配で心がいっぱいになります。
赤ちゃんが「お腹がすいたよ」「眠いけど上手に眠れなくて困っているよ」と伝えてくれれば良いですが、現実はそうもいきませんよね。
毎日夜泣きの対応をしていると心身ともに疲れ果ててしまう親も多いです。
赤ちゃんが夜中に泣く原因は、成長途中で睡眠リズムが定まっていないことや、「お腹がすいた」「おむつが汚れている」といったサインを示している場合が多いと考えられます。
まずは、どのような理由で泣いているのかを探ってみましょう。
もしごはんやおむつの問題ではないようであれば、添い寝で赤ちゃんに安心感を与えたり、ママの乳首代わりになるおしゃぶりを使ってみるのも一つの方法です。
また、母乳育児の場合は、授乳のリズムが整っていれば、授乳そのものが赤ちゃんを落ち着かせる役割を果たし、寝かしつけをスムーズにしてくれるでしょう。
特に、添い寝をしながら授乳すると、そのまま赤ちゃんが眠ってくれるかもしれません。
一方で、何をしても泣き止まない場合は、無理やり寝かせようとせず、いったん赤ちゃんをしっかり目覚めさせるという選択肢もあります。
疲れすぎてぐずっているときは、一度落ち着きを取り戻してもらうほうが、結果的にスムーズに寝かしつけできるケースがあるのです。
このように、夜泣きの原因や対処法を理解しておくと、赤ちゃんを落ち着かせて寝かしつけやすくなるだけでなく、自分自身の睡眠時間も確保しやすくなります。
親子双方が無理なく夜を乗り切るためにも、赤ちゃんのサインに寄り添いながら、状況に合わせた対策を見つけていきましょう。
悩み5:子ども中心の生活で自由な時間を持てない

子どもが幼い時期は、生活の中心が子どもになりがちです。
そのため、一人で外出したり、友達と遊びに行ったりしたいと思っても、「子どもを誰に預けたら良いのか」「自分の目が届かない場所で何かあったらどうしよう」といった不安や心配が頭をよぎり、なかなか行動に移せない親も多いです。
また、「子どもを置いて遊びに行くなんて、母親としてどうなのだろうか」「周りの人に批判されるのではないか」といった罪悪感や周囲の目を気にして、外出をためらってしまうケースも少なくありません。
このような状況は、親の息詰まりやストレスにつながりやすく、子育ての負担を増大させる一因となっています。
対策
子ども中心でなかなか自由な時間が持てないと、心身ともに疲れ果ててしまいます。
ただ、子どもが成長すれば、数時間お昼寝をしたり、夜ぐっすり寝てくれるようになったり、一人で静かに遊んでくれるようになるので、もう少しの辛抱です。
自由な時間を持てないときは、パートナーと交代でリフレッシュの時間を取る方法があります。
また、1日の中で数分は休むと決めて、安全を確保したスペースで子どもを遊ばせながら休憩を取る方法もおすすめです。
またベビーシッターや一時預かり、ファミリー・サポート・センターなどの活用を検討しても良いでしょう。数時間から1日単位で子どもを預かってくれるサービスもあります。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| ベビーシッター | ・子どものお世話全般を引き受けてくれるサービス ・対応時間は利用するサービスによって異なる ・場所は自宅や指定した場所など融通が利きやすい |
| 一時預かり | ・市区町村や保育園によって実施しているサービス ・数時間から1日単位で子どもを預かってもらえる ・一定の条件を満たせば無償で利用できるところもある (保育の必要性があると判断した場合など) |
| ファミリー・サポート・センター | ・行政がおこなっている子育て支援サービス ・保育園や幼稚園の送迎から一時預かりまで行っている |
子育ては、子どもの成長を見られることで楽しいと感じる瞬間も多いですが、時には「疲れたな」「ちょっとリフレッシュしたいな」と思うものです。
どうしても自分の時間が欲しいというときは、無理をせずパートナーと話し合って解決策を見つけたり、利用できるサービスを活用したりしてリフレッシュしましょう。
悩み6:子どもとの接し方がわからない

毎日子どもと接する中で、「どう対応するのが正しいのか」「この子の気持ちを理解できているのか」と悩む親は少なくありません。
赤ちゃんは言葉を話すことができないため、泣いたりぐずったりすることで、自分の気持ちを表現します。
成長して話せるようになっても、大人と同じように複雑な感情や要望をうまく伝えることは難しいです。
親は、子どもの行動や表情から「お腹が空いているのか」「おむつを替えたいのか」「暑いのか寒いのか」「遊びたいのか」「何かが嫌なのか」など、子どもの気持ちを理解しようと努めますが、その判断は容易ではありません。
判断に困り、子どもとの接し方がわからず、自信を失ってしまう親も多いでしょう。
対策
子どもへの上手な接し方がわからないということは、親にとって大きなストレスです。
子どもがグズったとき「どうしたら良いだろう」「子どもの気持ちがわからないなんて親失格だ」と辛い気持ちになります。
特に理由もわからず子どもが泣き止まないときは自信を失う親もいるでしょう。
しかし、子どもとの接し方に正解はありません。
親子は一緒に成長していくもので、接し方もゆっくり学んでいけば良いのです。
例えば、まだ言語の発音ができない赤ちゃんの場合、赤ちゃんが感じていることを声に出して伝えてあげましょう。
たとえば、赤ちゃんが外を見ていたら「何か音がするね」「良い天気だね」など、赤ちゃんが感じていることをイメージして伝えてあげると嬉しがります。
赤ちゃんは自分が見ているもの、感じていることを話しかけてもらえるのが大好きです。
泣いているときも「お腹がすいたのかな?」「オムツが汚れたのかな?いやだよね」と優しく声がけをしてあげると良いでしょう。
少し大きくなってきたら、子どもの気持ちに共感するように心がけたり、できるようになったことを褒めてあげたりすると喜びます。
親が自分の話や気持ちに共感してくれることで、信頼を感じますし、日常的に褒めてあげることで「自分をちゃんと見ていてくれている」と安心感につながるのです。
また、子どもとの接し方に悩む親の中には「叱り方がわからない」「悪いことを注意すると泣いてしまうので困っている」という方もいるでしょう。
そんなときは次のポイントを意識してください。
- ダメ!危ない!など単語だけで伝えようとせず何がダメかを伝える
- 悪いことをしたときや、注意したいときはちゃんとわかりやすい言葉で伝える
- 叱る理由は1回で一つに限定する
- 感情的に叱らない・注意しない
子どもを叱ったり注意したりするとき、感情的になったり「ダメ!」「危ない!」「何やってるの!」など単語を使う方が多いかもしれません。
しかし、単語だけでは何がダメで、危ないのかが子どもに伝わりません。
わかりやすく何がダメで何が危ないのか伝える必要があります。
他にも「この間も言ったよね」「あれも悪い、これも悪い」など今、叱る理由ではないことをまとめて叱るのも、子どもは何に叱られているのかがわからなくなります。
叱るときや注意するときは、冷静に子どもがわかりやすい言葉で伝えることが大切です。
また叱ったあとは、いつまでも長引かせず「さっきは叱ったけれど、ママ/パパは〇〇が大好きだよ」「今度からは気を付けようね」とフォローを入れてあげると良いでしょう。
悩み7:幼稚園・保育園に入れるか不安

厚生労働省の調査では、2024年4月時点で全国に2,944人の待機児童が存在し、保育園や幼稚園に入園できない子どもたちがいます。
保育園は、保護者の代わりに日ごろの保育を行うことを目的とした施設です。
保護者が共にフルタイムで働く場合や、ひとり親家庭の場合など、仕事と子育てを両立するためには保育園への入園が重要となるでしょう。
「仕事に復帰したいから保育園を探しているのに、いつになっても空きが出ない」「いつになっても保育園に入園できない」と悩む親も少なくありません。
一方、幼稚園では、年齢に合ったクラスに空きがあれば入園できるケースもあります。
ですが、幼稚園は教育を主な目的とする施設のため、保育時間が短いことが多く、親が共にフルタイムで働く場合や仕事に復帰したい場合にはあまり適していません。
これは、仕事と子育ての両立を目指す上で大きな壁となっています。
対策
子どもにとって幼稚園や保育園は新しい環境で、成長を促すためにも重要です。
しかし、待機児童問題や、地域に子どもが多い場合「入りたくても入れない」という状況に陥って仕事に支障が出るケースもあります。
「仕事をしなければいけない」「でも預けるところがない」という状況は、精神的に追いつめられてしまいますよね。
保育園や幼稚園の入園に不安を感じている場合は、まず「入園が難しくなる理由に該当するものはあるか」をチェックしてみると良いでしょう。
幼稚園は親が働いていない状態でも空きがあれば入園できる場合もあります。
一方、認可保育園では「指数(点数)」によって入園の可否が決まり、点数が高いほど入園しやすくなります。
一般的に、両親がフルタイムで共働きをしている世帯は保育の必要性が高いと判断されて高得点になります。
しかし、事情があって親が働いていない状況や、家の近くに子どもの面倒を見てくれる祖父母などがいる場合、保育園の必要性が低いと判断されてしまう場合もあります。
他にも「地域で人気の幼稚園や保育園を希望している」「年齢の倍率が高いクラスへの入園を希望している」なども、入園しにくくなる可能性があります。
ただ自治体によっては「ひとり親家庭」「兄弟がすでに希望している園に通っている家庭」が優先して入園できる場合もあるようです。
幼稚園や保育園への入園率を高めるためには
- 「パート勤務をフルタイムに変更する」
- 「第一希望だけでなく第三希望まで視野を広げる」
- 「途中入園や倍率が低いクラスへの入園を検討する」
などの方法を検討してみると良いでしょう。
また、事情があって親が働くことができない場合は、市役所や区役所で「こども誰でも通園制度」について相談してみることをおすすめします。
この制度は、親が就労していなくても、満0歳6ヶ月から満3歳未満の子どもを保育園に預けることができるものです。
本制度は2026年からは全国的に検討される予定ですが、2026年以前でも、保育園によっては空き状況に応じて、「入園後数ヶ月以内に就労開始すること」を条件に入園できる場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
悩み8:他の子どもとの差が気になる

子どもが幼稚園や保育園に通い始めると、他の子どもと比べて、自分の子どもは発達や成長が遅れているのではないかと不安を感じることがあります。
たとえば「ご飯を食べる量が他の子より少ない」「トイレトレーニングが進まない」など、他の子どもと比較して焦ってしまう親は少なくありません。
子どもの成長には個人差があるということを理解していても、どうしても周りの子どもと比べてしまい、悩んでしまうことがあります。
特に初めての子育てでは、インターネットや育児本で得た情報と異なると、自分の育て方に何か問題があるのかもしれないと不安になることもあるでしょう。
対策
「うちの子って他の子よりも成長が遅い?」という感覚は、いつも子どもを近くで見ている親だからこそ感じるものです。
また幼稚園や保育園に入って、他の子はできていることを自分の子どもはできていなかったという現実を突きつけられた親の辛い気持ちは、はかり知れません。
「どうしてこんなことができないの?」「他の子はできるのに」と他の子との差を気にして子どもにきつくあたってしまいそうになる親も少なくはないでしょう。
しかし、子どもの発達過程は必ずしも一緒ではないため、他の子と比べず、見守ってあげることが大切です。
たとえば、食べる量が少ない子の中には、生まれたときの体重が小さく年齢に対して成長がゆっくりという子もいます。
他にも、あまり運動をしないのでお腹がすかない子や、胃や腸での消化液が少なめで消化に時間がかかり、お腹がすくまでの時間が長い子もいるでしょう。
食べる量は子どもによって異なりますし、〇歳児検診で指摘されたことがない場合や、成長曲線に沿って身長体重が伸びてきているのであれば、心配する必要はないでしょう。
次に、トイレトレーニングが進まないときの理由として次のものが挙げられます。
- オムツの方が楽だと思っている
- 遊んでいて今していることを中断したくない
- イヤイヤ期で親の言うことにはイヤと言いたい時期
- おしっこやうんちが溜まっているという感覚がまだ未熟
- トイレトレーニングに失敗したとき「どうしてできないの?」など叱ってしまったことがある など
「イヤ」というお子さんの様子や、これまでのトイレトレーニングを振り返ると「もしかして」と感じるヒントが隠れているかもしれません。
他にも、発達で気になることがあれば一人で悩まず、病院や子育て支援センター、〇歳児検診などで相談してみると良いでしょう。
悩み9:子どものイヤイヤ期にどう対応すれば良いかわからない

イヤイヤ期とは、自己主張が強くなって自分の気持ちを押し通そうとする時期です。
1歳後半〜3歳ごろまでの時期に「イヤ」を繰り返すことが多くなります。
イヤイヤ期は、子どもの成長過程における自然な姿ではありますが、その対応に多くの親が悩まされています。
この時期の子どもは、「なんでも自分でやりたい!」「イヤだ!」という強い自我が芽生え始め、思い通りにならないと感情を爆発させてしまうのです。
子どもの成長の喜びを感じつつも、親にとっては試練の時期と言えます。
対策
イヤイヤ期が起こりやすい2歳頃は「魔の2歳」と呼ばれるほど、親を悩ませる時期です。
また、この時期は何でも自分でやりたがるので、保育園の登園前などの忙しい時間帯に「靴を自分で履きたい」「私、ぼくがやりたい」と言われると親もイライラしてしまいます。
そしてイライラしたことに自己嫌悪を感じて悲しくなるなど親子ともに辛い時期です。
イヤイヤ期は親を困らせる時期ではなく、子どもが大きく成長している時期です。
「成長しているんだ」と考え、子どもに沿った対処法で乗り切りましょう。
イヤイヤ期への対策としては、次のものが挙げられます。
- 基本的には「やりたい」を否定しない
- イヤという気持ちを受け入れてあげる
- 気持ちを切り替えるワンクッションを挟んで行動を促す
イヤイヤ期は「自分でやってみたい」という意欲が強まる時期です。
危ないことでなければ、基本的にやりたいことを否定せず「やってみようか」とチャレンジを促してあげましょう。
もし、時間がないときに「これがやりたい」といわれたら、途中まで手伝ってあげて仕上げを一人でやらせてあげると、子どもは満足感や達成感を得ることができます。
次にイヤイヤが始まったら「そっか。嫌なんだね」と共感し、その上で何が嫌なのかをゆっくりと時間をかけて聞いてあげると素直に話してくれるかもしれません。
このときに「これが嫌なの?」「あれが嫌なの?」など親が率先して聞くと「イヤ」が始まる可能性もあるので、子どもが話すのをじっくり待つことが大切です。
他にも、何かをして欲しいとき、急に「〇〇しよう」と進めるのではなくて「テレビが終わったらご飯を食べよう」「お絵描きが終わったらお風呂に入ろう」など、ワンクッションを置くと素直に行動してくれるかもしれません。
悩み10:食べ物の好き嫌いが多い

子どもの好き嫌いは、2歳頃になると現れ始めます。
親は、子どもの健康を考えて様々な食材を使った料理を工夫して作るものの、「これは嫌い」と食べてもらえないことが増えていきます。
「ちゃんとご飯を食べなさい」と無理強いされると、子どもは食事の時間を楽しいと感じられなくなってしまいます。
さらに、好き嫌いを叱られると、イヤイヤと言って泣き出してしまう子もおり、親にとっても子どもにとっても、食事の時間が辛い時間になってしまうことがあります。
対策
子どもの好き嫌いが多くて困っている、という悩みを持つ親は非常に多いです。
子どもは大人のように「ごめんね、これは好きじゃないから食べられない」と丁寧に言ってくれるわけではなく、イヤだからとお皿ごとひっくり返してしまうこともよくある話です。
成長のためにしっかり食べて欲しい気持ちと、予想外な行動をされてイライラが溜まる気持ちで親は心身ともに疲れてしまいます。
子どもの好き嫌いが多くて心配なときは、食べる量を自分で選んでもらったり、次のご飯で何も言わずに出して様子をみたりと子どものペースで克服することが大切です。
特に、食べる量を自分で選んでもらうと「自分で選んだから食べられるかもしれない」とすんなり食べてくれる可能性もあります。
他にも、苦手な食材を細かく刻めば食べられるかもチェックしてみましょう。
細かく刻めば食べられる場合、食べ物の触感やニオイが気になるのかもしれないなど、好き嫌いを克服するための対策が立てやすくなります。
また、親子で子どもが苦手な食材を使った料理を作ることで「自分で作ったものだから食べてみよう」という気持ちになってくれる可能性もあるでしょう。
子どもに好き嫌いがあるのは、本能的に苦手とする味があるためです。
たとえば、苦味は毒を含んでいる食べ物、酸味は腐敗した危険な食べ物だと認識する本能があるため、子どもの多くは苦味と酸味は苦手という場合が多いです。
そのため、味付けを変えてみると食べてくれるかもしれません。
子どもの好き嫌いによる栄養の偏りを心配して「嫌いでも頑張って食べてみよう」と促す親も多いですが、嫌なものを食べさせられることで、さらに食べなくなってしまう可能性もあります。
まずは子どものペースに合わせてさまざまな方法で好き嫌いの克服にチャレンジしてみましょう。
悩み11:きょうだいの育て方がわからない

きょうだいそれぞれに合った適切な育て方が分からず、悩む親は多いです。
例えば、上の子には「我慢しなさい」と言うことが多い一方で、下の子には甘くなってしまう、あるいは下の子に対して「お兄ちゃん/お姉ちゃんみたいにしなさい」と比較してしまうなど、無意識のうちに子どもたちを区別してしまうケースもあります。
親としては、どちらの子も平等に大切に思っていますが、忙しさや疲れからつい片方の子だけを「だだをこねないで」「言うことを聞きなさい」「いい加減にしなさい」などと叱ってしまうこともあるでしょう。
複数の子どもを育てる難しさを感じている親は少なくありません。
対策
きょうだいを育てるご家庭では「どうしても下の子に目が行ってしまう」「きょうだいでケンカしていると、上の子だけ叱ってしまう」というケースも多いでしょう。
また下の子に対しても「上の子はこんなにわがままじゃなかったのに」「どうしてお兄ちゃん、お姉ちゃんみたいに言うこときいてくれないの?」とイライラする場合もあります。
きょうだいでも性格や考え方、好きなものが異なる可能性もあるため「きょうだいをどうやって育てたら良いのか」「対応の仕方がわからない」という親もいるでしょう。
きょうだいの育て方で大切なことは、どちらにも平等に接することです。
たとえば、きょうだいがケンカしているとき「どうしてケンカになったのか」を聞き、下の子が悪いのであれば「それは良くないことだよ」と悪いことは悪いと伝えます。
上の子には「お兄ちゃん、お姉ちゃんも大変だよね」「ちゃんと下の子と遊んであげてえらいね」など、上の子の苦労や立派さを褒めてあげると良いでしょう。
下の子には「お兄ちゃん、お姉ちゃんが遊んでくれて嬉しいね」と声をかけたり、公園などで遊ぶ場合は「お兄ちゃん、お姉ちゃんと順番に遊ぼうね」など平等に接します。
上の子は特に、下の子がうまれると「自分は構ってもらえない」「お兄ちゃん/お姉ちゃんだから」と我慢する機会が増えます。
まずは上の子に対して「ちゃんと見ているよ」と伝える姿勢も大切です。
また、きょうだい同士で比較することは、子どもの自己肯定感を低下させる可能性があるので避けましょう。
他にも、時折親が「お兄ちゃん/お姉ちゃんはこう思っているんじゃないかな」「弟/妹はこうしたら喜ぶと思うよ」と気持ちを代弁してあげることで、子どもが相手の立場や気持ちを想像しやすくなり、他者理解や思いやりを育むきっかけになります。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン すくすくラボ」について
公益財団法人イオン1%クラブでは、0歳から3歳までの子どもとその家族を対象とした子育て支援活動「イオン すくすくラボ」を運営しています。
子育ては、一人で抱え込まず、周囲の協力を得ながら楽しむことが大切です。
同活動では、子育てに詳しい講師によるセミナーやお悩み相談会、親子で楽しめるふれあい遊びなどを実施しており、子育て世帯に寄り添った活動に取り組んでいます。
これらの活動を通して、「イオン すくすくラボ」は子育て家庭を支援し、地域社会の持続的な発展に貢献することを目指しています。
まとめ
子育てには様々な悩みがつきものですが、それと同時に大きなやりがいもあります。
子どもの笑顔や日々の成長を間近で見守ることができるのは、子育てならではの喜びです。
子育てで悩んだ時は、一人で抱え込まず、周囲の人に相談したり、相談窓口を利用したりするなど、様々なサポートを活用しましょう。
子育ての喜びを分かち合い、共に成長していく中で、かけがえのない時間を過ごすことができるはずです。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域発展の貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
公益財団法人イオン1%クラブでは、地域社会の持続的な発展を目指し、0歳から3歳の乳幼児や未就学児とそのご家族を対象に、育児に関する深い知識を持つ講師によるセミナーやお悩み相談会等を行い、地域の子育て世代をサポートする「イオン すくすくラボ」も運営しています。
また、小学校1年生から中学校3年生までの子どもたちが環境に関する様々な活動を行う「イオン チアーズクラブ」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、お子さまの成長に合わせたさまざまな活動も行っています。
ぜひ下のURLからご覧ください。