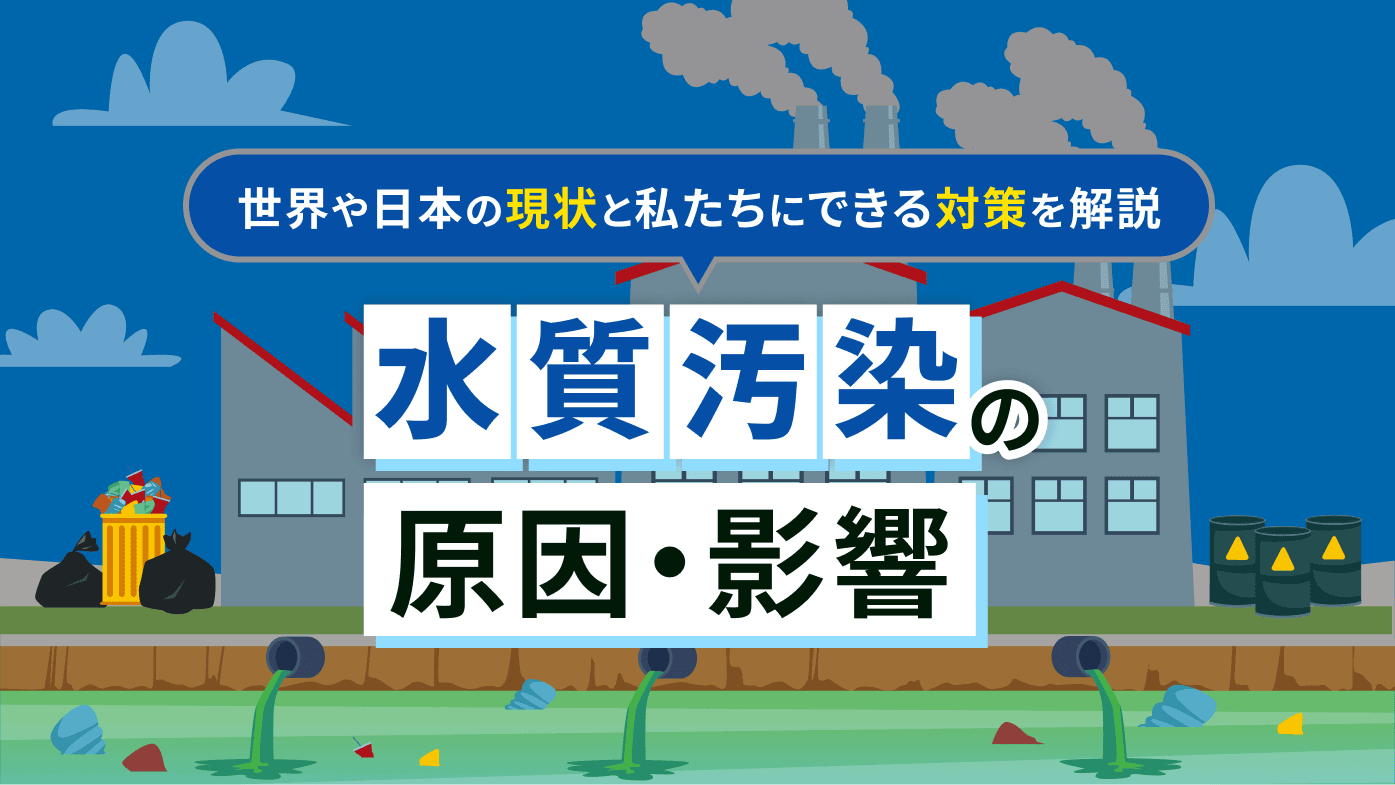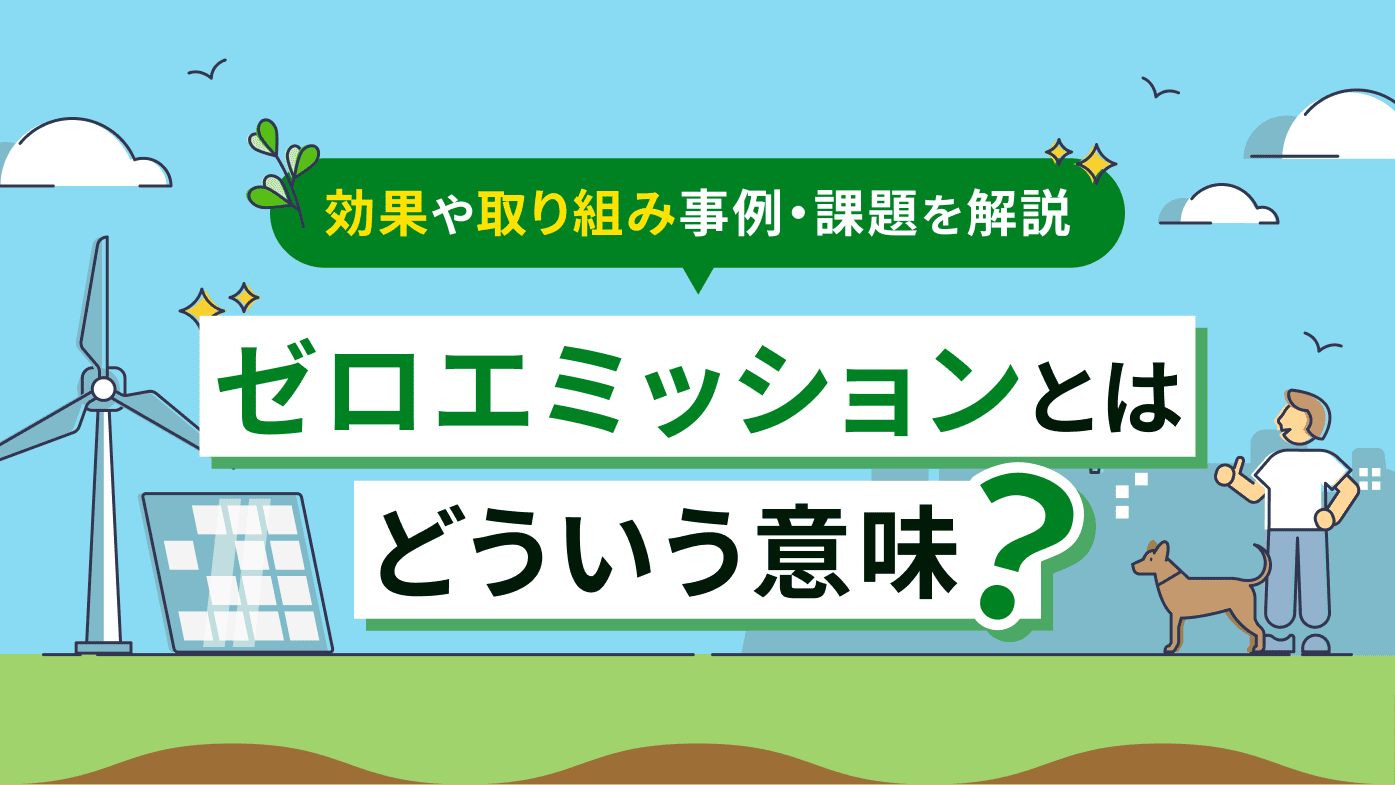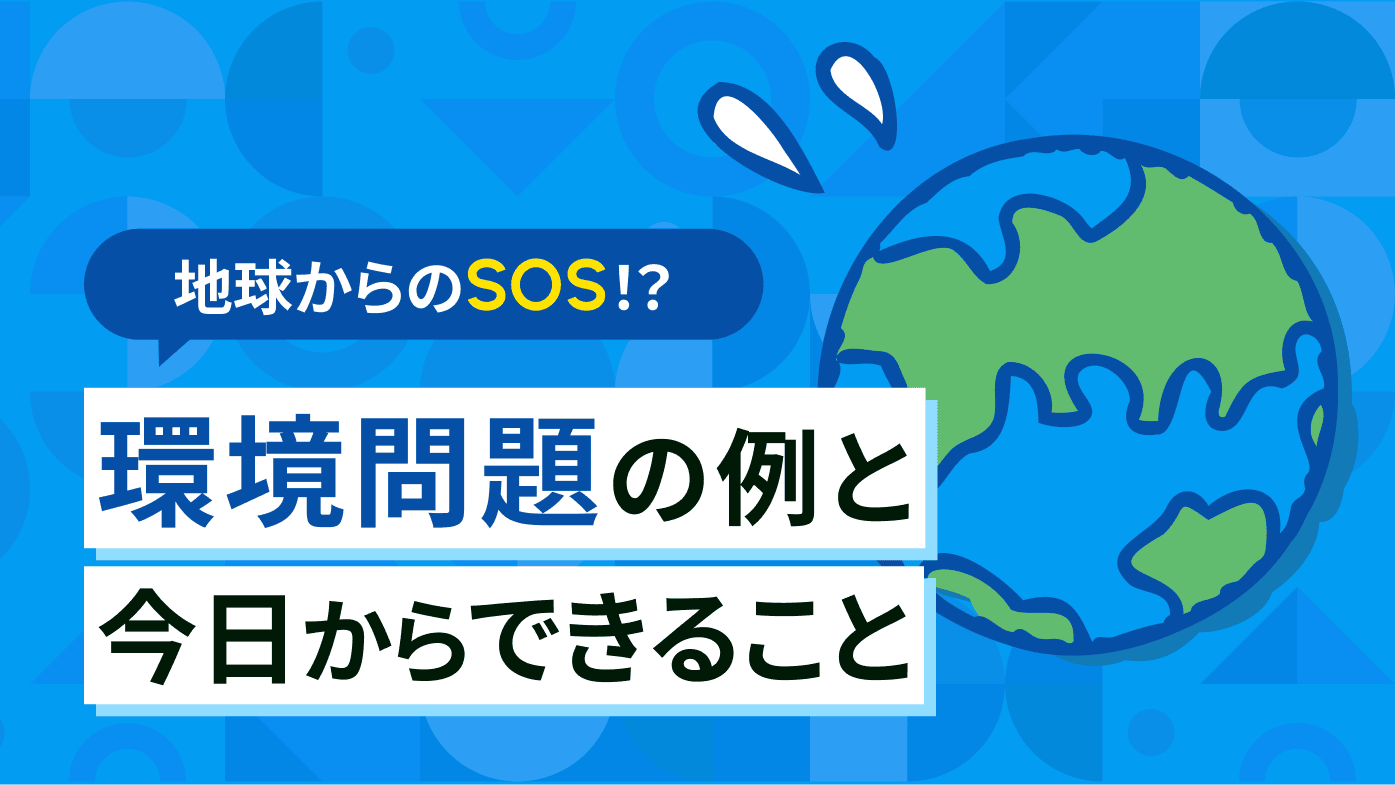
2025.07.08
地球からのSOS!?環境問題の具体例や原因と今日からできることを解説
近年、異常気象や生態系の変化など、さまざまな「環境問題」が深刻化し、まるで地球がSOSを発しているかのような状況が続いています。
本コラムでは、代表的な環境問題の具体例や現状、その背景にある原因をわかりやすく解説し、私たちが今日から始められる対策についても紹介します。
身近なデータや事例を交えながら、地球の未来のために、一人ひとりができる「小さな一歩」を一緒に考えてみましょう。
目次
地球で起きている環境問題とは?

今、地球ではさまざまな環境問題が深刻化していることをご存じでしょうか。代表的なものとして、次のような問題が挙げられます。
- 気候変動(地球温暖化など)
- ゴミ問題
- 土壌や水質の汚染
- 森林破壊
- 大気汚染
- 生物多様性の喪失 など
これらの多くは、人間の活動が原因の一つとされています。私たちが便利さや快適さを追い求めた結果、地球環境に大きな負担をかけてしまったのです。
だからこそ、環境問題は今や国や企業だけでなく、私たち一人ひとりが向き合うべき課題といえるでしょう。
まずは、本コラムを通じて「今の地球の現状」を知ることから始めてみましょう。
日本と世界で深刻化する環境問題の具体例と現状

環境問題には、地球全体に関わるものから、私たちの身近な地域で起きているものまで、さまざまな種類があります。
ここでは、地球全体と日本で特に深刻とされている環境問題を取り上げ、その内容や影響について解説します。
①気候変動
気候変動とは、気温の上昇や雨の降り方が変わるなど、地球全体の気候が長い時間をかけて少しずつ変化していくことを指します。
日本では、2024年時点で過去100年間に平均気温が約1.4℃上昇しており、その影響で猛暑日や豪雨が増えたりする現象が起きています。
こうした変化は、農作物の品質低下、病害虫の発生地域の拡大により伝染病が広がりやすくなるなど、私たちの暮らしや健康に大きな影響を与えます。
世界的にも同様に気温の上昇やその影響が見受けられており、気候変動はまさに「今、世界中で起きている問題」なのです。
②ゴミ問題
ゴミ問題は、私たちの日常生活と密接につながっており、その影響は年々深刻化しています。
日本では、2022年時点で年間およそ4,000万トンの一般廃棄物が発生しており、大半が焼却や埋立処理に回されています。
そのため、焼却によって二酸化炭素が大量発生し、気候変動を加速させる懸念があるほか、埋立地の確保も課題となっています。
特にプラスチックのゴミは大きな問題です。
世界では、年間800万トン以上の使い捨て容器などがそのまま海に流れ出ていると推定されています。海の中で砕けたプラスチックはとても小さな「マイクロプラスチック」になり、魚が食べてしまったり、サンゴの成長を妨げたりして、海の生き物や環境に悪い影響を与えています。
③土壌や水質の汚染
土壌や水質の汚染は、自然環境や私たちの暮らしや健康に大きな影響を与えます。
土壌汚染とは、本来は植物の生育などさまざまな働きを持つ土壌が、有害な物質によって汚染された状態のことを指し、水質汚染とは、川や海などが元々もっている水の汚れを浄化するはたらきを超えて汚染されてしまっている状態を指します。
例えば、汚染された土壌で育った野菜や果物、汚染された川や海に生息している魚などに有害物質がたまる恐れがあり、それを食べた人の健康に悪影響をおよぼす可能性があります。
日本の現状としては、2022年度に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は1,576件で、そのうち約37%(590件)の土壌の汚染状態が、指定の基準を超過したと報告されています。
また、同じく2022年度に水質汚濁防止法に基づく河川、湖沼、海域における調査では、河川の環境基準達成率は約92%(調査母数:2,570件)、湖沼の環境基準達成率は約50%(調査母数:191件)、海域の環境基準達成率は約80%(調査母数:2,570件)という数値が報告されています。
このように定期的に調査を行い、土壌や水質の汚染を対策・防止する法律に基づき土地の所有者へ汚染の除去を命じるなどの対処をしています。
④森林破壊
森林破壊は、気候のバランスを崩し、生き物のすみかを奪ってしまう深刻な環境問題の一つです。
森林は、地球の陸地の約3分の1を占めていますが、2010年から2020年の10年間で、世界では毎年およそ470万へクタールの森林が失われています。これは、九州全体の面積(約368万ヘクタール)を上回る規模の森林が、わずか1年で失われていることになります。
森林が失われると、気候変動が進んだり、野生動物が絶滅したりといった影響が出ます。さらに、建築や燃料に使用する木材をはじめとした地域の暮らしに必要な資源が失われ、人間の生活にもさまざまな悪影響をおよぼします。
⑤大気汚染
大気汚染の主な原因は、自動車や工場などから排出されるPM2.5や窒素酸化物、硫黄酸化物といった有害物質です。特に子どもや高齢者の健康への影響が大きく、世界保健機関(WHO)は、大気汚染が原因で早期に命を落とす人が世界で年間約700万人にものぼると報告しています。
日本では、高度経済成長期に「四日市ぜんそく」などの公害が発生しました。
⑥生物多様性の喪失
生物多様性とは、地球上に暮らす多種多様な生きものたちが相互にバランスをとり、関わりながら生きていることを指します。
しかし、森林の減少や外来種の侵入などの影響により、生物多様性が危機に瀕しているのが現状です。
日本国内でも、環境省のレッドリスト(絶滅のおそれがある野生生物のリスト)には約3,700種が絶滅危惧種として登録されています。
なぜ環境問題が起きるのか?その原因と背景

私たちの暮らしや社会のあり方が、さまざまな環境問題の原因になっています。
ここでは、地球環境に負担をかけている主な原因について、いくつかの視点から詳しく解説します。
①人が増えて、自然がどんどん少なくなっている
環境問題の大きな原因の一つは、急激に進む人口の増加です。2024年には世界の人口が82億人を超え、発展途上国を中心に今も増え続けています。
発展途上国内では人口の急増に技術の発展が追いつかず、森林や土壌などの自然の力に依存した農業が営まれている地域も少なくありません。
過剰な耕作によって土壌の栄養が失われたり、森林伐採が進んだりすることで、自然環境の悪化が深刻化しています。
②化石燃料に頼りすぎている
日本では、2019年度のエネルギー供給のおよそ85%が化石燃料に依存しており、電力の約7割が石油・石炭・天然ガスといった「化石燃料」を使用している火力発電によってまかなわれています。世界全体でもエネルギー供給のうち75%が化石燃料に頼っているのが現状です。
化石燃料を燃やすと大量の二酸化炭素が発生し、気候変動のひとつである地球温暖化の主な原因となります。
さらに、化石燃料の燃焼によって発生する硫黄酸化物や窒素酸化物は、酸性雨の原因にもなり、その酸性雨が土壌を酸性化させ森林に影響を与えたり、歴史的建造物など文化財などにも悪影響を与えます。
③私たちの暮らしが地球に負担をかけている
今の私たちの暮らしは便利で快適ですが、その便利さの裏側で地球環境に負担がかかっていることがあります。
例えば、誰もいない部屋でエアコンを長時間使い無駄な電気を使用する、使い捨ての容器を頻繁に利用し廃棄する、買い替えに伴いまだ着られる衣類を頻繁に捨てるなどの行動は、二酸化炭素の排出やゴミの増加につながります。
さらに、日本の食品ロスは年間で約500万トンにもなり、食品ロスを含めた多くのゴミを燃やすことで二酸化炭素排出量の増加につながっています。
④一人ひとりの意識がまだまだ足りていない
環境問題がなかなか改善しない背景には、「自分ひとりが行動しても意味がない」といった無関心や、どこか他人任せにする意識があることが挙げられます。
例えば、レジ袋が有料化される前は、無料でもらうのが当たり前で、使い捨てプラスチックが環境に与える影響について意識する機会は少なかったかもしれません。
しかし、レジ袋有料化という変化をきっかけに、エコバッグを持ち歩くようになったという方もいるでしょう。このような小さな行動が、一人ひとりの環境に対する意識へとつながっていきます。
環境問題に対して今日から私たちにもできること

環境問題を解決するには、国や企業の取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの行動も大切です。
ここでは、気候変動やゴミの問題をテーマに、日常生活のなかで実践できる「エコな行動」をご紹介します。
①気候変動を防ぐためにできること
気候変動の対策は、身近なことから始められます。
例えば、エアコンの設定温度を見直すこともその一つです。
環境省によると、エアコンの温度を1℃上げ下げするだけで、冷房時は約13%、暖房時は約10%も電気の使用量が減るとされています。
また、古い家電を省エネタイプに買い替えることも有効です。例えば、10年前の冷蔵庫と今の省エネ冷蔵庫では、1年間で16〜29kgもの二酸化炭素の排出を減らせるという事例もあります。
さらに、できるだけ自動車を使わないことも、二酸化炭素の発生を抑制することにつながります。近場なら徒歩や自転車、遠方ならバスや電車などの公共交通機関を積極的に利用しましょう。
②ゴミ問題の対策としてできること
ゴミの量を減らすには、「5R」という5つの行動が大切です。
- リフューズ(Refuse):必要ないものはもらわない
- リデュース(Reduce):ゴミそのものを出さないようにする
- リユース(Reuse):繰り返し使う
- リペア(Repair):壊れたものはすぐ捨てず、修理して使う
- リサイクル(Recycle):きちんと分別して、ごみを資源として再利用する
例えば、レジ袋をもらわずマイバックを持ち歩くことは「リデュース」と「リユース」にあたりますし、状態の良い洋服をフリマアプリで再利用するのは「リユース」です。
ゴミの分別も「リサイクル」に該当します。紙、プラスチック、缶、びんなどをきちんと分別して捨てることで、再利用しやすくなり、限りある資源を守れます。
こうした日々のちょっとした意識と行動の積み重ねが、環境を守る大きな力になります。まずは「できることから」始めてみましょう。
③土壌や水質の汚染を防ぐためにできること
土や川、海の水を汚さないためには、家庭での排水の仕方や使う製品に気を配ることが大切です。
例えば、料理で使った油をそのまま排水口に流すと、水を汚す原因になります。油は固めたり、紙に吸わせたりして、「燃えるゴミ」や「生ゴミ」として捨てる、または自治体の回収サービスを利用するようにしましょう。
ただし、処理の前に必ずお住まいの地域の自治体のルールを確認するようにしてください。
地域のゴミ拾いや川の清掃などの活動に参加することも、自然を守る大切な取り組みの一つです。
このように、私たち一人ひとりの小さな行動が、未来のきれいな土や水を守る大きな力になります。
④森林破壊を防ぐためにできること
森林を守るためには、日々のちょっとした選択が大切です。
例えば、紙の無駄を減らすために裏紙を使ったり、必要以上に印刷しないように工夫したりすると、紙の使用量が減り、森林資源の節約につながります。
また、紙や木材製品を選ぶときは、「FSC認証※1」や「PEFC認証※2」といった、環境に配慮して管理された森林から作られた製品を選ぶことも、森林を守る支援になります。
「森林を減らさない」「森林を育てる」行動が、地球環境を守る第一歩になります。
※1 環境や地域社会に配慮してきちんと管理された森林から作られた木材や紙に付けられるマーク
※2 世界中で使われている森林認証制度を国際的に共通のルールで評価し、信頼できると認められた木材や紙に付けられるマーク
⑤大気汚染を防ぐためにできること
大気汚染を防ぐためには、自動車の使い方を少し見直すだけでも効果があります。
例えば、自動車のエンジンをかけたままの「アイドリング」は、無駄な燃料を消費するだけでなく、排気ガスとしてPM2.5や窒素酸化物も空気中に放出するため、短時間の停車でもエンジンを止める「アイドリングストップ」を心がけましょう。
自動車に頼らず、できるだけバスや電車などの公共交通機関や自転車、徒歩で移動することも効果的です。
⑥生物多様性の喪失を防ぐためにできること
生物の多様性を守るためには、自然へのやさしい関わり方が大切です。
ポイ捨てをしない、野生動物にむやみに近づかないといった行動は、生き物の暮らしを守ることにつながります。
また、買い物をするときも「FSC認証」「MSC認証※」など、多くの生き物が住む森林や海の環境に配慮されたモノを選ぶことが、生物多様性を守る行動になります。
さらに、地域の自然観察会や保全活動に参加することで、自然の大切さを実感しながら環境を守れます。
※ 海の環境や資源を守りながら獲られた水産物に付けられる「海のエコラベル」で、第三者の審査を受けた持続可能な漁業の証
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがメンバーで協力し合い、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「子どもを自然と触れ合わせたい」や「環境問題について身近に感じてほしい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、環境問題について解説しました。
環境問題は、決して他人ごとではなく、私たち一人ひとりの暮らしと密接につながっています。深刻な現状を知ることはもちろん、そこから「自分に何ができるか」を考えることが大切です。
買い物や移動、日々の選択が地球を守る一歩になります。小さな行動が大きな変化を生むことを信じて、今日からできることに取り組んでみませんか?
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。