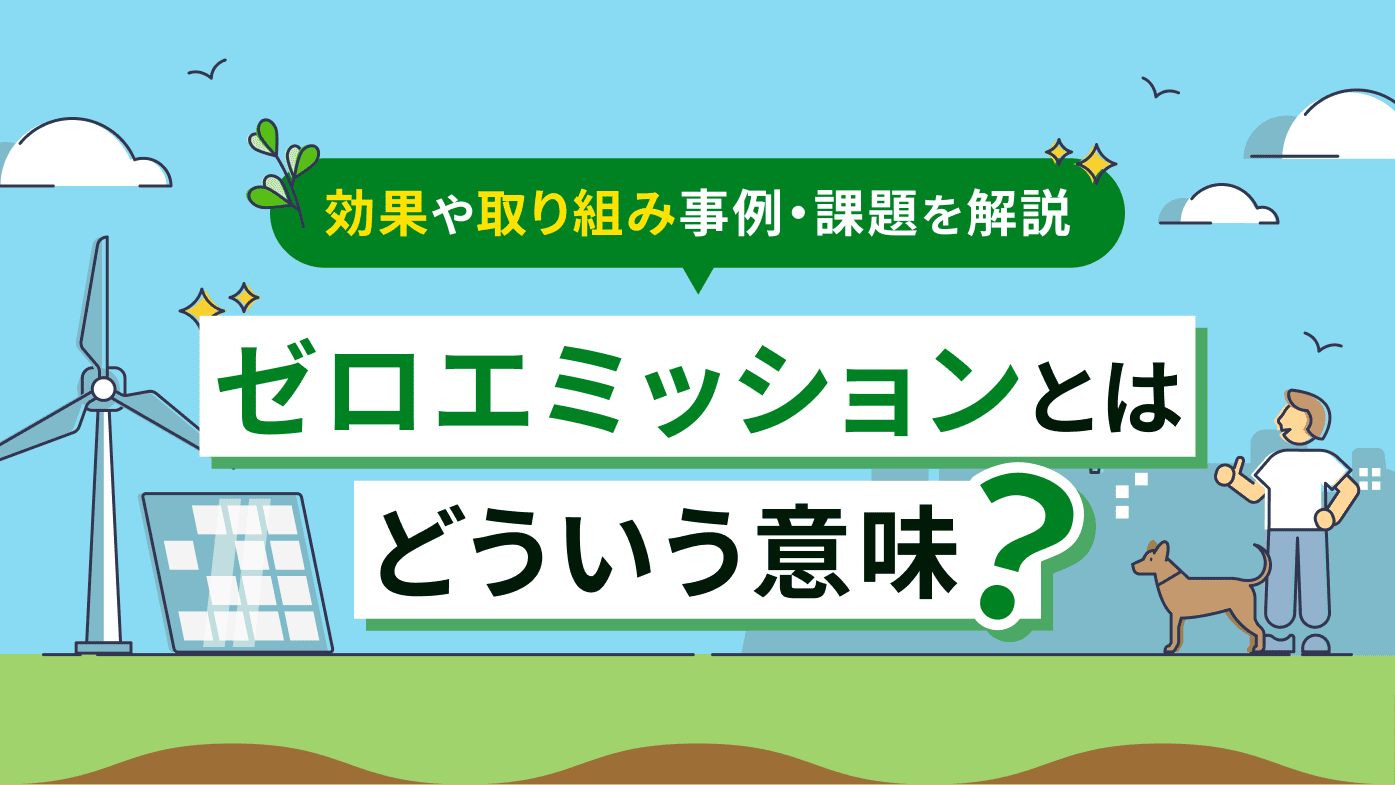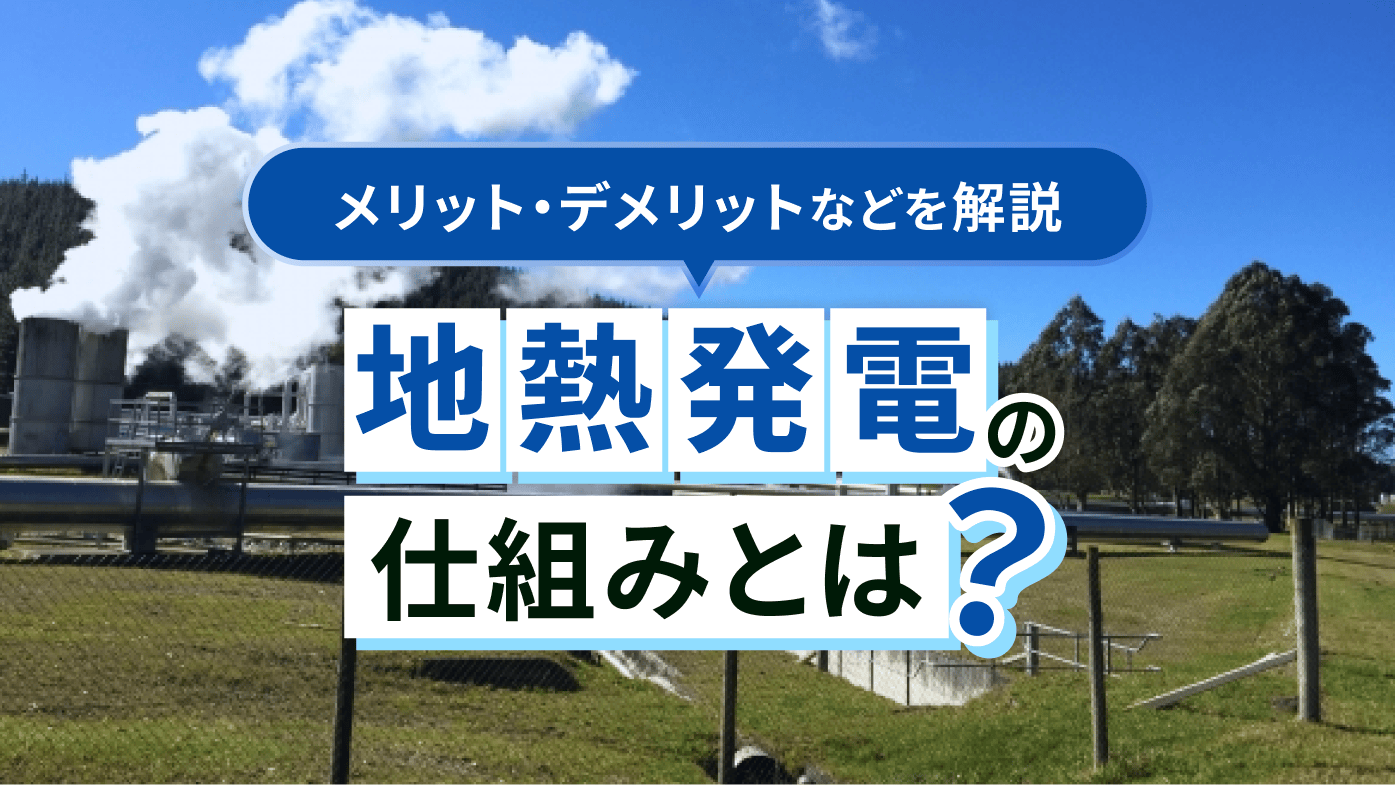
2025.08.12
地熱発電の仕組みとは?メリット・デメリットや日本の取り組みも解説
地熱発電とは、地球内部にある熱エネルギーを利用して電気をつくる発電方式です。
火山が多い日本は、世界でも有数の地熱資源国とされていますが、そのポテンシャルを十分には活用できているとは言えません。
本コラムでは、地熱発電の基本的な仕組みや種類、メリット・デメリットに加えて、日本における現状や課題についてもわかりやすく解説します。
再生可能エネルギーに関心がある方や、環境にやさしい発電方法を知りたい方はぜひご覧ください。
目次
地熱発電とは何?はじめに知っておきたい基礎知識

地熱発電とは何かを正しく理解するためには、まず「地熱とは何か」を知ることが大切です。
ここでは、地熱の意味や特徴、地熱発電がどのように再生可能エネルギーの一つとして位置づけられているのかをわかりやすく解説します。
そもそも地熱とは
地熱とは、地球の内部に存在する「熱エネルギー」のことを指します。
地球の中心部は非常に高温で、その熱が地殻を通じて少しずつ熱が地表へと伝わっています。この地熱は、火山活動や温泉などの形で、私たちの生活にも身近な存在となっています。
地熱エネルギーは、石油や石炭のように燃やして使うのではなく、地球にもともと蓄えられている熱を直接利用するため、二酸化炭素の排出が少なく安定した供給が可能という特徴があります。
そして、この自然の熱を利用して電気をつくる仕組みが「地熱発電」です。
地熱発電は再生可能エネルギーのひとつ
地熱発電は、太陽光・風力・水力と並ぶ「再生可能エネルギー(Renewable Energy)」の一つです。
再生可能エネルギーとは、枯渇の心配が少なく、環境への負荷が比較的少ない持続可能なエネルギーを指します。そのなかでも地熱発電は、天候に左右されず、昼夜を問わず安定的に発電できるという大きな特長があります。
さらに、地熱資源は地域に根ざした分散型エネルギーとして活用でき、災害時にも強いとされています。日本は火山が多く、世界有数の地熱資源に恵まれた国ですが、その活用はまだ十分とは言えません。
だからこそ、安定供給や脱炭素社会への貢献という視点から、地熱発電の価値があらためて注目されているのです。
このほかの再生可能エネルギーについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【我が家が発電所に!?】あまり知られていない太陽光発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説
【水力発電の可能性と課題】水力発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説
風力発電のメリットとデメリットを説明!仕組みや注目されている背景も解説
地熱発電のタイプは主に3種類

地熱発電には、地下から取り出す蒸気や熱水の状態、利用方法の違いによって、いくつかのタイプがあります。
ここでは、世界的にも代表的な「ドライスチーム方式」「フラッシュ方式」「バイナリー方式」の3種類について、それぞれ解説します。
ドライスチーム方式
ドライスチーム方式は、地中から取り出した高温の乾いた蒸気をそのまま使ってタービンを回し、発電を行う方法です。構造がシンプルで効率が高く、優れた発電方式の一つとされています。
日本では、地熱発電を国内で最初に取り入れた松川地熱発電所(岩手県)で、ドライスチーム方式が採用されています。
ただし、松川地域のように蒸気だけが噴き出す「蒸気卓越型」の地熱地域は非常に珍しく、こうした特徴はその地域特有の地下構造によるものと考えられています。
そのため、ドライスチーム方式は地質条件が整った限られた地域でのみ導入される発電方式です。
フラッシュ方式
フラッシュ方式は、日本の地熱発電でもっとも一般的に採用されている発電方法です。
地中からくみ上げた高温の熱水(液体)を減圧することで蒸気を発生させ、その蒸気でタービンを回し、発電します。
発電に使ったあとの熱水は、再び地中へ戻されるため、地熱資源をくり返し利用できるのが大きな特長です。
また、温泉地のような高温地域で導入しやすく、既存の温泉との共存を目指した取り組みも各地で進められています。
バイナリー方式
バイナリー方式は、比較的低温の地熱資源でも発電できる技術です。
この方式では、地中から取り出した温水そのものではなく、その熱を使って低い温度で蒸発する液体(作動流体)を蒸気に変え、その蒸気でタービンを回して発電します。
100℃前後の温水でも発電が可能なため、既存の温泉施設への導入も進んでおり、温泉水を直接使わないため、自然環境への影響が少ないのも特長です。
また、設備が小規模で済むため、分散型エネルギーとしても適しており、地方自治体や企業による導入事例も増えています。
地熱発電の仕組みや流れをわかりやすく解説

地熱発電は、「地下の熱を取り出して電気をつくる」仕組みです。
一見シンプルに思えますが、実際には自然の力と技術を組み合わせる必要があり、複雑で高度な仕組みになっています。
ここでは、地熱発電所で電気がつくられるまでの流れを、3つのステップに分けて解説します。
①地中の熱エネルギーを取り出す
地熱発電は、まず地下にある高温の蒸気や熱水をくみ上げるところから始まります。
数百メートルから数千メートルの深さまでボーリング(掘削)を行い、「地熱貯留層」と呼ばれる熱が蓄えられた岩盤層に到達させます。
この層には、地下のマグマの熱で温められた水や蒸気が閉じ込められており、それを「生産井(プロダクション井)」という井戸を通じて地表に取り出します。
くみ上げた蒸気や熱水の温度や状態(蒸気か熱水か)によって、適した発電方式が決まります。
例えば、高温の蒸気(約200〜350℃)が得られる場合はフラッシュ方式、比較的低温の熱水(約80〜150℃)ならバイナリー方式が採用されます。
②蒸気でタービンを回して発電する
取り出された蒸気(または、地熱で間接的に温められた作動流体)は、タービンという羽根車に送り込まれ、高速回転させることで熱エネルギーを回転エネルギーに変換します。
その回転エネルギーが発電機に伝わり、電気が生み出されるという仕組みです。
この工程は火力発電とよく似ていますが、地熱発電では燃料を燃やさず、地球内部の熱を利用するため、二酸化炭素の排出が非常に少ないという大きな特長があります。
なお、バイナリー方式では地熱水の熱だけを使って、少ない熱でも蒸発する液体を温めて蒸気を発生させるなど、発電の仕組みには方式ごとの違いがあります。
③発電に使われた蒸気や熱水は、再び地中へ
地熱発電では、発電に使い終わった蒸気や熱水を、地下深くにある井戸「還元井(リインジェクション井)」から地中に戻すことで、熱の循環を保つ仕組みになっています。
このように一度使った熱を自然に返すことで、地熱がたまっている地下の空間「地熱貯留層」の圧力を保ち、資源の枯渇や地盤沈下といった環境への悪影響を防げます。
特に、温泉との共存が求められる日本では、地熱発電と温泉のバランスを保つうえでも、この「熱を戻す仕組み」は、非常に重要です。
地熱発電のメリット・デメリット

地熱発電の最大のメリットは、発電する際にほとんど二酸化炭素を排出せず環境への負荷が少ない点にあります。
さらに、太陽光や風力と異なり天候や時間帯に左右されにくく、24時間安定して発電できるという強みもあります。
日本のように火山が多い国では、地熱資源が豊富に存在しており、エネルギー自給率の向上や、災害に強い分散型エネルギー※としての活用も期待されています。
一方で、いくつかデメリットもあります。
まず、地下資源の調査や発電所の建設に、多くのコストと時間がかかることです。
温泉の場所と重なることも多いため、地元住民の理解や協力を得るための調整や、自然環境への影響も調査する必要があります。
※ 電気を一か所で大量につくるのではなく、地域ごとに小さく分けて電気をつくる仕組みのこと。
日本における地熱発電の現状と課題

日本は、世界でも有数の地熱資源に恵まれた国です。
しかし、実際の発電量や発電所の導入規模を見てみると、そのポテンシャルが十分に活かされているとは言えません。
ここでは、日本における地熱発電の将来性や、なぜ導入が進みにくいのか、そしてそれらの課題を解決するための取り組みについて解説します。
日本は世界第3位の地熱資源国
日本は、アメリカ、インドネシアに次いで、世界で3番目に多くの地熱資源を持つ国とされています。
特に、東北地方や九州地方には、地下に熱エネルギーが豊富にたまっている「地熱資源エリア」が広がっており、地熱発電に適した地域が多く存在しています。
また、日本全国には約2,900か所(2021年度時点)の温泉地があり、温泉として利用されている熱と、発電に使う地熱が近い場所にあることから、地熱発電との相性が高いのも日本ならではの特徴です。
日本で地熱発電を増やすための課題と取り組み
日本は世界でも有数の地熱資源を持つ国であり、地熱発電が今後のエネルギー対策において、大きな可能性を秘めた分野であることを示しています。
しかし、普及を進めるにはいくつか課題があります。
まず、地熱開発の多くが「国立公園」や「温泉地」に位置しており、土地利用に関する規制が厳しいという点が挙げられます。
さらに、温泉事業者と地熱発電事業者の間で、資源の使い方や影響について調整が必要となるケースが多く、地域の理解や協力を得るまでに時間がかかる傾向があります。
加えて、地下の地熱資源を調査したり、掘削したりするには多額の費用と長い時間がかかるため、特に民間企業にとっては参入のハードルが高いという構造的な問題も指摘されています。
こうした課題に対し、政府や自治体、企業が連携しながら、環境に配慮しつつ地域と共存する形での取り組みが進められています。
例えば、比較的低温でも発電できる「低温地熱発電」や「温泉熱発電」の開発、開発に関する規制緩和の検討、地域住民との対話を通じて理解や協力を得るための取り組みなどが挙げられます。
今後、技術の進歩と地域との信頼関係の構築が、地熱発電のさらなる普及と発展のカギとなるでしょう。
まとめ
本コラムでは、地熱発電の仕組みやメリット・デメリット、そして日本における現状と課題について解説しました。
地熱発電は、二酸化炭素の排出が少なく、天候に左右されずに安定した発電が可能な再生可能エネルギーです。
日本は世界でも有数の地熱資源に恵まれていながら、現時点ではその活用が十分とは言えません。
しかし、技術の進歩や制度の見直し、地域との連携が進むことで、地熱発電は日本のエネルギー戦略を支える大きな柱になる可能性を秘めています。
そのためにも、私たち一人ひとりが地熱発電に関心を持ち、その価値を理解することが、持続可能な未来への第一歩につながります。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。