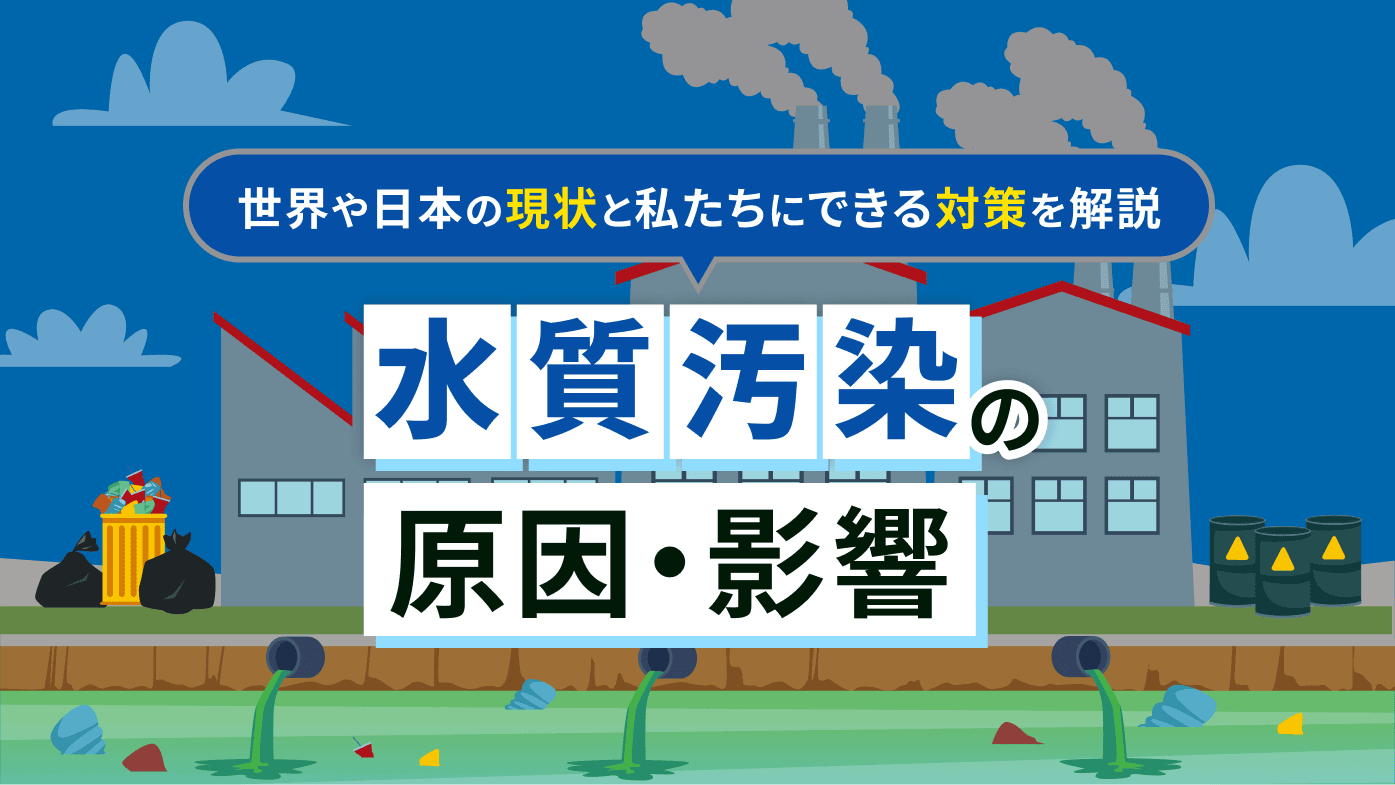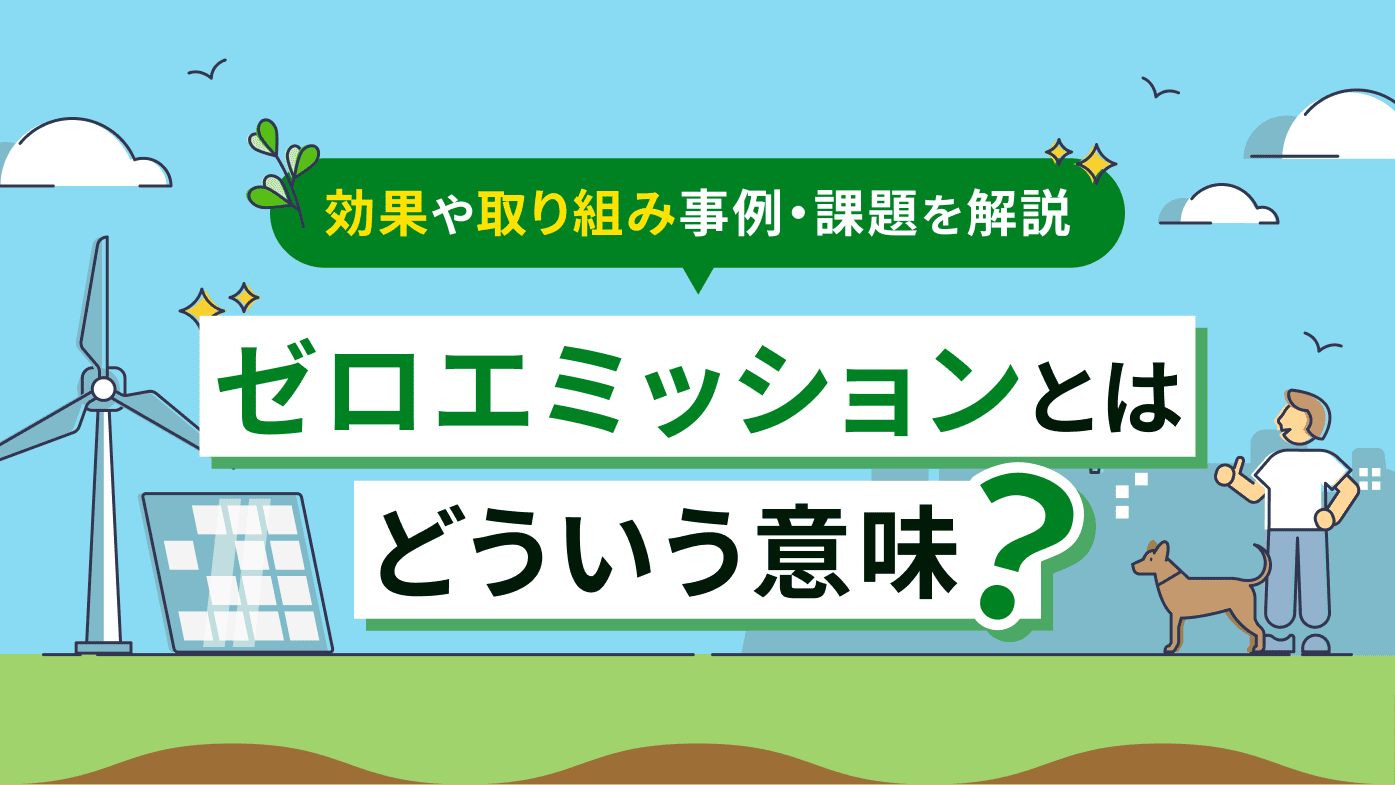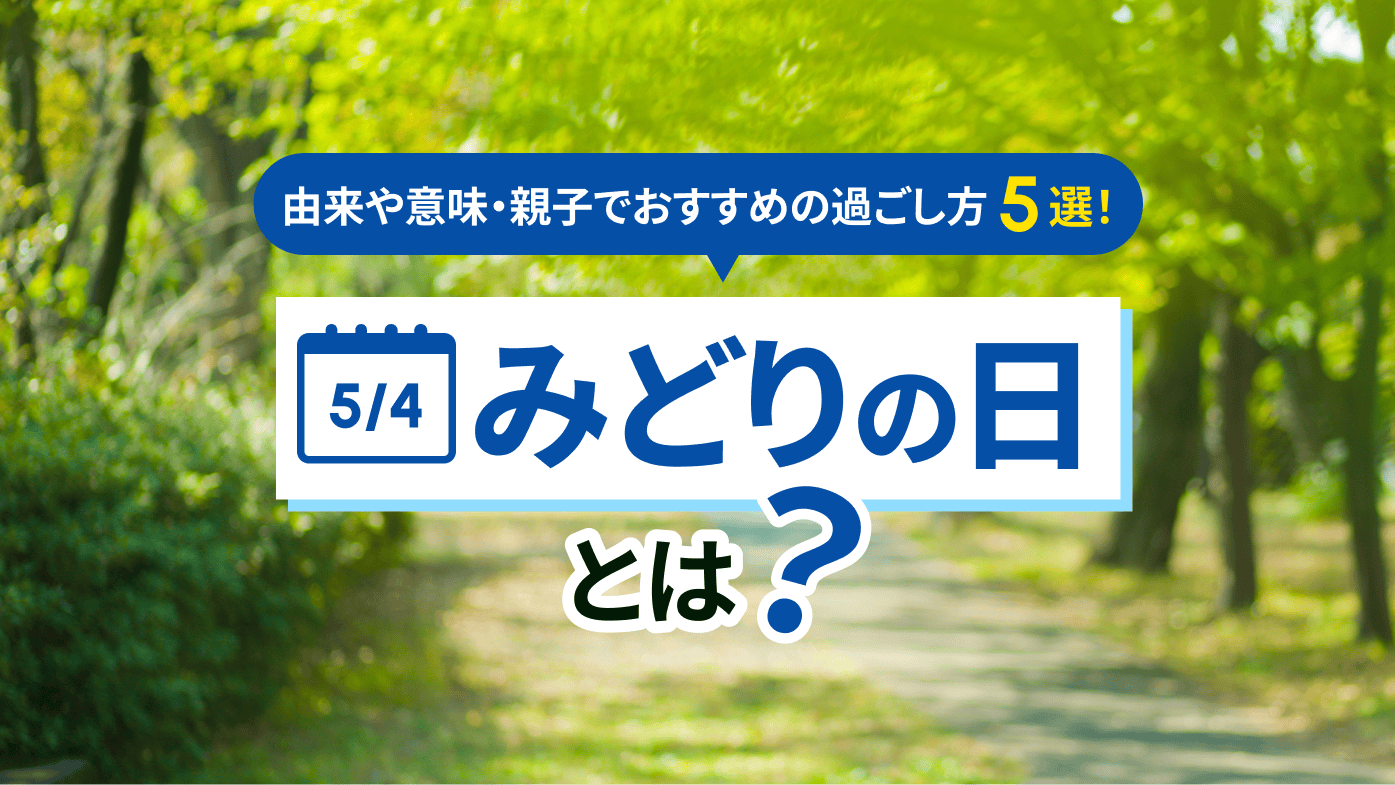
2025.04.15
みどりの日はいつ?由来や意味・親子でおすすめの過ごし方5選!
みどりの日は自然に感謝する日であり、国民の祝日です。
しかし、「みどりの日はどうしてできたの?」「みどりの日には具体的に何をすればいいの?」と疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、みどりの日の由来やおすすめの過ごし方について、わかりやすく解説します。
目次
みどりの日っていつ?由来と意味を親子で学ぼう

みどりの日は、毎年5月4日です。
みどりの日の趣旨は、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日」とされています。
また、日本の国民の祝日の一つでもあります。
みどりの日と昭和の日って何が違うの?
みどりの日と昭和の日は、どちらも日本の国民の祝日ですが、由来と意味が異なります。
みどりの日は、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日」です。
一方、昭和の日は、もともと昭和天皇の誕生日だった4月29日に由来しており、「昭和の出来事を思い出して、国の未来を考える日」です。
また、2006年までは4月29日がみどりの日でしたが、2007年からはみどりの日は5月4日に移動し、4月29日が昭和の日になりました。
このような背景があるため、みどりの日と昭和の日は、混同してしまう方も少なくないようです。
みどりの日の日付が変わったのはどうして?
みどりの日の日付が変更されたのは、2005年の「国民の祝日に関する法律」改正によるものです。
この改正により、2007年から4月29日は昭和の日に変更され、5月4日はみどりの日となりました。
5月4日は、もともと5月3日の憲法記念日(祝日)と5月5日のこどもの日(祝日)の間にあるため、祝日法によって「国民の休日」と呼ばれる休日でした。
みどりの日の意味を考慮し、5月4日は新緑の季節でゴールデンウィーク中でもあるため、適した日ということでみどりの日と定められました。
みどりの日がなくなるって本当?
みどりの日がなくなるという話が昔に流れていましたが、これは誤りです。
2007年に4月29日が昭和の日に変更されたことから、「みどりの日がなくなってしまう」と言われたこともありますが、先の話でも述べた通り、みどりの日は5月4日に移動しただけです。
現在も、みどりの日は国民の祝日に関する法律で5月4日と定められています。
「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」日、つまり自然に感謝する日として過ごしましょう。
みどりの日には何をする?親子で楽しむおすすめの過ごし方

みどりの日は、自然に感謝し、親しむための国民の祝日です。
みどりの日に親子で自然を満喫し、学びを深めるためのおすすめな過ごし方をご紹介します。
公園や森でのピクニック
公園や森でのピクニックは、みどりの日におすすめの過ごし方です。
芝生の上で食事を楽しんだり、自然観察をしたりすることで、子どもたちも自然の美しさを実感できます。
さらに、ピクニックは、家族の絆を強める時間にもなります。
自然豊かな環境で過ごすことで、心が豊かになり、家族の結束が強まることでしょう。
植物園・動物園のお出かけ
植物園や動物園へお出かけすることも、みどりの日にぴったりな過ごし方です。
普段見ることのできない植物や動物を観察することで、子どもたちは生態系や生物多様性について学べます。
子どもたちが自然の美しさを体験しながら、自然への関心を高めることができるため、植物園や動物園をお出かけ先の選択肢に入れるとよいでしょう。
家庭でのガーデニングや自然観察
家庭でのガーデニングや自然観察も、みどりの日にふさわしい過ごし方です。
庭やベランダで花や野菜を育てることは、植物の成長を間近で観察する良い機会になります。
その過程で、子どもたちは「育てる大変さ」や「命の大切さ」を学ぶことができるでしょう。
図書館で植物に関する本を読む
図書館で植物に関する本を読むのも、みどりの日の過ごし方の一つです。
図書館には、図鑑や写真集など、植物に関する本が数多くあります。
花や外国の植物の写真を見たり、植物の生態について学んだりするのも良いですし、本を片手に自然を散策するイメージを膨らませるのも楽しいでしょう。
また、本を読むことは想像力を豊かにしたり、自己肯定感を高めたり、読解力や語彙力を伸ばすことにもつながります。
地域の自然体験イベントへの参加
地域の自然体験イベントに参加するのもおすすめです。
地域によっては、みどりの日に合わせてキャンプや動植物観察会など、さまざまなイベントが開催されることがあります。
自然体験イベントに参加することで、自然とのふれあいを深められたり、普段できない体験ができたりします。
子どもたちにとっても、いつもとは違う環境で貴重な体験ができるので、楽しみながら自然に触れられる点が魅力です。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブの「イオン チアーズクラブ」では、小学校1年生から中学校3年生までの子どもたちが、年間を通してさまざまな環境に関する体験活動を実施しています。
例えば、遊休農地を活用した田植え体験学習でお米作りの大変さや楽しさを実感したり、カブトムシの幼虫観察や花畑での花摘をしたりと、インターネットや本だけでは学べない貴重な体験をしました。
そのほかにも、各地にある「チアーズ農園」では、たい肥撒きや収穫体験なども実施しています。
イオン チアーズクラブでは、体験活動を通じて、実際に自然に触れながら環境への興味や考える力を育むとともに、集団行動における社会的なルールやマナーも学ぶことができます。
「イオン チアーズクラブ」に参加して自然について学ぼう!

イオン チアーズクラブなら、お子さんが自然の中でさまざまな体験をし、環境について学ぶことができます。
ここでは、イオン チアーズクラブが実際に行った、自然に関する体験活動をいくつかご紹介します。
牛久チアーズ農園
茨城県牛久市にある「牛久チアーズ農園」は、チアーズクラブ専用の農園です。
イオン チアーズクラブのメンバーが種まきや苗植えから収穫まで、一連の農作業を体験することができます。
「牛久チアーズ農園」の活動は、農作物を作る大変さや楽しさを実感し、自然環境や食べ物の大切さについて学ぶことを目的として実施されています。
2024年4月21日の活動では、ロメインレタスの定植※やそら豆とかぶの生育観察、ホウレンソウの収穫体験などを行いました。
そのほか、5月には生育観察をしたかぶの収穫、秋にはかぼちゃの定植作業を行いました。
※ポッドなどで育てた苗を、最終的な生育の場である畑などに植え替える作業
上野動物園の見学
上野動物園の見学では、上野の森の歴史や文化に触れることができました。
上野公園は、「上野の森」として長年多くの人々に親しまれています。
日本で最初の動物園である上野動物園を訪れることで、「なぜ上野に動物園が作られたのか」「上野の森はどのように形成されていったのか」など、歴史や文化について興味を持つきっかけとなりました。
当日は天候にも恵まれ、多くの動物たちを観察でき、メンバーは目を輝かせていました。
さくらの植樹
北海道厚真町(あつまちょう)では、イオン チアーズクラブのメンバーと地域の協力団体の方々、合わせて約150名がさくらの植樹を行いました。
この植樹は、ダム工事に伴って発生した大量の土砂を、盛土として活用した場所で行われました。
参加者たちは、将来この場所がさくらの名所となり、人々の憩いの場となることを願いながら、エゾヤマザクラの苗木を合計1000本植樹しました。
この他にも、イオン チアーズクラブではさまざまな活動を行っています。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、みどりの日について解説しました。
みどりの日は、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日」で、自然に感謝する日です。
遠出をしなくても、身近な場所で自然に触れる方法は数多くあります。
今回紹介した自然の楽しみ方を、ぜひ試してみてください。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域発展の貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
公益財団法人イオン1%クラブでは、小学生を中心とし、体験学習から自然や環境に向き合うことができる「イオン チアーズクラブ」も運営しています。
イオン チアーズクラブでは、環境に関するさまざまな体験や学習を1年を通して実施し、自然や環境に興味を持ち、考える力を育てるお手伝いをしています。
また、中学生が環境問題を自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」などさまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLからご覧ください。