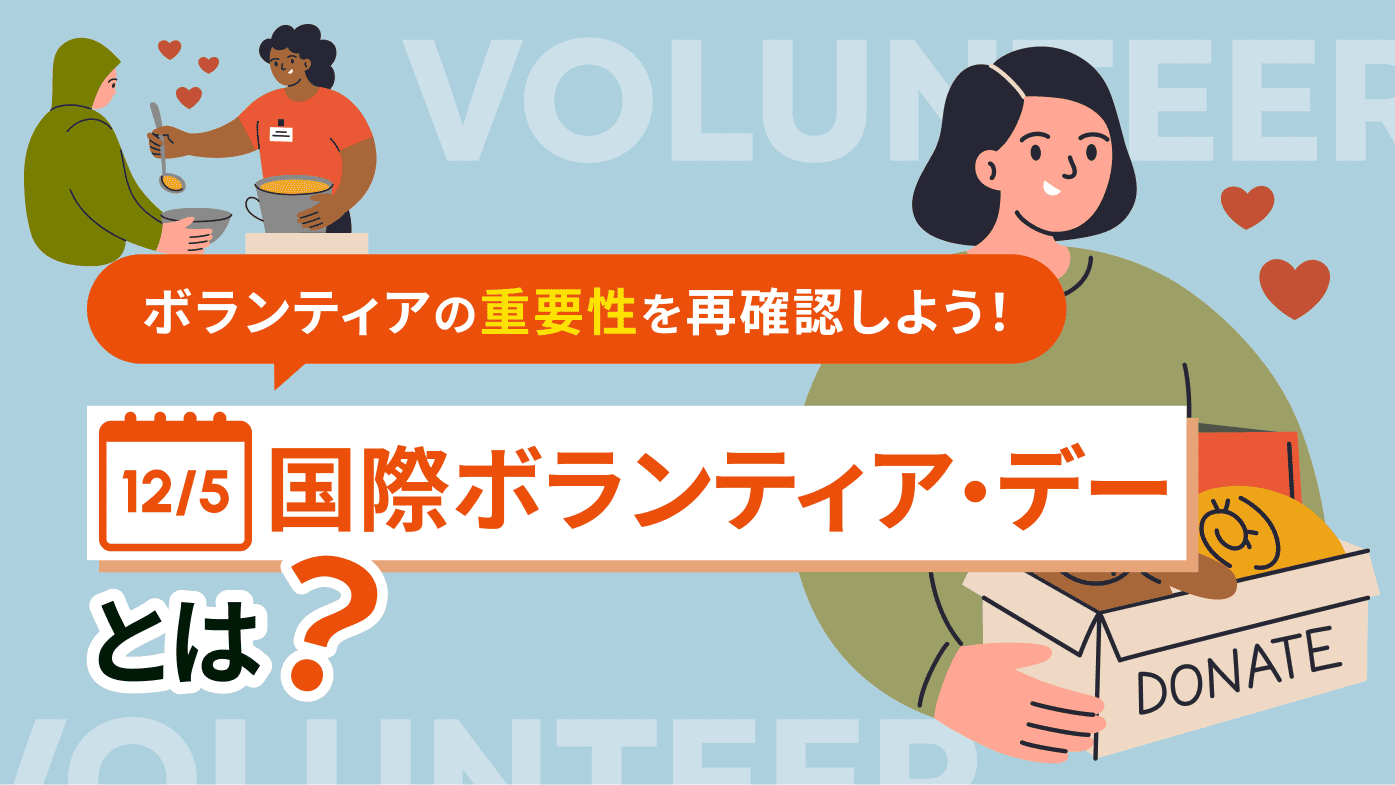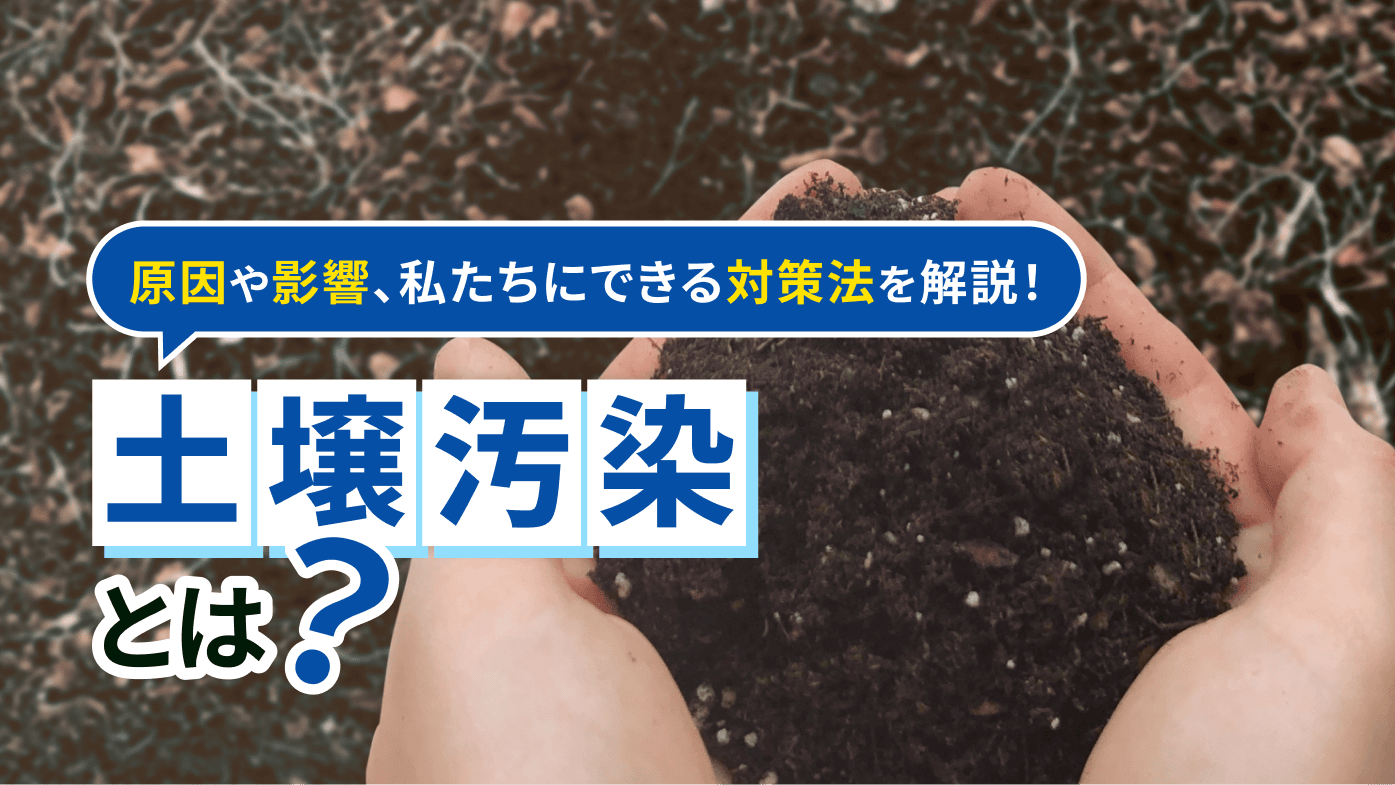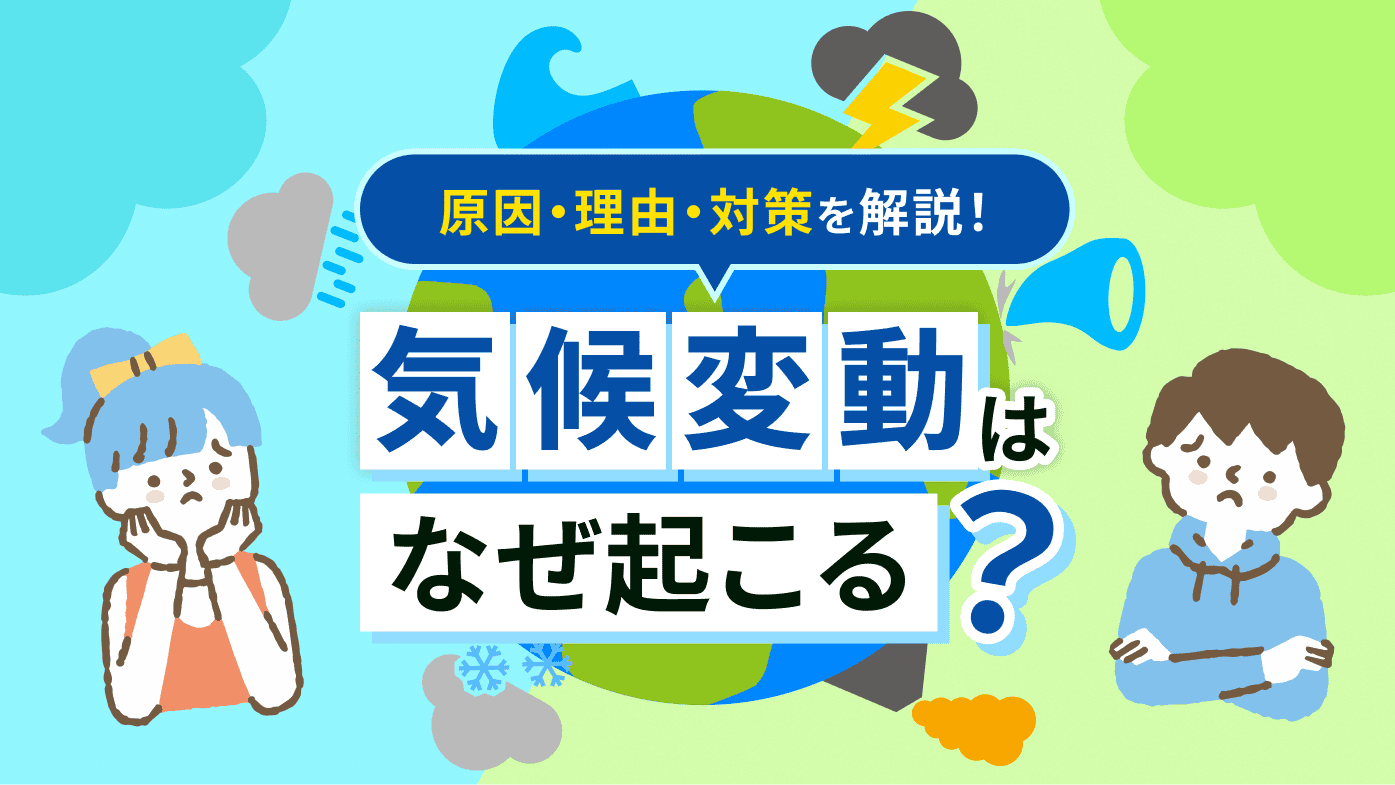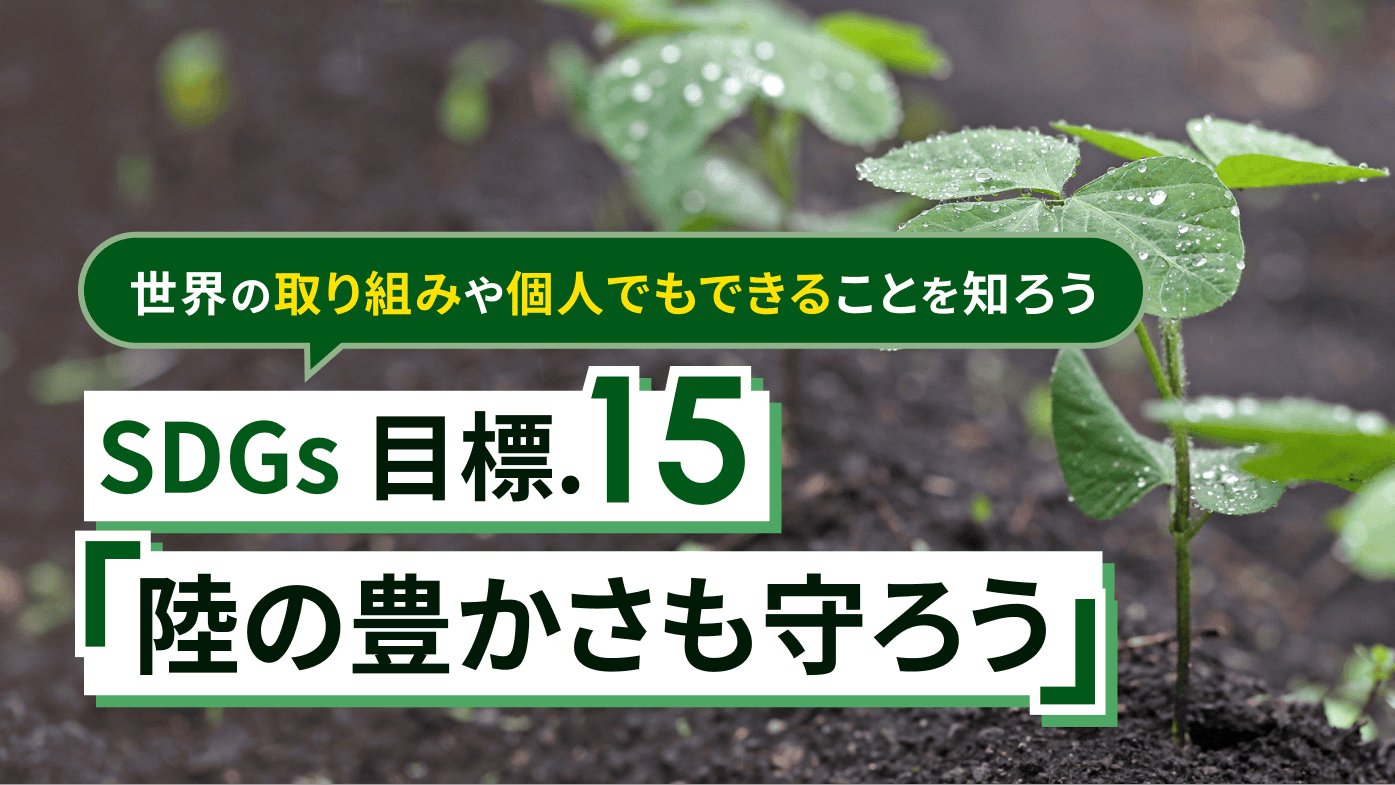
2025.10.14
SDGsの目標の一つ「陸の豊かさも守ろう」とは?世界の取り組みや個人でもできることを知ろう
「陸の豊かさも守ろう」とは、SDGsが掲げる目標の一つです。SDGsの目標はいずれも、世界中のさまざまな問題を解決するために設計されており、こちらもまた同様です。
しかし、内容が少し難しく、わかりにくいと感じられる方もいるでしょう。
そこで本コラムでは、概要だけに留まらず、具体的な取り組みまで詳細に解説します。一回読めば、「陸の豊かさも守ろう」が何なのかをしっかりと理解できるでしょう。
目次
SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」とは?

近年、さまざまなメディアでSDGsという言葉を目にするようになったと思いませんか。
しかし、言葉自体を知っている方は増えていても、具体的な中身まではあまり知られていません。
ここでは「陸の豊かさを守ろう」についてよく知るために、SDGsの基礎知識から順番に解説します。
知っておきたい基礎知識|そもそもSDGsって?
SDGsとは「持続可能な開発目標」のことで、世界中で起こっているさまざまな問題を解決するために設定された、世界共通の目標です。
SDGsでは、2030年までに達成すべき課題として、「陸の豊かさも守ろう」も含めて全17種類の目標を設定しています。
17種類の目標はそれぞれ世界が抱える問題への対策につながっていて、これらを達成することで持続可能な世界の実現を目指します。
SDGsについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【小学生向け】SDGsって何だろう?わかりやすく17の目標などを解説!
SDGsで私たちにできることは?17の目標から小・中・高・大学生向けに解説
「陸の豊かさも守ろう」は海洋以外の自然環境問題に対応するための目標
SDGsの17種類の目標のうち、目標15として掲げられているのが、陸全般の自然環境が抱える問題の解決を目指す「陸の豊かさも守ろう」です。
ここでいう陸全般の環境問題とは、例えば次のようなものがあります。
- 野生動物の絶滅危機
- 森林の減少
- 砂漠化、干ばつ
- 極端な気候(大雨ばかり降る、逆に全く降らないなど)
これらの環境問題は、主に人間の活動によって引き起こされていると言われています。
だからこそ、地球に暮らす全員が一丸となって、陸の豊かさを守ろうという意識を持ち、行動する必要があるでしょう。
「陸の豊かさも守ろう」には12のターゲットがある
目標15として掲げられる「陸の豊かさも守ろう」には、それを達成するための12個のターゲット(小さな目標)が設定されています。
12個のターゲットの内容を表にまとめました。
「陸の豊かさも守ろう」における12個のターゲット
| No | 目標 |
|---|---|
| 1 | 2020年までに国際的な協定にしたがって、森林、湿地、山地、乾燥地など陸上の生態系と、内陸の淡水地域の生態系、および、それらがもたらす自然の恵みを、守り、回復させ、持続可能な形で利用できるようにする。 |
| 2 | 2020年までに、あらゆる種類の森林の、持続可能な形の管理をすすめ、森林の減少をくいとめる。また、おとろえてしまった森林を回復させ、世界全体で植林を大きく増やす。 |
| 3 | 2030年までに、砂漠化に対応し、砂漠化、干ばつ、洪水の影響を受けておとろえてしまった土地と土壌を回復させ、これ以上土地をおとろえさせない世界になるように努力する。 |
| 4 | 2030年までに、持続可能な開発のために欠かせない山地の生態系の能力を強めるため、多様な生物が生きられる山地の生態系を確実に守る。 |
| 5 | 自然の生息地がおとろえることをおさえ、生物の多様性が損なわれないようにし、2020年までに、絶滅が心配されている生物を保護し、絶滅を防ぐため、緊急に対策をとる。 |
| 6 | 国際的に決められたとおり、遺伝資源を使って得る利益が公正で公平に分けられるようにする。また、遺伝資源を適切に使うことができるようにする。 |
| 7 | 保護しなければならない動植物の密猟や、法律に反した取り引きをなくすために、緊急の対策をとる。法律に反する野生生物の製品が求められたり、売られたりすることがないようにする。 |
| 8 | 2020年までに、移動先に定着する外来種の侵入を防ぐとともに、外来種が陸や海の生態系に与える影響を大きく減らすための対策をはじめる。特に優先度の高い外来種は駆除する。 |
| 9 | 2020年までに、生態系や生物の多様性を守ることの大切さを、国や地方による計画や開発のプロセス、貧困をなくすための取り組みやお金の使い方に組み入れて考えられるようにする。 |
| a | 生物の多様性や生態系を守ること、それらを持続可能な形で利用していけるようにするために、あらゆるところから資金を集め、より多くのお金が使えるようにする。 |
| b | 森林の保護や再植林をふくめて、持続可能な森林の管理を進めるために、あらゆるところからお金を集め、開発途上国が持続可能な森林の管理を進めようと思えるように十分な資金が使えるようにする。 |
| c | 持続可能な形で収入を得られるように、コミュニティの能力を高めるなどの取り組みを進め、保護しなければならない動植物の密猟や法律に反した野生生物の取り引きをやめさせるために、国際的な支援を強化する。 |
1~9のターゲットは「〇年までに〇とする」といった将来的な目標を示したものです。a~cは「〇のために〇をする」といった具体的な行動を含む目標を示しています。
なぜこれらのターゲットが掲げられているのか、すなわちどのようにして陸を守ることにつながるのかについては、次の見出しで詳しく解説します。
「陸の豊かさも守ろう」がSDGsの目標となった背景・現状の課題

「陸の豊かさも守ろう」がSDGsの目標の一つとなった理由は、陸の自然環境が人間の活動によっておびやかされているためです。
ここでは、現在、問題になっている陸の自然環境における課題を細分化して解説します。
「陸の豊かさも守ろう」の12のターゲットのうち、どれがどの課題に関係しているのかもあわせてまとめているので、「なぜこのようなSDGs目標が掲げられたのか」という背景も理解できるでしょう。
なお、12のターゲットのうち、1番目にあたる次のターゲットは、「陸の豊かさも守ろう」の主題的な目標であるため、すべての課題に関係しています。
【1】2020年までに国際的な協定にしたがって、森林、湿地、山地、乾燥地など陸上の生態系と、内陸の淡水地域の生態系、および、それらがもたらす自然の恵みを、守り、回復させ、持続可能な形で利用できるようにする。
出典:ユニセフ
計画性のない都市化や資源調達により森が失われている
2010年から2020年の10年間を平均すると、世界の森林面積は1年間に470万ヘクタール以上も減少していると言われています。
特に減っているのは熱帯地域であり、原因は主に土地の転用だと言います。つまり、人口の増加にともなう農地や宅地の拡大にあたって、森林を無計画に伐採してしまっていることが問題になっているのです。
そのほかの原因としては、森林火災や違法伐採などによる減少も報告されています。
森林減少に対応している「陸の豊かさも守ろう」のターゲット
【2】2020年までに、あらゆる種類の森林の、持続可能な形の管理をすすめ、森林の減少をくいとめる。また、おとろえてしまった森林を回復させ、世界全体で植林を大きく増やす。
出典:ユニセフ
【6】国際的に決められたとおり、遺伝資源※を使って得る利益が公正で公平に分けられるようにする。また、遺伝資源を適切に使うことができるようにする。
※遺伝資源:植物、動物、微生物などで、産業や研究などに利用できるまたは利用できる可能性がある遺伝的な情報をもつもの
出典:ユニセフ
「陸の豊かさも守ろう」のターゲット2と6は、急激な森林減少を解決するための対策として掲げられています。どちらも計画的な伐採および植林を推進するものです。
干ばつや砂漠化など草木が育たない土地が増えている
世界では、砂漠化や干ばつが進行し、草木が育たないほど劣化した土地が増えていると言います。
急激に進行している砂漠化の原因には、人間の活動が大きく関わっています。
土地はもともと再生能力を持っています。しかし、能力を超えるレベルの田畑の開拓および耕作、動物の放牧が行われては、土地の再生が追いつきません。
弱った土地は、土の中に含まれた栄養や水分が出ていくのを食い止める力がありません。その結果、カラカラに乾燥した土地になってしまうのです。
また、気候変動によって雨が極端に降らなくなることでも干ばつや砂漠化は起きます。これもまた人間の活動によって排出される二酸化炭素による影響が非常に大きいと考えられています。
土地の回復・保護に対応している「陸の豊かさも守ろう」のターゲット
【3】2030年までに、砂漠化に対応し、砂漠化、干ばつ、洪水の影響を受けておとろえてしまった土地と土壌を回復させ、これ以上土地をおとろえさせない世界になるように努力する。
出典:ユニセフ
「陸の豊かさも守ろう」のターゲット3は、砂漠化を解決するための対策として掲げられています。
弱った土地や土壌を再生させること、また、さらに弱らせないための努力が必要であることに触れています。
多くの動物や植物たちが絶滅危機にある
国際自然保護連合(IUCN)は、絶滅危惧種をレッドリストとしてまとめており、こちらによると、哺乳類は全体の26%、鳥類は全体の12%、針葉樹は全体の34%がリストに登録されているとのことです。
また、日本でも環境省が独自のレッドリストをまとめており、2020年の発表時点※で哺乳類は34種類、鳥類は98種類、そのほかにも多くの動植物が登録されています。
動植物が絶滅する原因としては密猟や乱獲のほか、森林減少や砂漠化などの環境問題も挙げられます。
※ 日本独自のレッドリストは5年ごとに更新、2025年版はじきに発表予定
動植物の保護に対応している「陸の豊かさも守ろう」のターゲット
【4】2030年までに、持続可能な開発のために欠かせない山地の生態系の能力を強めるため、多様な生物が生きられる山地の生態系を確実に守る。
出典:ユニセフ
【5】自然の生息地がおとろえることをおさえ、生物の多様性が損なわれないようにし、2020年までに、絶滅が心配されている生物を保護し、絶滅を防ぐため、緊急に対策をとる。
出典:ユニセフ
【7】保護しなければならない動植物の密猟や、法律に反した取り引きをなくすために、緊急の対策をとる。法律に反する野生生物の製品が求められたり、売られたりすることがないようにする。
出典:ユニセフ
「陸の豊かさも守ろう」のターゲット4・5・7は、動植物を絶滅危機から救うための対策として掲げられています。
動物そのものだけでなく、そのすみかや食べ物を供給する山地の保護に関しても盛り込まれているのが特徴です。
侵略的外来種により生態系が崩されている
外から持ち込まれた外来種のなかでも、地域の自然環境や生態系に悪影響を与えるものが、侵略的外来種です。これによって、もともとあった生態系のバランスが乱れ、大きく変わってしまうことがあります。
外来種に捕食されて、その地域にいる野生生物が減少、あるいは絶滅してしまうことがあるためです。
日本では、判明しているだけでも約2,000種類の外来種が生息しているとのことで、その原因のほとんどが人間の活動にともなって運び込まれてきたものだと言います。
例えば、アライグマは、1970年代後半以降にペットブームが起こり、日本へと多く輸入されましたが、逃がしたり逃げてしまったりして侵略的外来種となりました。
侵略的外来種の課題に対応している「陸の豊かさも守ろう」のターゲット
【8】2020年までに、移動先に定着する外来種※の侵入を防ぐとともに、外来種が陸や海の生態系に与える影響を大きく減らすための対策をはじめる。特に優先度の高い外来種は駆除する。
※外来種:もともとその土地で生育していなかった動植物
出典:ユニセフ
「陸の豊かさも守ろう」のターゲット8は、外来種対策として掲げられています。
外来種の侵入を防ぐだけでなく、特に大きな問題を起こしている侵略的外来種については駆除も行う必要があることを示しています。
国ごとの自然保護の意識および資金格差
陸の豊かさを守るには、世界中がアクションを起こす必要があります。しかし、そのうえで問題になるのが、国によって自然保護に対する意識や、活用できる資金に差があることです。
例えば、日本は自然保護への意識が比較的低いと言われています。過去に実施されたさまざまな意識調査においても、環境問題に対する関心が他国に比べて極めて低い結果となってしまっています。
資金面での話でいえば、森林減少や砂漠化などは発展途上国で特に大きな問題となっていますが、経済状況により対策を実施することが難しいケースも少なくありません。
実際、世界では約16億人が薪や食料、建築資材などを森から得て生活しており、貧困層の約75%が土地劣化の影響を直接受けているというデータもあります。自然資源に頼って暮らす人々にとって、環境の悪化はそのまま生活基盤の崩壊を意味し、貧困のさらなる深刻化を招いてしまうのです。
「陸の豊かさも守ろう」は、単なる自然保護のみならず、貧困問題とも密接に結びついたテーマであるとも言えます。
意識差や資金格差に対応している「陸の豊かさも守ろう」のターゲット
【9】2020年までに、生態系や生物の多様性を守ることの大切さを、国や地方による計画や開発のプロセス、貧困をなくすための取り組みやお金の使い方に組み入れて考えられるようにする。
出典:ユニセフ
【a】生物の多様性や生態系を守ること、それらを持続可能な形で利用していけるようにするために、あらゆるところから資金を集め、より多くのお金が使えるようにする。
出典:ユニセフ
【b】森林の保護や再植林をふくめて、持続可能な森林の管理を進めるために、あらゆるところからお金を集め、開発途上国が持続可能な森林の管理を進めようと思えるように十分な資金が使えるようにする。
出典:ユニセフ
【c】持続可能な形で収入を得られるように、コミュニティの能力を高めるなどの取り組みを進め、保護しなければならない動植物の密猟や法律に反した野生生物の取り引きをやめさせるために、国際的な支援を強化する。
出典:ユニセフ
「陸の豊かさも守ろう」のターゲット9と、a、b、cは、国ごとの環境問題に対する意識差や資金格差を埋めるために掲げられています。
特にa~cに関しては、対策するうえで前提として必要な資金の確保に関係することもあり、具体的な内容となっています。
陸の豊かさを守るために行われている世界の取り組み例

「陸の豊かさも守る」という目標を達成するために、日本をはじめ、世界ではさまざまな取り組みが行われています。
ここでは、そうした取り組み事例のなかからいくつかをピックアップして解説します。
日本では行政機関や大学が積極的に取り組みを実施
日本では行政機関や大学を中心に、積極的な活動が行われています。
行われている取り組みの一例としては、例えば次のようなものがあります。
- 防衛省・自衛隊:ゴミ拾いとジョギングを組み合わせたプロギングという活動を取り入れ、地域の美化や生物多様性、森林保全などの環境保全に貢献
- 九州大学:伊都キャンパスは約99haの保全緑地※を有し、森林や湿地などの保全を目的とした研究が行われている
- 広島修道大学:人間環境学部や国際コミュニティ学部と言った部において、環境に関する分析や各国の状況に関するディスカッションなどをさまざま実施している
ゴミ拾いのような具体的なアクションもあれば、研究や分析といった意識改革および対策の模索に関わる取り組みも多いようです。
※ 樹林地を中心に豊かな自然を保全するため、法律や条例などの制度に基づき、緑地の利用規制を行っている緑地
国連が中心となり全世界で連携した取り組みも行われている
国連が中心となって全世界が連携し、「陸の豊かさも守ろう」という目標に対して行われた取り組みもあります。
例えば1996年には、「深刻な干ばつまたは砂漠化に直面している国(とくにアフリカ大陸の国々)における砂漠化防止のための国際連合条約」を発効しました。
また、2000年に設置された国連森林フォーラムでは、各国の政府間が協力して森林を守るための計画を取り決めています。
陸の豊かさを守るために私たち個人ができること・5つ

ここまでの解説で、「陸の豊かさを守るために個人でできることはないの?」と思った方もいるかと思います。
そこでここでは、私たち個人が「陸の豊かさも守る」という目標を達成するためにできることについて、5つ解説します。
自然の魅力や大切さを知る
陸の豊かさを守るためにまずおすすめなのが、自然の魅力や大切さを知ることです。
例えば休日に公園や川沿いなどを散歩してみたり、少し足を伸ばして山に行ってみたり、簡単なことから始めてみてはいかがでしょうか。
自然とふれあい、魅力や大切さを知ることで、「自分は自然の何が好きなのか」や「どこに素晴らしさを感じるのか」といった興味関心をまずは育てましょう。
自然が大切だと感じる気持ちを自覚してこそ、環境問題に対するアクションを起こそうという意気込みがわいてくることでしょう。
SDGsを踏まえて作られたモノを購入する
モノを選ぶときのポイントとして、「SDGsを踏まえて作られたものであるか」を意識してみるのもおすすめです。
例えば、次のような認証ロゴマークが付いたモノを探してみましょう。
| 認証制度 | 内容 |
|---|---|
| FSC認証 | 森林管理協議会によって制定された認証で、望ましい管理方法などを満たした木材製品を対象としている |
| グッドインサイドマーク | 持続可能な方法で栽培されたコーヒーやカカオ、お茶を対象とした認証 |
| バードフレンドリーマーク | 環境および動物の保護に配慮された日陰栽培有機コーヒーを対象とした認証 |
| フェアトレード認証 | 最低価格を保障した公平・公正な取引に関する認証で、主に途上国の生産者を対象としている |
例えば、FSC認証のモノを購入すれば森林の保護をサポートでき、フェアトレード認証のモノを購入すれば発展途上国の支援につながります。
地産地消・旬の食材を活用
地産地消や旬の食材を活用することは、実は砂漠化を引き起こす原因のひとつである気候変動の対策につながります。
例えば、地産地消の場合、遠方に食材を輸送する必要がないため、飛行機やトラックから排出される二酸化炭素の排出量を抑えられます。
また、旬の食材を食べることも大切です。
昨今はさまざまな食材が一年中手に入るようになりましたが、これはハウス栽培や外国からの輸入品です。旬の食材に比べると、適した気候にするためのエネルギーや、輸送のためのエネルギーが多くかかってしまいます。
季節ごとの旬な食材を表にまとめてみました。
| 旬の季節 | 主な食材 |
|---|---|
| 春の食材 | 菜の花、キャベツ、タケノコ、しいたけ、アサリ |
| 夏の食材 | トマト、キュウリ、オクラ、シソ、アジ、スイカ |
| 秋の食材 | ジャガイモ、ほうれん草、ごぼう、さつまいも、栗 |
| 冬の食材 | 白菜、大根、春菊、みかん、りんご、ブリ、さわら |
旬の食材は栄養価が高く、さらには味も美味しいので、積極的に食べるようにしてみましょう。
地産地消についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
野生の動物にエサを与えない
野生動物たちにエサを与えないことは、結果として動物の保護につながります。
例えば、野生動物にエサを与えてしまうと、人間がエサをくれると学習し、自力でエサをとれなくなる可能性があります。
そうなると自然の中で生活していくことが困難になり、地域の生態系が崩れてしまうことにつながりかねないのです。
かわいいから、なついてほしいからとエサをあげたくなってしまうこともあるかもしれませんが、ぐっとこらえて見守ることが大切です。
環境保護に関するボランティアに参加する
より直接的な環境保護に取り組みたいという方は、環境保護に関するボランティアに参加してみましょう。
さまざまな場所に赴き緑化活動や環境保全活動を行うフィールドボランティアや、環境保護に関する団体で事務作業を行う事務ボランティアなどがあります。
こういったボランティアは各団体のWebサイトなどで募集しているほか、Web上のボランティアの募集掲示板を利用して探せます。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがメンバーで協力し合い、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「子どもを自然と触れ合わせたい」や「楽しみながら環境や社会について学んでほしい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
「イオン チアーズクラブ」で開催された活動

イオン チアーズクラブでは、さまざまな体験活動を実施しています。
ここでは、陸の豊かさを守ることにもつながる過去の活動例をいくつかご紹介します。
上野動物園で動物や植物を観察
上野動物園の見学では、上野の森の歴史や文化に触れることができました。
上野公園は、「上野の森」として長年多くの人々に親しまれています。
日本で最初の動物園である上野動物園を訪れることで、「なぜ上野に動物園が作られたのか」「上野の森はどのように形成されていったのか」など、歴史や文化について興味を持つきっかけとなりました。
当日は天候にも恵まれ、多くの動物たちを観察でき、メンバーは目を輝かせていました。
イオン兵庫三木里脇農場でリサイクル堆肥を使った農業体験
兵庫県三木市にあるイオン兵庫三木里脇農場で、イオン チアーズクラブメンバーによる農業体験を実施しました。
環境に優しいリサイクル堆肥をまいたほか、旬を迎えたオーガニックレタスの試食や、サニーレタスの収穫も体験しました。
旬の食材のみずみずしさや甘さにメンバーたちは驚きを隠せないようでした。
この他にも、イオン チアーズクラブではさまざまな活動を行っています。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、SDGsの目標のひとつである「陸の豊かさも守ろう」について解説しました。
生態系や生物多様性を守ることを目的としたこの目標は、人々の生活にも深く関わっています。
環境保護というと国や組織などによる大規模な取り組みを想像するかもしれません。しかし、モノや食材の選び方であったり、野生の動物との接し方であったりなど、個人でできることも多くあります。
まずは身近な自然に触れてみて、大切にしようという気持ちを育てることから始めてみてはいかがでしょうか。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。