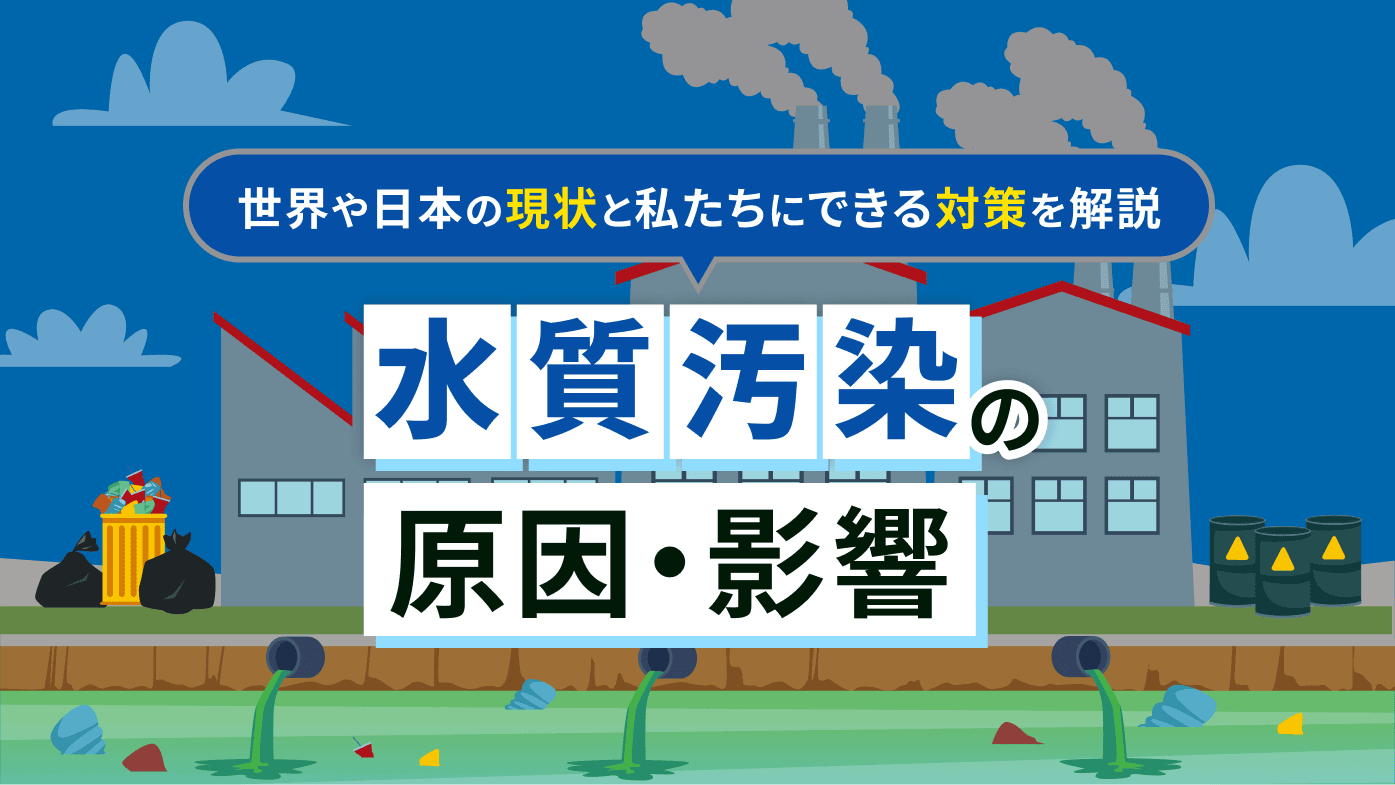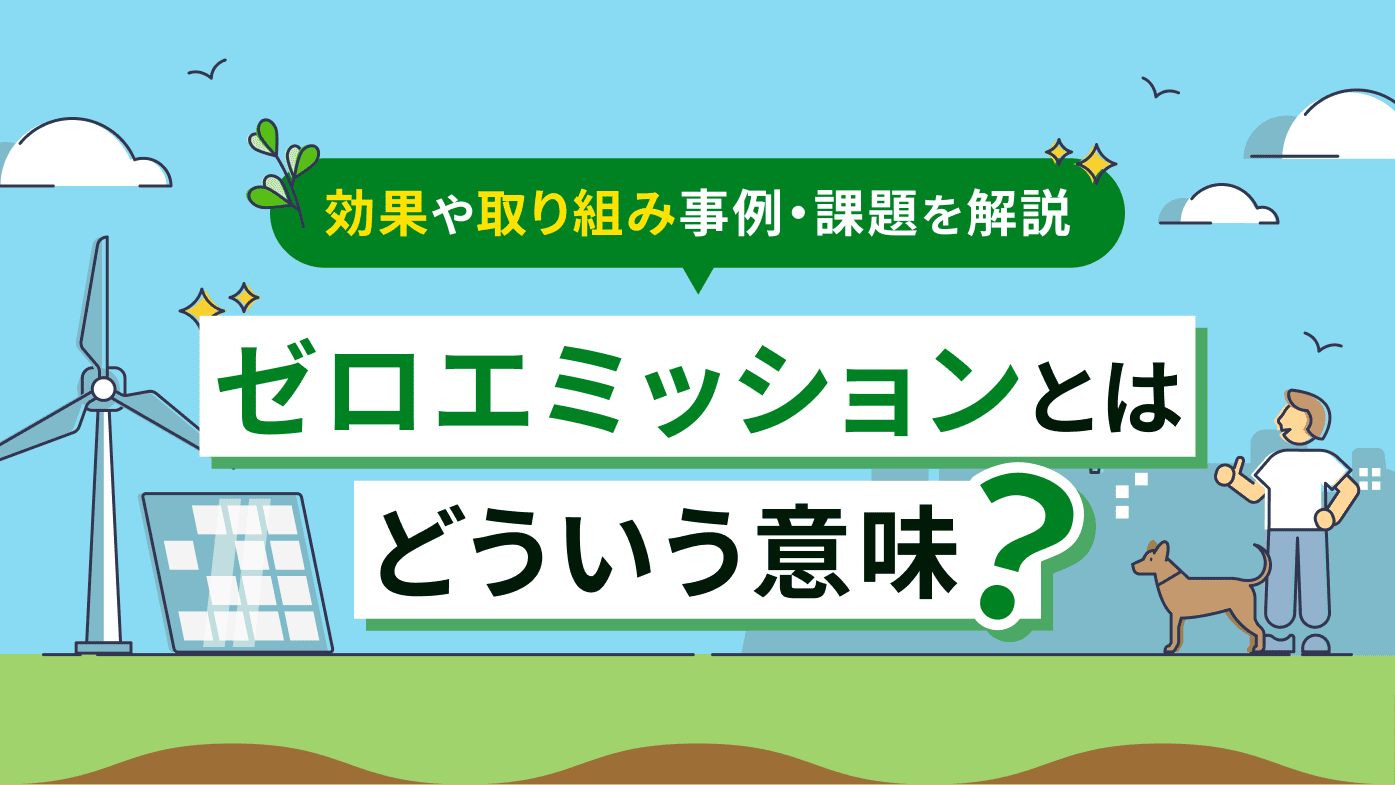2025.08.19
地産地消で地域を元気に!地産地消のメリットや取り組みを解説
「地産地消(ちさんちしょう)」という言葉を耳にしたことがあっても、「どんな意味?」「どんな良さや注意点があるの?」と詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか。
地元でつくられた食材や製品を、地元で使ったり食べたりするこの仕組みは、私たちの暮らしにとっても、環境や地域経済にとってもさまざまなメリットがあります。
本コラムでは、地産地消の基本的な意味から、メリット・デメリット、そして日々の暮らしのなかでどのように取り入れられるかまで、わかりやすく解説します。
目次
地産地消とは?意味をわかりやすく解説

「地産地消」とは、「地元でつくられたものを、地元で消費する」というシンプルな考え方です。
地産地消は環境への配慮や地域経済の活性化、そして私たちの暮らしの豊かさにもつながる、奥の深い取り組みなのです。
ここでは、まずその基本的な意味や、地産地消を支える要素について解説します。
地産地消とは「地元でつくって、地元で消費する」こと
地産地消とは、「地元でつくられたものを、地元で消費する(食べる・買う)」という考え方です。
例えば、地元の農家が育てた野菜を近くのスーパーで買って家庭で食べたり、地元の漁港で水揚げされた魚を、地元の飲食店がメニューに取り入れたりするような行動が、地産地消の具体的な例です。
「地産」は、農作物(米・野菜・果物など)、水産物(魚・貝・海藻など)、畜産物(牛乳・肉・卵など)といった生産品が中心ですが、最近では地元でつくられた加工品や木材、伝統工芸品なども含まれるようになっています。
一方、「地消」は、そうした地元の産品を地元のなかで消費・活用することを意味します。家庭の食卓はもちろん、学校の給食や飲食店、直売所、道の駅など、さまざまな場面で実践されています。
つまり、地産地消は単に「地元の野菜を食べる」だけでなく、地元の資源を地元のなかで循環させる取り組みです。その実践方法は、地元の特色や人々の暮らし方によって多様です。
地産地消における地元の定義とは?
「地元」とは、基本的に自分が暮らしている地域(市町村や都道府県、生活圏)を指します。
地産地消における「地元」の定義に明確なルールはありませんが、一般的には市町村や県単位、あるいは日常生活の行動範囲(生活圏)を「地元」と考えることが多いです。
例えば、同じ県内で育てられた野菜や水揚げされた魚は「地元産」とされ、スーパーや直売所の売り場では「〇〇市産」「〇〇県産」と表示されています。
地域によっては、隣接する市区町村とのつながりも「地元」と見なすケースがあります。
地産地消が大切な理由とは?
地産地消が注目されるようになった背景には、私たちの暮らしや社会の変化があります。
かつては当たり前だった、「地元でとれたものを地元で食べる」という生活スタイルは、大量生産・大量流通の発展により、しだいに失われてきました。
その結果、私たちは食べ物の産地や生産者が見えにくくなり、「どこで、誰がつくったのかわからないものを食べる」ことが日常になっています。
こうしたなかで、「生産者の顔が見える安心な食材を選びたい」「地元とのつながりを大切にしたい」と考える人が増えています。さらに、災害による物流の停滞や物価の高騰といった不安定な状況も、「地元で支え合える仕組み」への関心を高めるきっかけとなりました。
地産地消は、そうした現代の課題を見つめ直し、地元とともに暮らす豊かさを取り戻すヒントとして、あらためて注目されているのです。
地産地消のメリット

地産地消には、私たち消費者にうれしいメリットがたくさんあります。
新鮮な食材が手に入るだけでなく、安心して食べられることや、地元を応援できること、さらに地球環境にもやさしいという面もあります。
ここでは、地産地消の魅力を5つのポイントに分けてご紹介します。
①新鮮な食材が食べられる
地元でとれた野菜や魚は、お店に並ぶまでの時間が短いため、新鮮な状態で手に入ります。
例えば、朝に収穫された野菜が、その日のうちにスーパーや直売所に並ぶこともあります。
新鮮な野菜はシャキシャキとした食感があり、果物は甘みがしっかり感じられます。また、新鮮なうちに調理できるため、栄養価を損なうことなく食べられます。
季節ごとの「旬の味」を楽しめるのも、地産地消ならではの魅力です。春には山菜、夏にはトマトやとうもろこし、秋にはさつまいも、きのこなど、季節の味を身近に感じられます。
②食の安全性が高まりやすい
地元でつくられた食材は、「どこで、誰が、どのように」つくったのかがわかりやすく、安心感を得られやすいのが特長です。
例えば「〇〇さんのトマト」といったように、生産者の名前が表示されていたり、農薬や肥料の使い方を説明している場合もあります。このように生産者と消費者の距離が近ければ、信頼関係が築きやすくなるでしょう。
直売所や市場では、農家の方と直接話せることもあり、「この野菜は今が旬ですよ」「今年は特に甘くできました」といった話を聞けることもあります。こうした「顔の見える関係」は、「信頼して買える」という気持ちにもつながります。
③地域経済の応援につながる
地元でつくられたものを地元で消費する(食べる・買う)ことは、地域のなかでお金がめぐることを意味します。
例えば、地元の農家さんや漁師さんが育てた野菜や魚を、近くのスーパーや飲食店が仕入れ、それを私たちが買って食べる。そのような流れができると、地域の経済が元気になり、働く場所や仕事が増えることにもつながります。
さらに、地域の特産品に注目が集まると、観光や地域の魅力アップにもつながります。
つまり、地産地消は「地域を応援する行動」とも言えるのです。
④環境への負荷を減らせる
地産地消は、環境へのやさしさという面でも注目されています。
食材を遠くから運ぶには、トラックや船、飛行機などの移動手段が必要で、そのたびにたくさんの二酸化炭素が排出されてしまいます。
しかし、地元でとれたものを近くで使えば、運ぶ距離(フードマイレージ)が短くなるので、排出される二酸化炭素も少なくなります。
また、食材を遠くまで運ぶ必要がないので、日持ちせるための包装や保存料が減らせるというメリットもあります。これにより、プラスチックごみや食品ロスも減らせます。
毎日の「食材の選び方」が、地球の環境にも関わっていると考えると、地産地消は私たちができるエコな取り組みの一つと言えるでしょう。
地産地消のデメリット

地産地消にはさまざまなメリットがありますが、実際に日常生活へ取り入れる際では、いくつかの不便さや課題を感じることもあります。
ここでは、地産地消に取り組むうえで知っておきたい注意点や、消費者が感じやすいデメリットを紹介します。
①値段がやや高めに感じられることがある
地元でつくられた商品は、スーパーなどで見かける他の品と比べて、少し値段が高く感じられることがあります。
これは、大量生産や大規模な流通が難しく、手作業や小規模な生産で手間ひまかけて育てられていることが多いためです。
また、生産量が限られているため、特売や値下げが行われにくいのも理由の一つです。そのため、大量に仕入れを行う全国チェーンのスーパーなどと比べて、価格差が目立ってしまうことがあります。
ただし、その価格には「新鮮さ」や「安心感」、さらには「地元の生産者を応援する」といった、目に見えない価値も含まれています。価格だけでなく、その背景にある思いや品質にも目を向けてみることが大切です。
②品ぞろえや選択肢が限られることがある
地元産にこだわって食材を選ぶと、季節や地域の事情によって、どうしても品ぞろえが限られてしまうことがあります。
例えば、夏にはトマトやきゅうりなどの野菜が豊富に並ぶ一方で、冬には扱う種類が少なくなったり、選べる食材が偏ってしまったりすることがあります。
さらに、肉・魚・乳製品なども地元産にこだわると、販売しているお店が限られたり、欲しい商品が手に入らなかったりする場面が出てくるかもしれません。
こうした点で「選びにくい」「少し不便」と感じることもありますが、裏を返せば、季節の移ろいや土地の恵みを五感で味わいながら、食事を楽しめるということでもあります。
③流通や販売のインフラを整えるのが大変
地産地消をさらに広げていくためには、食材を届けるための流れや売り場の整備など、地元全体での体制づくりが欠かせません。
例えば、農家が自分たちで野菜などを販売しようとすると、収穫物を保管する設備や運ぶ手段が必要になりますし、販売先を見つけるための工夫や努力も必要になります。
また、地元のスーパーや飲食店が地元産の食材を扱うには、生産者と協力し合いながら、安定して仕入れられる仕組みをつくることが求められます。
こうした取り組みには、農家やお店だけでなく、地元の協力団体など、さまざまな立場の人たちが協力することが大切です。
消費者である私たちにできることは、「買えるときに、無理なく地元のものを選んでみよう」という気持ちを持って行動することです。これだけでも、地産地消の応援になります。
私たちにもできる地産地消のはじめ方

地産地消は、特別な知識や大きな行動を必要とするものではありません。買い物や食事など、日々の暮らしのなかで少し意識を変えるだけで、誰でも気軽に取り入れられます。
ここでは、すぐに実践できる3つのアクションをご紹介します。
①スーパーの地元産コーナーや道の駅などをのぞいてみる
もっとも気軽にできるのが、「地元産の商品に目を向けてみる」ことです。
多くのスーパーでは、「〇〇県産」や「地元農家の野菜」などの表示があるコーナーを設けています。価格や見た目でなく、「どこでつくられたか」を選ぶときの基準に加えてみましょう。
また、週末に道の駅や農産物直売所へ足を運んでみるのもおすすめです。
その日にとれたばかりの新鮮な食材に出会えて、買い物が「地元とつながる体験」になります。
②地元の農家や生産者とコミュニケーションを取ってみる
地産地消をさらに楽しむためには、地元の食材をつくっている人たちとの交流を増やしてみるのもおすすめです。
例えば、直売所で農家さんと会話してみたり、生産者が発信しているSNSをチェックしたりするだけでも、「誰が、どのようにつくったのか」が身近に感じられるようになります。つくり手の思いや工夫を知ることで、その食材に対する信頼や感謝の気持ちも自然とわいてきます。
また、地域によっては、野菜の収穫体験や農業ボランティア、地元食材を使った加工品づくりのワークショップなどが行われており、家族で楽しめるイベントとして人気です。こうした体験をとおして、単に「買って食べる」だけでは得られない学びや発見があるのも、地産地消の魅力の一つです。
③地産地消の魅力を学び、伝える
地産地消の良さを実感するには、まず「知ること」から始めてみましょう。
例えば、地元の特産品や農作物について調べてみたり、地元の食文化について書かれた本や記事を読んでみたりすると、「なぜ地元のものを食べるのか」が少しずつ見えてきます。
また、お子さんがいるご家庭では、地産地消について一緒に学ぶこともおすすめです。
週末に道の駅で買い物をしながら旬の食材にふれたり、学校の給食や食育の話題に関心を持ったりするだけでも、身近な学びのきっかけになります。
さらに、自分が知ったことや感じたことを、SNSやブログで発信してみるのも良いでしょう。誰かに伝えることで、地元の魅力を広げるきっかけにもなります。
小さな「気づき」を周りと共有することが、地産地消をより身近なものにしてくれるでしょう。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがチームを組み、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「子どもに食べ物の大切さを伝えたい」や「楽しみながら自然や食について学んでほしい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
「イオン チアーズクラブ」で開催された活動

ここでは、イオン チアーズクラブでこれまでに実施してきた活動内容の一部をご紹介します。
イオン チアーズ農園での活動
イオン チアーズクラブでは、チアーズクラブのメンバーを対象にした農作業体験を実施しています。
イオン チアーズ農園では、種まきから収穫までの一連の作業を通して、農作物を育てる大変さや楽しさを体感しながら、自然環境や食べ物の大切さについて学んでいます。
自分たちの手で苗から育てた作物を収穫するという体験は、「食べ物がどのように育ち、私たちの食卓に届くのか」を実感できる貴重な機会です。
こうした体験を通じて、食べ物のありがたみを再認識し、自然の恵みへの感謝の気持ちを育めます。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、地産地消の大切さやメリット、そして私たちにできる取り組みについて解説しました。
地産地消とは、「地元でつくられたものを、地元で食べたり使ったりする」暮らし方のことです。身近なスーパーや直売所で地元の食材を選ぶといった、ちょっとした行動から始められます。
新鮮でおいしい食材を手に入れられるだけでなく、地域の人たちを応援できるなど、環境にもやさしいメリットがあります。もちろん、すべてを地元のものにするのは難しいこともありますが、できるときに、できることから取り入れていくのはいかがでしょうか。
まずは週末の買い物で、地元産の野菜や果物に目を向けてみる。そのような小さな一歩が、地域と未来を支える力になります。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。