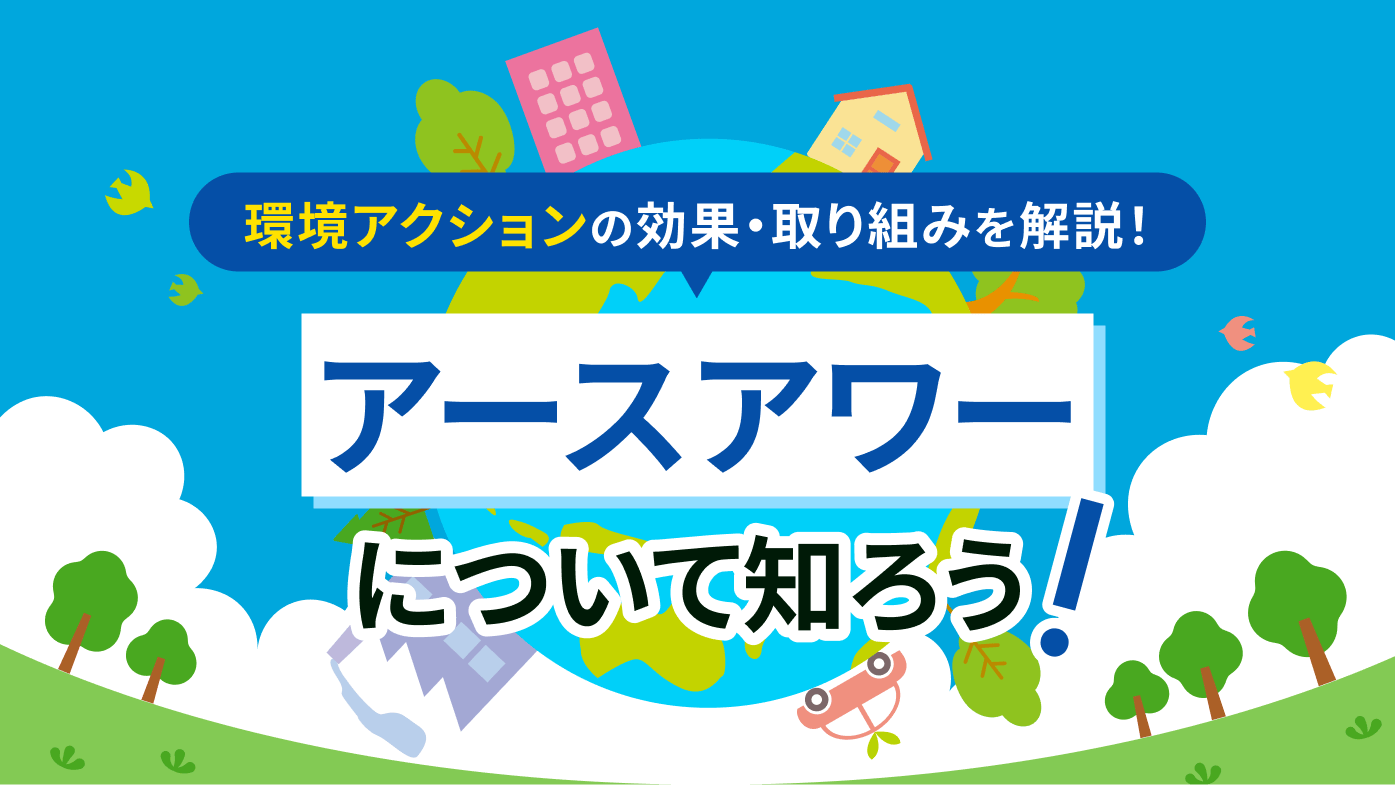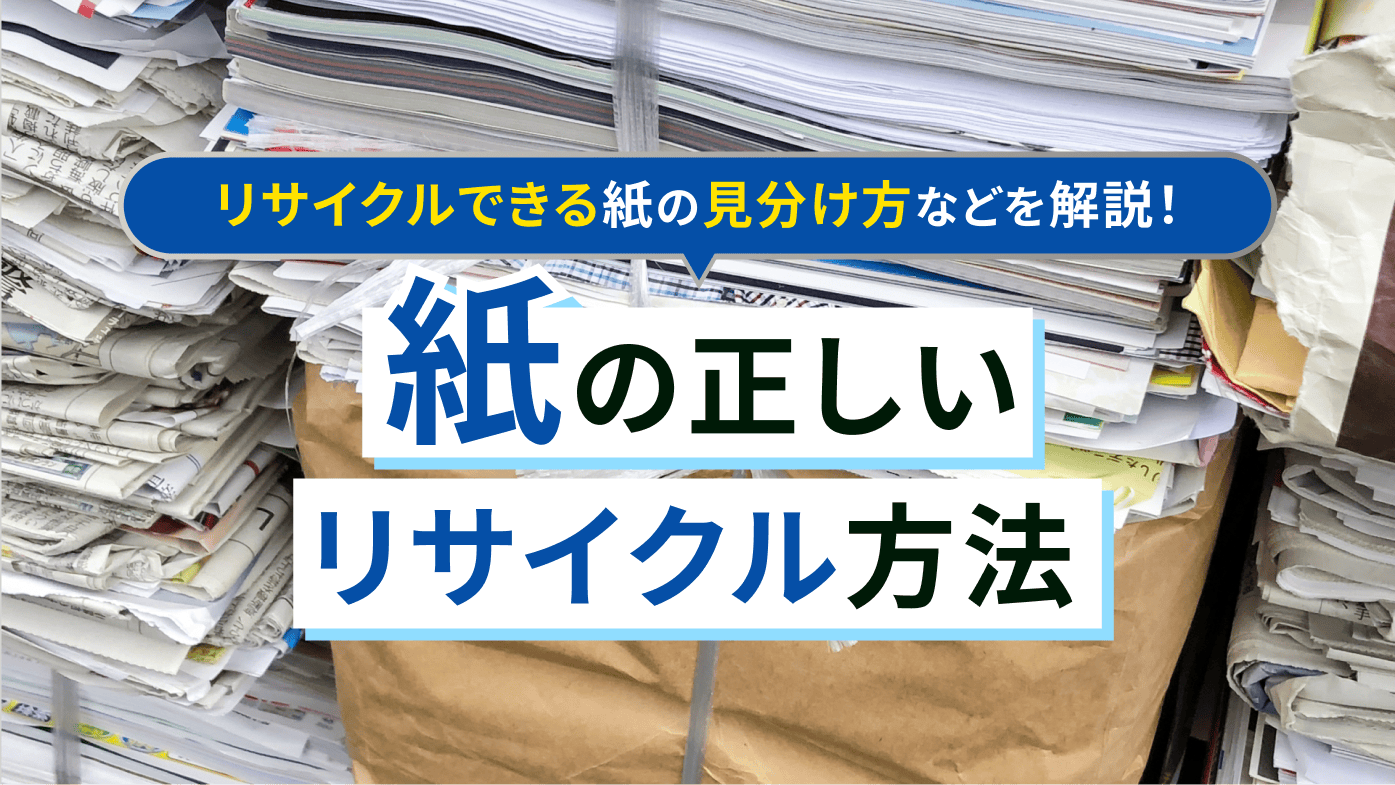
2025.11.18
紙の正しいリサイクル方法って?リサイクルできない紙の見分け方や環境への影響を解説!
紙は私たちの生活に欠かせない資源ですが、リサイクルできる紙とできない紙があることをご存じでしょうか。
紙を正しくリサイクルすれば、森林資源を守り、環境負荷を減らせます。
本コラムでは、紙の正しいリサイクル方法やリサイクルできない紙の見分け方、紙のリサイクルが環境に与える影響について詳しく解説します。
目次
紙のリサイクルとは?まず知っておきたい基礎知識
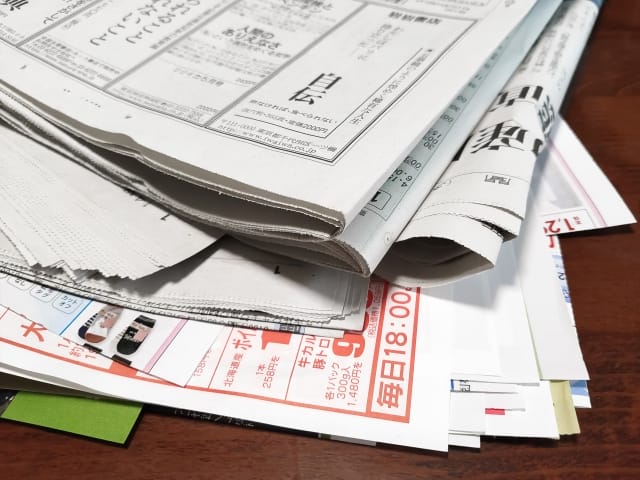
まずはなぜ紙のリサイクルが重要なのかやリサイクルの流れ、リサイクルできる紙とできない紙の見分け方について解説します。
なぜ紙のリサイクルが重要なの?
紙のリサイクルがもたらす大きな利点の一つは、資源の節約にあります。紙の原料となる木を新たに伐採する必要が減るため、森林資源の保護につながるのです。
さらに、可燃ごみに出される紙を減らすことで焼却に伴う温室効果ガスの排出を抑えられる点も、持続可能な社会づくりにおいて重要な要素です。
このように紙のリサイクルは、森林資源を守りながら、温室効果ガスの排出抑制にも貢献する重要な取り組みです。
紙がリサイクルされるまでの流れ
古紙が新しい製品に生まれ変わるまでには、主に5つのステップがあります。
1.発生・回収
家庭や会社などで出た古紙(新聞、雑誌、段ボール)は、自治体や古紙回収業者によって回収されます。
2.古紙問屋
回収された古紙は、古紙問屋に集められます。
古紙問屋では、古紙の重さを量ったあと、古紙の種類(新聞、雑誌、段ボールなど)ごとに分別し、圧縮梱包機で約1トンの塊に圧縮。
圧縮梱包された古紙は、国内の製紙工場に出荷されたり、海外に輸出されたりします。
3.製紙工場
古紙は製紙工場で新しい紙の原料としてリサイクルされます。
圧縮梱包された古紙はパルパーと呼ばれる巨大なミキサーのような機械に入れられ、温水や薬品と一緒に混ぜられ、ドロドロの状態にほぐされます。
そのとき、古紙に含まれるごみやチリなどの異物を取り除きます。
フローテーターという機械で、インクや塗料を取り除き、必要に応じて、古紙を漂白します。
繊維をきれいな水で洗い、抄紙機(しょうしき)で薄く均一に広げて水分を絞り、乾燥させたあと、シート状にします。
乾燥後、巨大なロールに巻き取ったり、決められた大きさに切ったりして、新しい紙が完成します。
4.紙加工工場
製紙工場で作られた紙は、紙加工工場に運ばれ、新聞や雑誌、段ボール箱などさまざまな製品に加工されます。
5.販売
加工された紙製品は、さまざまなお店で販売され、消費者の手に渡ります。
そして、使用後は再び古紙として回収され、リサイクルされるのです。
紙のリサイクルは、家庭での分別から始まるため、私たち一人ひとりが適切に分別することで、資源の有効活用や環境保護に貢献できます。
リサイクルできる紙・できない紙の見分け方
家庭から出る古紙で一般的によく目にするのは次の5種類です。
- 新聞
- 段ボール
- 雑誌
- 飲料用紙パック
- 雑がみ(新聞・雑誌・段ボール・紙パック以外のリサイクル可能な紙で、紙容器や包装紙、紙袋、台紙などが該当します)
これらの紙はリサイクルが可能で、適切に分別すれば、新しい紙製品として再利用されます。
一方で、次のような紙はリサイクルの過程で機械トラブルや不良品の原因になるなど、問題を引き起こす可能性があるため、リサイクルには適しません。
| 名称 | 理由 |
|---|---|
| カバンや靴などの詰め物・緩衝材 (使用済み昇華転写紙) | 古紙処理工程で取り除けず、製品にカビ状の斑点になって現れてしまう |
| 昇華転写紙(アイロンプリントされた紙など) | |
| 臭いや汚れのついた紙 | 臭いが残ってしまったり、汚れが残ったりして衛生上の問題になる |
| 箔押しされた紙(金銀の折紙など) | 古紙処理工程で取り除けず、製品が金属反応を示してしまう |
| カーボン紙・ノーカーボン紙 | 特殊なインクを完全に取り除けず、斑点が製品に現れてしまう |
| 防水加工された紙(紙コップ、紙皿、アイスクリーム容器など) | 古紙処理工程で離解できず、製紙原料とならない |
これらの紙は燃えるゴミ(可燃ゴミ)などとして、自治体のルールに従って処分しましょう。
紙のリサイクルルールは自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体のウェブサイトやゴミ出しカレンダーを確認し、正しく分別することが大切です。
また、地域の古紙問屋や回収業者に相談するのも一つの方法です。
家庭でできる!紙リサイクルの正しい方法

次に家庭でできる紙リサイクルの方法と、分別の際の注意点を解説します。
自治体の分別ルールに従って分ける
紙をリサイクルする際は、自治体の分別ルールに従う必要があります。
お住まいの自治体のルールに従い、「新聞・雑誌」「段ボール」など種類ごとに分け、異なる種類の紙が混ざらないよう注意しましょう。
また古紙の回収方法も自治体ごとに異なり、町内会や子ども会などの地域団体が回収する場合や、家庭ごとに分別して回収業者が回収する場合があるため、迷ったら、お住まいの自治体のウェブサイトやゴミ出しカレンダーを確認するか、直接問い合わせてみましょう。
せっかく分別した古紙を無駄にしないためにも、自治体のルールをしっかり確認し、適切にリサイクルを行うようにしましょう。
紙の種類ごとにまとめて束ねる
紙のリサイクルを適切に行うためには、種類ごとに分別し、正しい方法で出すことが重要です。
次のルールを参考に、リサイクル可能な紙を適切に処理しましょう。
| 名称 | 解説 |
|---|---|
| 新聞・雑誌 | ・サイズを揃えて束ねて出す ・ホチキスやテープはできるだけ外して出す ・シュレッダーで細かくした紙は、他の紙とは分けて出す |
| 段ボール | ・平らに折りたたんで出す ・複数枚ある場合は、まとめて束ねるか、テープで留める ・大きな段ボールは、小さく折りたたんでから出す ・濡れた段ボールは乾かしてから出す |
| 飲料用紙パック | ・中をすすぎ、乾かしてから出す ・開けられるタイプのパックは開いて出す ・キャップやストローは取り外して、別で捨てる |
| 雑がみ | ・バラバラにならないように紙袋や段ボールに入れて出す ・紙以外のものは、できるだけ取り除いて外す |
紙をリサイクルに出す前に、軽い汚れは拭き取り、濡れた紙は乾かしましょう。
ただし、油や食品汚れがひどい紙はリサイクルが難しいため、燃えるごみとして処分してください。
自治体のルールを確認し、正しく分別しましょう。
リサイクル回収に出せなかったときはどうすればいい?
古紙回収日に出しそびれてしまっても、他にもリサイクルできる方法があります。
適切な回収ルートで無駄なくリサイクルに協力しましょう。
新聞販売店の回収サービスを利用する
新聞を購読している場合、新聞販売店による古新聞の回収サービスを利用できることがあります。
回収サービスは、定期的に自宅まで回収に来てくれるため、持ち込む手間が省け、回収日を忘れてしまっても安心です。
ただし、販売店や地域によっては回収サービスを行っていない場合もあるため、事前に確認が必要です。また、新聞を購読していない方は利用できません。
スーパーやコンビニ、公共施設の回収ボックスを活用する
スーパーマーケットやコンビニエンスストア、公共施設などには古紙を回収する専用のボックスが設置されていることがあります。
回収ボックスは多くの場合、施設の営業時間内であれば自由に利用でき、買い物や外出のついでに古紙を持ち込めるため便利です。
古紙回収日に出しそびれてしまった場合でも、新聞販売店の回収サービスや、スーパー・コンビニ・公共施設の回収ボックスを活用すれば、適切にリサイクルできます。
紙はできるだけゴミとして処分せず、身近なリサイクル手段を利用して、環境保護に貢献しましょう。
紙のリサイクルによってもたらされる環境へのメリットとは?

紙のリサイクルは、環境や社会に大きな影響を与える重要な取り組みです。
ここでは、紙のリサイクルがもたらすメリットを紹介します。
森林保護・温室効果ガス排出の抑制
紙をリサイクルすることは上述している通り、森林資源の保護や温室効果ガス排出の抑制につながります。
日本における紙・板紙の年間生産量は、2022年時点で2,368万トンに達しており、私たちの生活にとって紙は欠かせない存在となっています。
しかし、紙の消費量が増えるほど原料となる木の伐採も進み、森林が失われるリスクが高まります。そこで、紙をリサイクルして資源を節約すれば、その分、新たに木を伐採する必要がなくなり、森林の保護につながるのです。
また、紙ゴミの排出を抑えることでゴミ焼却時に排出される温室効果ガスも抑制できます。
紙の処理コスト削減
紙をリサイクルすることは、廃棄物の処理コスト削減にもつながります。
紙をゴミとして出すと、特定の業種の事業から出る廃棄物以外の多くは一般廃棄物として処理されます。一般廃棄物には紙以外のゴミも多く含まれていますが、この一般廃棄物を処理するのに、2021年は21,449億円ものコストがかかりました。
また、事業系一般廃棄物※を調査したところ、搬入された廃棄物のうち16%はリサイクル可能な紙類だという報告もあります。
この16%の紙類を適切にリサイクルすることが、廃棄物の処理にかかるコストの削減につながっていくのです。
※ 事業活動によって排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に分類されないもの。廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物に分けられており、一般廃棄物はさらに、事業活動によって排出される事業系一般廃棄物と、家庭から出る家庭系一般廃棄物の2種類に大別されている。
今日からできる!紙の消費を減らすアイデア

ここでは、家庭やオフィス、学校で紙を使用する際にすぐに実践できる、環境を考えた具体的な行動をご紹介します。
家庭でできる!紙の消費を減らす行動
家庭で紙の消費を抑えるために取れる行動は、FSC認証製品を積極的に選ぶことや、雑がみの分別を徹底することなどが挙げられます。
1.FSC認証製品を選ぶ
紙製品を購入する際に、「FSC認証マーク」が付いているモノを選ぶことで、適切に管理された森林から採取された木材を使用した製品を支援できます。
FSC認証とは、「森林管理協議会(Forest Stewardship Council)」が持続可能な森林管理を保証する国際認証制度であり、違法伐採や環境破壊を防ぐ取り組みの一環です。
紙製品を買う際には、FSCマークをチェックし、環境負荷の少ない製品を積極的に選びましょう。
2.雑がみを資源ゴミとして分別する
「雑がみ」とは、新聞や雑誌、段ボール以外のリサイクル可能な紙類のことを指します。
雑がみは燃えるゴミとして捨てられがちですが、実はリサイクル可能な貴重な資源です。
多くの自治体では、雑がみを資源ゴミとして回収しており、適切に分別することでリサイクルの効率が向上します。
家庭内で雑がみをまとめるための専用ボックスを用意し、定期的に資源回収に出す習慣をつけると良いでしょう。
学校や仕事でできる!紙の使用量を減らす工夫
紙の消費を抑える方法として、最も代表的なのが「ペーパーレス化」です。
ペーパーレス化とは、その名の通り、紙の使用量を減らし、デジタル技術を活用することを指します。
学校や仕事では、次のような取り組みが行われています。
- 資料やプリントなどをデータで配布し、紙の使用量を削減する
- 紙の書類をスキャンしてデータ化して管理し、紙はリサイクルする
- ノートや手帳の代わりにタブレット端末やスマートフォンを活用する
- 印刷する際は両面印刷や、1枚に2ページ分を印刷する
- ホワイトボードを利用する
紙の使用量を減らすことは、単なるコスト削減だけでなく、森林資源の保護や温室効果ガスの排出削減につながります。
ペーパーレス化は、少しの工夫から始められます。
まずは、自分ができることから実践し、紙の使用を減らす意識を高めていきましょう。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがメンバーで協力し合い、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「子どもを自然と触れ合わせたい」や「楽しみながら環境や社会について学んでほしい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
「イオン チアーズクラブ」で開催された活動
イオン チアーズクラブなら、お子さんが自然の中でさまざまな体験をし、環境について学ぶことができます。
ここでは、イオン チアーズクラブが実際に行った、環境問題に関する体験活動をいくつかご紹介します。
さくらの植樹

北海道厚真町(あつまちょう)では、イオン チアーズクラブのメンバーと地域の協力団体を含む約150名が集まり、さくらの植樹を行いました。
植樹が行われたのは、ダム工事によって発生した大量の土砂を盛土として活用した場所です。
将来、この地がさくらの名所として人々の憩いの場になることを願い、エゾヤマザクラの苗木1000本が植えられました。
参加者たちは一本一本丁寧に植え、大切に育ってほしいという思いを込めながら作業に取り組みました。
植樹祭「そよら福井開発」

ショッピングセンター「そよら福井」のオープンに先立ち、植樹祭が開催されました。
このイベントには、4つのイオン チアーズクラブから計25名のメンバーが参加し、他の参加者と共に植樹宣言を行いました。
その後、グループに分かれて植樹活動を開始し、地域の緑化に貢献しました。
また、近隣の幼稚園児や小学生、その保護者約200名を含む総勢約225名がこの植樹祭に参加し、36種類・2100本の苗木を植樹しました。
子どもたちも熱心に苗を植え、楽しみながら学びの機会を得ることができました。
Tシャツのリサイクルによる服の循環体験

イオン チアーズクラブのメンバーが衣料廃棄問題について楽しく学ぶことのできる、サステナブルワークショップを実施しました。
ワークショップでは、「日本国内でいらなくなった服の量」や「自宅にある着なくなった服の数」について、クイズを交えながら身近な衣料廃棄問題について学習しました。
その後、チアーズTシャツを綿に戻し、紙やフェルトへリサイクルする過程を動画で視聴しました。
さらに、参加者はリサイクル素材で作られた活動ノートを、自宅から持ち寄った古着でデコレーションし、オリジナルノートを作成するなど、アップサイクル※を体験しながら、衣類の再利用について理解を深めました。
※ 捨てるものに手を加え、価値をつけて新しい製品へと生まれ変わらせる手法
この他にも、イオン チアーズクラブではさまざまな活動を行っています。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、紙のリサイクルについて解説しました。紙のリサイクルは、限りある森林資源を守り、ゴミの削減や温室効果ガス排出量の抑制につながる、環境に優しい取り組みです。
日本は世界トップクラスの古紙利用率を誇っていますが、さらなる向上のためには、一人ひとりの意識と行動が欠かせません。
日常生活の中で、紙を無駄にせず大切に使うことや、正しく分別することが、持続可能な未来への第一歩となります。
紙は私たちの生活に欠かせない存在です。これからも長く使い続けられるよう、できることから実践していきましょう。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
公益財団法人イオン1%クラブでは、小学生を中心とし、体験学習を通して自然や環境に向き合える「イオン チアーズクラブ」も運営しています。
イオン チアーズクラブではリサイクル工場の見学や、過去にはサトウキビを使ったさまざまなリサイクルの体験など、環境に関する体験や学習をしています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」などさまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLからご覧ください。