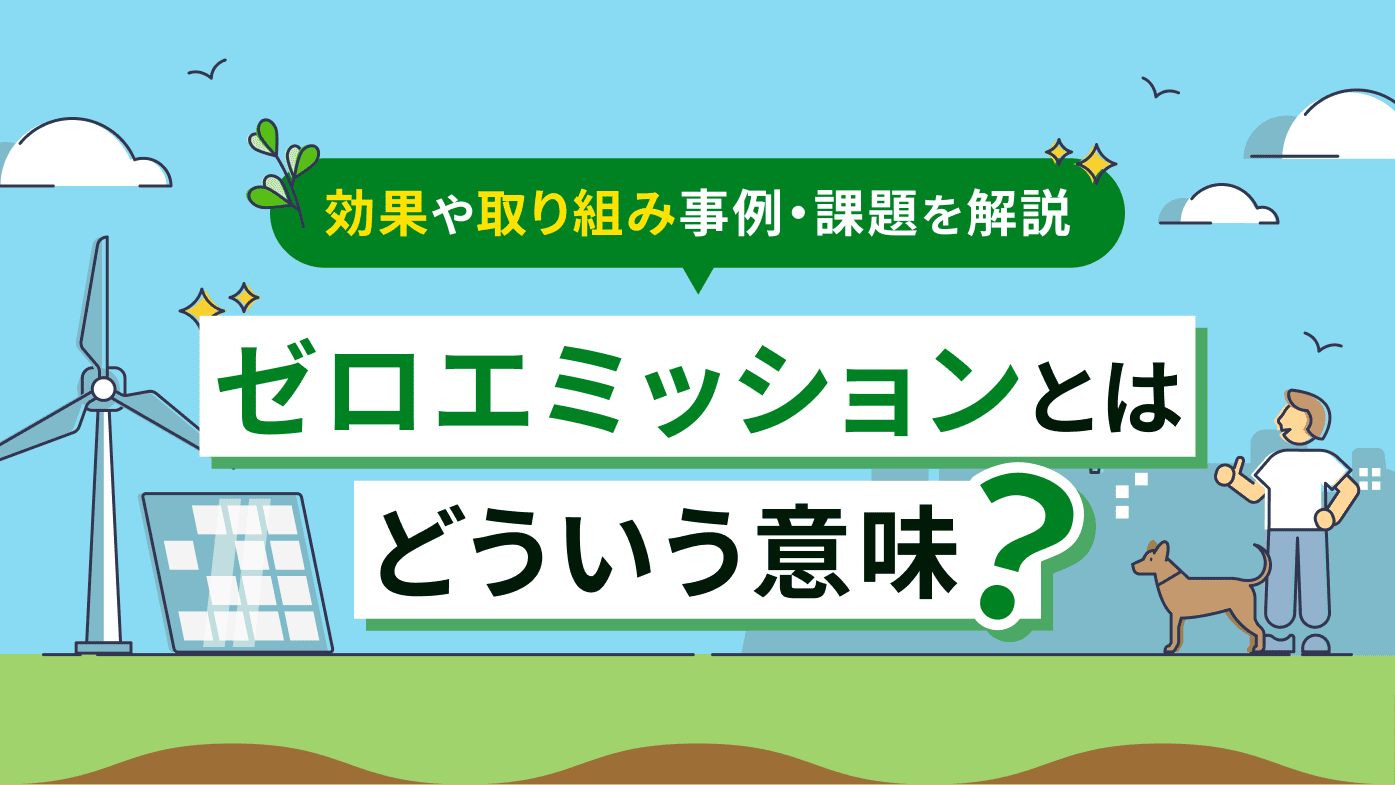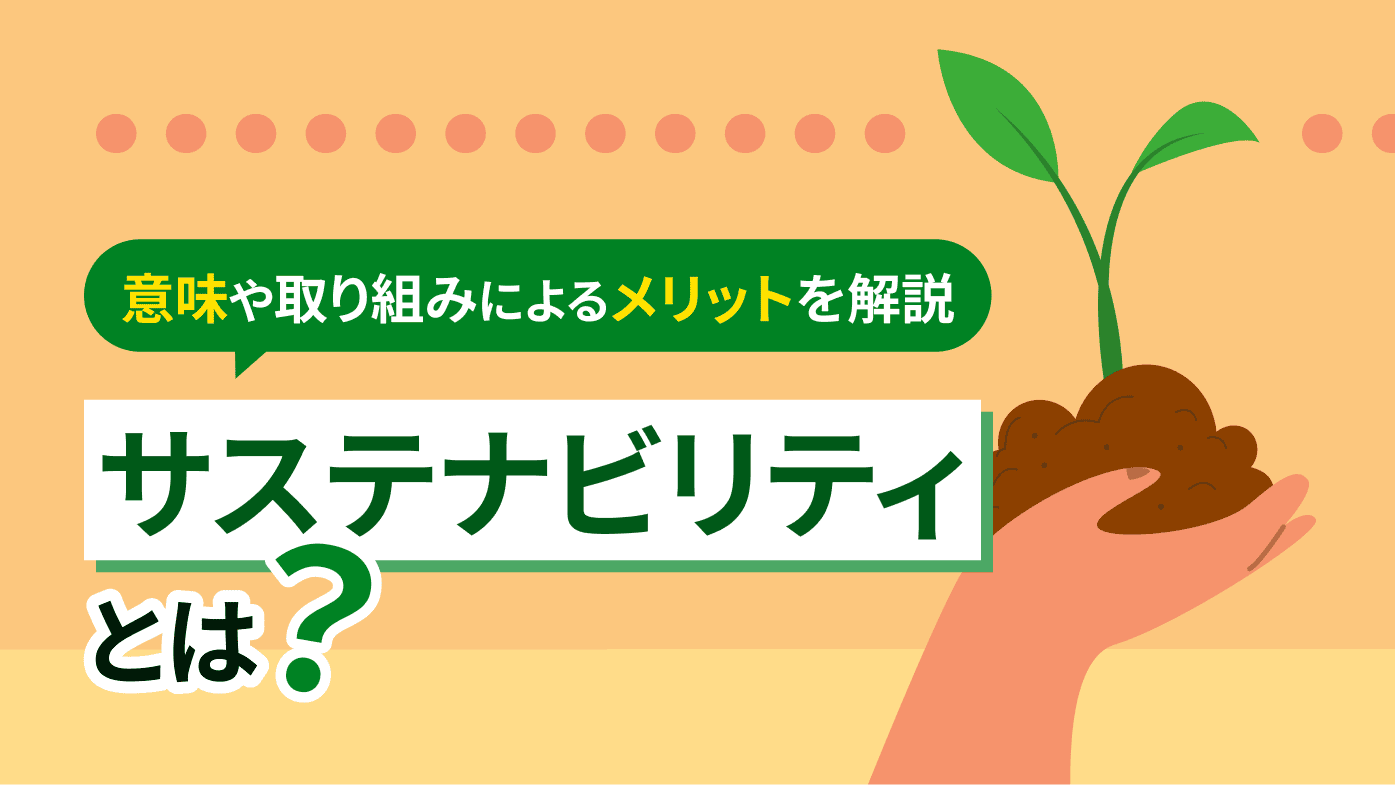
2025.07.22
サステナビリティとは?意味や取り組みによるメリットを解説
近年、「サステナビリティ」という言葉をニュースや広告で目にする機会が増えましたが、その意味をしっかりと説明できる方は意外と少ないのではないでしょうか。
このコラムでは、サステナビリティの基本的な意味や背景、注目されている理由、そして私たちの日常生活にどのように関わっているのかを、わかりやすく解説します。
さらに、企業や個人による具体的な取り組み事例もご紹介しますので、今すぐ始められるヒントがきっと見つかるはずです。
目次
サステナビリティの意味とは?言葉の由来と基本の考え方

「サステナビリティ」という言葉は、直訳すると「持続可能性」となります。しかし、その言葉が何を意味し、どのような背景から生まれたのかについては、意外と知られていません。
ここでは、サステナビリティという言葉のルーツや考え方の変遷をたどりながら、現代社会でなぜこれほど重要視されているのかを解説します。
サステナビリティの由来と歴史的背景
「サステナビリティ(Sustainability)」という言葉は、「sustain(持続する)」と「able(〜できる)」に由来します。
この概念が世界的に注目されるきっかけとなったのが、1987年に国連の「環境と開発に関する世界委員会(WCED)」が発表した報告書『我ら共有の未来(ブルントラント報告)』です。
この報告書のなかで、サステナビリティは「将来世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発」と定義されました。
サステナビリティが意味する「持続可能な社会」とは?
「持続可能な社会」とは、環境・社会・経済の3つの分野がバランスよく保たれ、将来の世代も今と同じように豊かな生活を送れる社会のことを指します。
例えば、私たちが便利さを追い求めて自然資源を過剰に消費し続ければ、未来の人々の暮らしが損なわれる可能性があります。
サステナビリティの基本的な考え方は、「現在の私たちの快適さ」と「将来の世代の生きる権利」の両立を目指すことにあります。
また、持続可能な社会の実現には、貧困や格差の是正、教育の機会確保、ジェンダー平等の推進など、さまざまな社会課題の解決も欠かせません。
つまり、サステナビリティとは、単に「エコ」や「環境にやさしい」といった意味だけでなく、すべての人々が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会を目指す包括的な考え方なのです。
サステナビリティを支える3つの柱

サステナビリティは、「環境」「社会」「経済」の3つの柱がバランスよく調和してこそ、持続可能な社会が実現します。
ここでは、それぞれの要素が果たす役割について解説します。
①環境保護
サステナビリティのなかでも、もっとも広く知られているのが「環境」に関する取り組みです。
地球温暖化、海洋プラスチック汚染、森林伐採、生物多様性の減少など、人間の活動による自然への影響は年々深刻化しています。
こうした問題に対応するためには、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入、資源のリサイクル、そして循環型経済への転換といった多角的な取り組みが不可欠です。
近年では、企業や自治体が二酸化炭素排出量の削減目標を掲げるなど、積極的な環境対策を進める動きも活発になっています。
環境の持続可能性を守ることは、私たちが生きる地球そのものの「生存基盤」を維持することにつながります。
その意味で、「環境」はサステナビリティを構成する3つの柱のなかでも、もっとも基本的で重要な柱と言えるでしょう。
②社会開発
サステナビリティにおける「社会」の視点とは、すべての人に公正な機会を提供し、安心して暮らせる社会の仕組みをつくることを意味します。
具体的には、ジェンダー平等の推進、教育の普及、健康や福祉の充実、人権の尊重、そして貧困の解消などが挙げられます。
こうした取り組みは、企業による「ダイバーシティ(多様性)の推進」や、自治体が進める「地域包括ケアシステム(高齢者や障がい者を地域全体で支える仕組み)」など、さまざまなかたちで社会に広がっています。
多様な背景や価値観を持つ人々が、互いに尊重し、差別なく共に暮らし、働ける社会の実現は、サステナビリティのなかでも非常に重要な柱の1つです。
人が安心して生きられる社会基盤があってこそ、持続可能な未来は実現できるのです。
③経済開発
サステナビリティにおける「経済」の視点とは、経済活動が将来の世代に悪影響を与えることなく、長期的に安定した成長を実現できる仕組みをつくることです。
そのため、短期的な利益追求にとどまらず、雇用の安定や地域経済との共生を図り、持続的価値を創造していくことが企業には求められます。
近年では、「ESG投資(環境・社会・ガバナンスに配慮した投資)」が広がっており、持続可能性を重視する企業への評価が高まっているのもその表れです。
こうした動きは、企業規模や業種を問わず広がりを見せています。例えば中小企業における「地元に根ざしたビジネス」や「従業員の健康支援」など、地域や企業の規模に応じた取り組みが、地域社会と経済の未来を支える重要な役割を担っています。
持続可能な経済は、豊かな社会と自然環境や生活環境の調和がとれた暮らしを支える基盤の一つなのです。
サステナビリティはなぜ注目されているの?

サステナビリティが注目されるようになった背景には、気候変動による自然災害の増加、貧富の格差の拡大、資源の枯渇など、地球規模で深刻化するさまざまな課題があります。
こうしたなか、2015年に国連が掲げた「SDGs(持続可能な開発目標)」が世界共通の目標となり、政府・企業・個人が「このままのあり方では環境・社会・経済のバランスが取れた社会を持続できない」と強く意識するようになりました。
特に若い世代を中心に、環境や人権、社会課題に配慮したモノやサービスを選ぶ「エシカル消費」の考え方が浸透しつつあり、企業側もその価値観に応えるかたちで、サステナビリティを経営の中心に据える動きが加速しています。
世界が抱える環境問題について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
地球からのSOS!?環境問題の例や原因と今日からできることを解説
サステナビリティの実現に向けて私たちができる取り組みは?

サステナビリティは、政府や企業だけの課題ではありません。私たち一人ひとりの行動も、持続可能な社会の実現に大きく関わっています。
難しく考える必要はありません。大切なのは、日々の暮らしのなかで、「できることから少しずつ」始めることです。
ここでは、誰でも無理なく取り入れられる「サステナブルな行動のヒント」をご紹介します。
毎日の買い物を「エシカル消費」に変えてみよう
「エシカル消費」とは、人や社会、環境に配慮してつくられたモノやサービスを選ぶ消費行動のことです。
例えば、次のような選び方がエシカル消費にあたります。
- フェアトレード認証のついたモノを購入する
- 地元で生産された野菜や食品を選ぶ
- 再生素材を使ったエコ商品や包装(パッケージ)を選ぶ
こうしたモノを選ぶだけでも、間接的に社会課題の解決や環境保全に貢献できます。
日本でも、消費者庁がエシカル消費の普及に取り組んでおり、学校や自治体でも関連する教育活動が広がっています。
「これ(モノ)は、どんな人が、どんな方法で作ったんだろう?」
そんなふうに、いつもの買い物にちょっとした視点を加えるだけで、社会を変える第一歩になるのです。
普段の生活にサステナブルな工夫を取り入れてみよう
サステナビリティの実現は、日常のちょっとした工夫や意識の積み重ねから始まります。
例えば、マイバッグやマイボトルを持ち歩く、電気をこまめに消す、節水シャワーヘッドを使うなどの習慣は、環境への負荷を減らす有効な取り組みです。
食事でも、旬の食材や地元産の野菜を選ぶ(地産地消)ことで、食材の輸送にかかるエネルギーや二酸化炭素排出を抑えられます。
また、家電を購入する際に省エネラベルをチェックしたり、使い終わった製品をリサイクルに出したりすることも、身近なサステナブルな選択の一つです。
暮らしのなかには誰にでもできることがきっとあります。無理のない範囲で、できることから少しずつ取り入れてみましょう。
身近なできることについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【その小さな一歩が未来を変える】一人ひとりができる地球温暖化対策について解説
サステナビリティとよく似た言葉と違いを解説!

「サステナビリティ」という言葉は、SDGsやCSR、ESGなどとよく一緒に語られますが、それぞれ意味や対象が異なるため、混同しないように注意が必要です。
ここでは、それぞれの違いと関係性をわかりやすく解説します。
サステナビリティとSDGsの違い
SDGsは、サステナビリティという大きな理念を、具体的な目標や数値に落とし込んだ「実行のための指針」と言えます。
例えば、「貧困をなくす」「教育を受けられる機会を増やす」「気候変動に対処する」といった幅広い課題が設定されています。
どちらも「誰一人取り残さない社会の実現」を目指しており、サステナビリティとSDGsは密接に関係しています。
つまり、「サステナビリティ=理念」、「SDGs=その理念を実現のための道しるべ」と理解するとわかりやすいでしょう。
SDGsについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【小学生向け】SDGsって何だろう?わかりやすく17の目標などを解説!
個人でできるSDGsへの取り組み具体例6選!日本の企業や政府の取り組みも紹介!
サステナビリティとCSRの違い
CSRとは、「企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)」の略で、企業が利益を追い求めるだけでなく、社会や環境に配慮した責任ある行動を取ることを意味します。
例えば、環境に配慮した製品づくりや、地域貢献、従業員の働きやすさの向上などがCSRの取り組みとして挙げられます。
CSRはあくまで企業の立場からの取り組みであり、一方でサステナビリティは、企業に限らず社会全体を対象とした広い考え方です。
そのため、CSRはサステナビリティのなかに含まれる一部の活動と捉えると、両者の関係がイメージしやすくなります。
CSRについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
企業のCSR活動とは?私たち消費者へのメリットまでわかりやすく解説
サステナビリティとESGの違い
ESGとは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字を取った言葉で、主に投資の観点から企業を評価するための基準です。
ESG投資では、企業の利益や売上だけでなく、環境保護への取り組み、人権・労働問題への対応、健全な経営体制といった項目も含めて企業の価値を判断します。
つまり、ESGは「企業がサステナビリティにどれだけ配慮しているか」を評価する「物差し」として活用されているのです。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがメンバーで協力し合い、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「自然や社会に関心を持つきっかけを作りたい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、サステナビリティの基本的な意味や背景、そして私たちが日常生活のなかでできる取り組みについて解説しました。
サステナビリティとは、環境・社会・経済のすべてを持続可能にするための重要な考え方です。実現するためには、政府や企業だけでなく、私たち一人ひとりの行動にかかっています。
まずは、身近なところからできることに取り組んでみましょう。
例えば、「人や環境に配慮したモノを買う」「無駄を減らす」といった、ほんの小さな取り組みでも構いません。こうした日々の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出し、持続可能な社会をつくる確かな一歩となるのです。
今日からあなたも、自分なりのサステナブルな暮らしを始めてみませんか?
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。