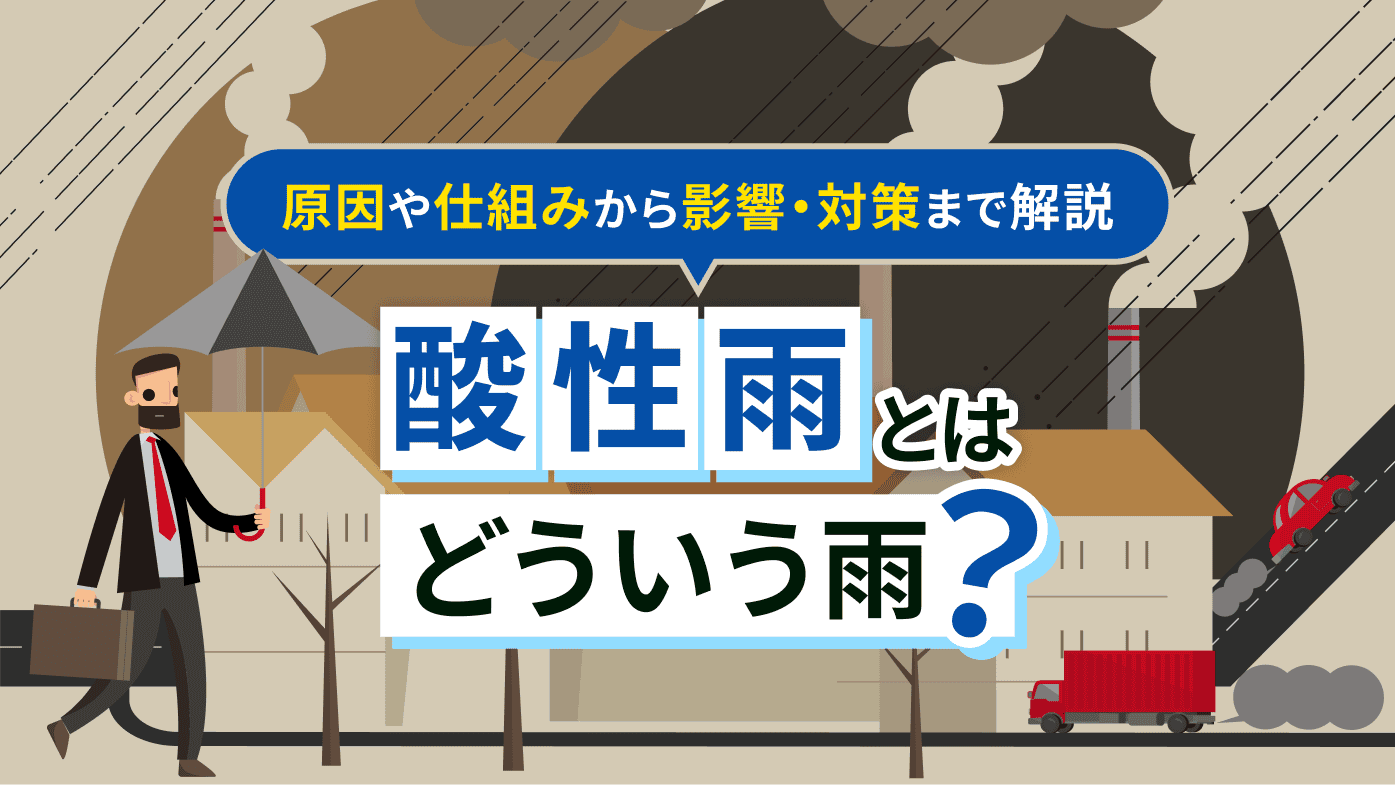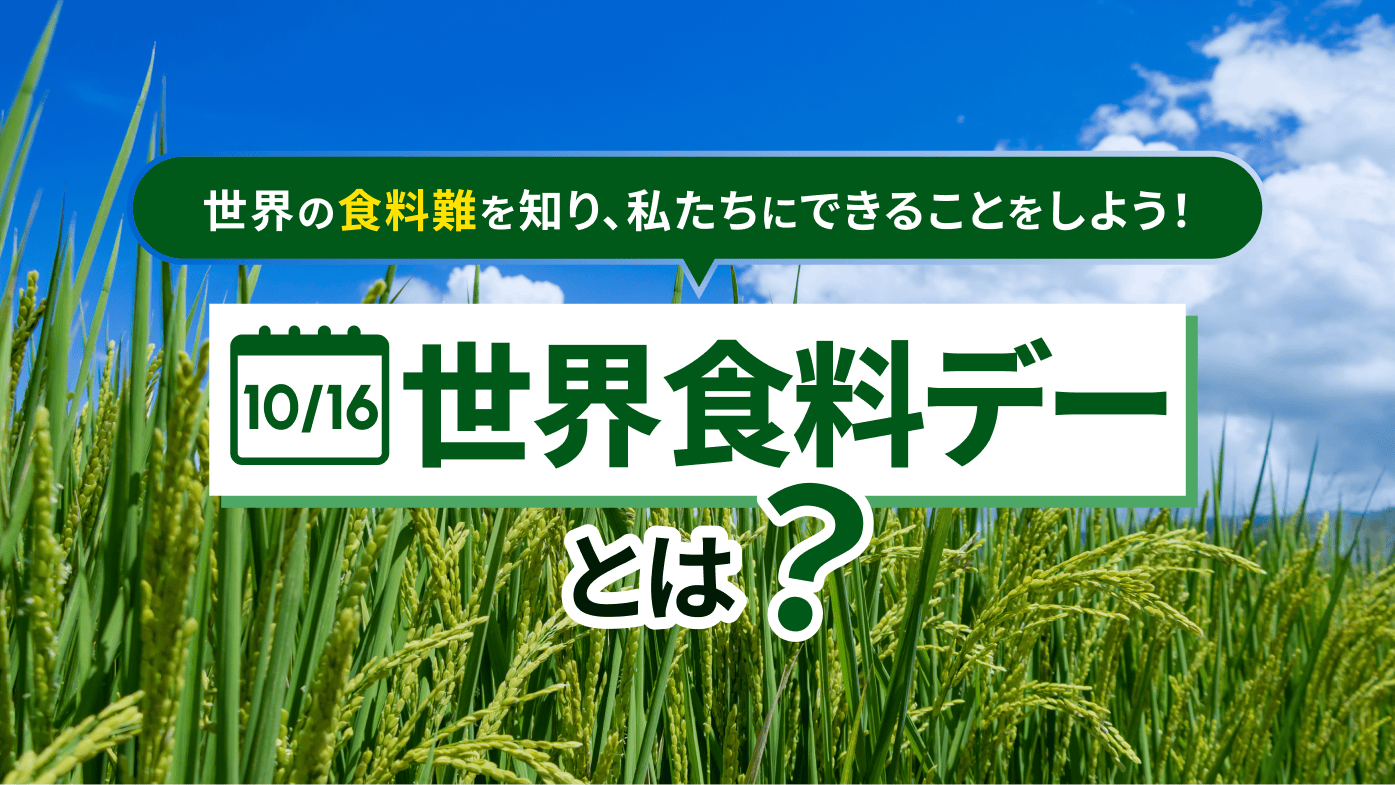
2025.08.26
世界食料デーとは?世界の食料難を知り、私たちにできることをしよう!
毎年10月16日は、国連が定めた「世界食料デー」です。
世界では十分な量の食料が生産されているのにも関わらず、飢餓に苦しむ人々が数多く存在し、特に子どもたちの健康や成長に深刻な影響を与えています。
世界食料デーは、私たちが「食料問題」について考え、行動を起こすきっかけとなる大切な日です。
本コラムでは、「世界食料デーとは何か?」「なぜこの日がつくられたのか?」という基本情報を中心に、食料難の現状、そして私たちが身近にできる取り組みについて紹介します。
目次
10月16日は世界食料デー

毎年10月16日は「世界食料デー」です。
ここでは「世界食料デーとは何か」について、由来や成り立ちも含めて解説します。
よく目にする「食料」と「食糧」の違いについてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
世界食料デーとは何をする日?
10月16日の世界食料デーとは、世界的な食料問題について考え、具体的な行動を起こすために国連が定めた日です。
食料は、私たちが生きていくために空気や水に次いで大切なものです。
世界人権宣言第25条の1でも「すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する」と定められており、生命を維持するためには十分な食料の確保が欠かせません。
しかし、世界の国や地域には、食料が不足して十分にご飯が食べられない人々が大勢います。
世界食料デーは、そのような現実に目を向け、アクションを起こすきっかけとなることを目指しているのです。
世界食料デーの由来・成り立ちとは?
世界食料デーは、国際連合食糧農業機関(FAO)の創設記念日が1945年10月16日であることにちなんで制定されました。
FAOとは、「すべての人々が栄養ある安全な食べ物を手にいれ健康的な生活を送ることができる世界」を目指す国際連合機関です。
この目的を達成するため、FAOでは①飢餓、食料料不安及び栄養失調の撲滅、②貧困の削減と全ての人々の経済・社会発展、③現在及び将来の世代の利益のための天然資源の持続的管理と利用、を主要な3つのゴールと定めています。
FAOの設立当時、世界各地には飢餓や栄養失調に苦しむ人々が数多くいました。問題の規模が大きいからこそ、定めたゴールを達成するためには、その状況を社会的に認知してもらい、解決に向けた取り組みを促す必要があったのです。
このような問題意識を踏まえ、1979年に開催された第20回FAO総会で「世界食料デー」の創設が提案されました。そして、1981年に初めて世界食料デーが実施されることになったのです。
食料と食糧の違いは?
世界食料デーについてインターネットやSNSを見ていると、「食料」または「食糧」という2つの言葉が使い分けられていて、戸惑った経験はありませんか。
それぞれの言葉には、次のような意味があります。
- 食料:魚介類、肉類、野菜、果物など、すべての食べ物のこと
- 食糧:特に米や麦など穀物を中心とした、主食となる食べ物のこと
「食料」はすべての食べ物を包括的に指すことから、一般的によく目にする言葉です。一方、「食糧」は主食となる食べ物を指すケースが多く見られます。
なお本コラムでは、「世界食料デー」にならい、固有名詞以外は「食料」で統一しています。
【日本】世界食料デーに開催されるイベント紹介

日本でも世界食料デーに合わせて、国や自治体が主催するさまざまな啓発イベントが開催されています。
食料問題に対する理解を深めたり、フードロス削減の行動を促したりする取り組みが多くの地域で実施されており、誰でも気軽に参加できる内容がそろっています。
ここでは、日本で実施されている代表的なイベントを3つご紹介します。
世界食料デー記念シンポジウム
「世界食料デー記念シンポジウム」は、世界の食料問題についての理解を深めることを目的に、外務省と国際連合食糧農業機関(FAO)が共同で開催しているイベントです。
その年ごとのテーマに沿って、専門家による講演やパネルディスカッションが行われ、最新の国際動向や課題について学べます。
リアルイベントとして開催されることもあれば、オンライン配信が行われることもあり、一般の方も参加可能です。10月中旬に開催され、食や栄養、環境、貧困など多角的な視点で「食」の未来を考える場として、多くの関心を集めています。
WORLD FOOD NIGHT
「WORLD FOOD NIGHT」は、世界の食料問題に対して行動している方や、これからアクションを起こしたいという方が交流できるイベントです。横浜市が開催しています。
新型コロナウイルス感染症の流行以前はオフラインで、以後はオンラインで、食料問題に対して実際に取り組んでいる方々からのプレゼンテーションが行われるほか、質疑応答の時間も設けられています。
例年のプレゼンテーションには、FAO駐日連絡事務所の所長も参加しているほか、食に関するさまざまな専門家から貴重な話を聞ける機会となっています。
#ごちそうさまチャレンジ
「#ごちそうさまチャレンジ」は、食事を通じて世界の飢餓問題に貢献できる、SNS発の参加型チャリティーキャンペーンです。国連WEP協会が実施しています。
ハッシュタグ「#ごちそうさまチャレンジで飢餓をなくそう」をつけて、食品ロス削減のアクションや「ごちそうさまポーズ」の写真をSNSに投稿するという、気軽に参加できるのが特徴的でした。
1投稿につき、協力団体から学校給食5人分(150円)が国連WFPの「学校給食支援」へ寄付されます。
【世界】世界食料デーに開催されるイベント紹介

世界各国でも世界食料デーに合わせて、国連機関や各国政府、NGOなどがさまざまなイベントを展開しています。
式典やフォーラムを通じて、食料問題の重要性を訴えるとともに、国際的な連携と市民参加を促進する大切な場となっています。
世界食料デー国際記念式典
「世界食料デー国際記念式典」は、10月16日の世界食料デーの日に、国際連合食糧農業機関(FAO)本部が開催している国際的な式典です。
式典では、世界各国の首脳やFAO関係者、国際機関、各国大使らが一堂に会し、現在の課題を述べ、また課題に立ち向かう決意を共有します。
また、2025年度はFAOの創設からちょうど80周年ということで、食料農業博物館のオープンを予定しているほか、式典もより特別なものになると想定されます。
世界食料フォーラム
「世界食料フォーラム(World Food Forum)」は、現代の食や農業をめぐる課題に対して世界の青年たちが声を上げ、新しい未来を提案する国際的なイベントです。
世界食料フォーラムは、FAOの青年委員会の発案がきっかけで、2021年に初めて開催されました。このときの参加者もまた、さまざまな地域や組織に属する若者たちであり、日本からも若手の農林漁業者が参加しました。
その後も世界食料フォーラムは続けられており、参加者の年齢層こそ広がっていますが、主導するのは若年層です。
世界食料デーに考えたい「食料問題の現状と課題」

日本では、食料に関するインフラが比較的整っているだけに、食料問題を意識する瞬間は少ないのではないでしょうか。
しかし、2025年、日本でも米の価格が大幅に上がり、問題となる事態が起こりました。食料問題は、決して他人事ではありません。
毎年10月16日の世界食料デーは、世界の食の現実に目を向けるきっかけをくれる日です。
そこでここでは、食料問題に関する前提知識のほか、世界の現状と課題についてわかりやすく解説します。
そもそも食料問題とは?
食料問題とは、食料に関する問題全般を指しますが、現代で特に取り沙汰されているのは、食料不足による「飢餓(きが)」と、「フードロス」です。
現代における食料問題は、単純に「食べ物が足りないから起こる」わけではありません。
実際、食べ物の生産量や備蓄量に関してだけいえば、世界中の人々が食べても十分な量があるといわれています。
しかし、「お金がなくて買えない」や「技術や知識不足で効率よく流通や保存ができずに腐らせてしまう」などの理由によって、飢餓や栄養不良を起こす人々が後を絶ちません。
その一方で、お金に余裕があり、技術や知識もそろっている国では、食べきれない量を生産・製造しては、大量に廃棄(フードロス)しているといった問題も起こっています。
このように現代の食料問題は、二極化しているのが特徴です。
食料問題がもたらす悪影響
食料問題は個人の健康にはもちろんのこと、社会全体にさまざまな悪影響を及ぼします。
例えば、子どもが成長期に十分な栄養を摂れないと、発育を阻害します。それも身長や体重が年齢相応に大きくならないだけでなく、知能の発達にも遅れが出てしまうのです。
結果、無事に大人になれたとしても、栄養不良であったことが一生涯にわたって足を引っ張りかねません。
また、食料を確保するために無理な農地や酪農地の開発、過剰な水の使用などが行われれば、環境破壊や生態系への悪影響にもつながります。
このように食料問題は社会や環境と密接に結びついており、私たちの暮らしの土台を揺るがしかねない深刻な問題なのです。
食料問題の現状と課題
先にお話しした通り、世界では「食べ物が満足に手に入らない人もいれば、廃棄または食べきれずに廃棄する人もいる」といった食の不均衡が起こっています。
国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した「世界の食料安全保障と栄養の現状(SOFI)2024年報告」によれば、2023年時点の栄養不足人口は7億1,300万人(世界人口の8.9%)から7億5,700万人(9.4%)と推定されています。
食糧問題に伴う栄養不足が特に慢性化しており深刻なのは、アフリカやアジア地域です。
一方で、WWF(世界自然保護基金)が2021年7月に発表した報告書によると、世界全体の食品廃棄量は年間で25億トンです。2011年にFAOが発表した量に比べ、約2倍も増えています。
このような現状を改善するには生産や流通のためのインフラや管理システムを、世界規模で整えることが重要だといわれています。
また、フードロス問題に関しては、私たち一人ひとりが食べ物を大切にし、無駄にしないといった意識および行動の改革も大切でしょう。
世界食料デーに行動しよう!フードロス削減への取り組み

食料問題とフードロスは密接に結びついており、世界各国でフードロス削減に向けた取り組みが進んでいます。
こうした動きに合わせて、私たち一人ひとりもフードロスに対して何ができるかを考え、実行していくことが大切です。
ここでは、世界食料デーをきっかけに始めたい、3つの具体的な取り組みを紹介します。
必要なものだけを買う
フードロスを削減するためには「必要なものだけを買う」意識を持つことが大切です。例えば、「安いから」「まとめ買いでお得だから」という理由で食材を購入して、うっかり使い切れずに廃棄してしまうようなことは避けましょう。
具体的な方法としては、まず、家にある食材の量や状態を常にチェックする習慣を身に着けてみましょう。そのうえで、賞味期限や消費期限が近い食材から使い切れるように意識した献立を考えて、追加購入する食材を選べば、必要以上に購入してしまうことを避けられます。
時間がないときには、冷蔵庫の中身が分かるようにひとまず写真を撮影しておいて、買い物時に見返しながら食材を選ぶのもおすすめです。
保存の仕方を考える
食品は、それぞれの食品に記載されている「食品表示」にしたがって保存することで、鮮度を保ち、美味しく食べきれます。
また、細かなところでは次のような保存のコツがあります。
- 冷蔵や冷凍が推奨される食材は帰宅後すぐにしまう
- 肉や魚介類から出るドリップ(汁)は、ほかの食材に触れないように気を付ける
- 調理済みのものはあら熱をなるべく早く取り、密閉して速やかに保存する
いずれも菌の増殖をなるべく防ぐことで、保存効率を高める方法です。
また、作り置きした料理や、事前に下処理・下ごしらえした食材は、中身の見える透明なプラスチックやガラス製の容器に保存することをおすすめします。
小分けすることであら熱が取れやすくなるほか、中身が分かりやすいほど使い忘れが起こりづらくなります。
外食でもフードロスを避ける
フードロスを避けるため、外食でも「食べ残しゼロ」を意識することが大切です。
注文する際は、「本当に食べきれるか」をよく考えることが重要です。特に、小食の方や食べる量にムラのある方は、ハーフサイズや小盛りメニューを選ぶなど工夫してみましょう。
「食べられると思って頼んだけれど、食べきれない」というときには、お店に持ち帰りできるかを相談してみるのもおすすめです。
環境省では、消費者庁、農林水産省と共にどうしても食べきれない場合に食べ残しを持ち帰る「mottECO(モッテコ)」を意欲的に推奨しています。
私たち一人ひとりが「食べきること」や「食べきれない場合は、食べ残しを持ち帰ること」を意識すれば食品ロスの削減に大きく貢献できるでしょう。
食べ物の大切さを学ぼう!公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがメンバーで協力し合い、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「子どもに楽しみながら環境や社会について学んでほしい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
イオン チアーズクラブで開催された活動

ここでは、イオン チアーズクラブでこれまでに実施してきた活動内容の一部をご紹介します。
田植え体験・稲刈り収穫体験
イオン チアーズクラブのメンバーたちが田植えと稲刈りを体験しました。
これらの活動は、普段何気なく食べているお米の生産過程を自分の手で体感することで、食べ物を育てる大変さや農家の方々の努力を知る機会になりました。
田植え体験では、農場の代表から直接指導を受けながら初めての苗植えに挑戦しました。
メンバーたちからは「楽しかったので、またやりたい。」「知らないことを知ることができて、また行きたい。」といった感想も聞かれました。
稲刈りでは、自分たちが植えた稲を鎌で刈り取る作業に挑戦しました。
メンバーたちは、鎌を安全に使う方法についてレクチャーを受けた後、大人とペアになって黄金色に輝く稲穂を刈り取り、とても嬉しそうでした。
メンバーたちにとって食べ物を育てる苦労や大切さを学ぶ良い機会となったことでしょう。
マックスバリュ東海管理栄養士による食育講座
「マックスバリュ東海管理栄養士による食育講座」では、管理栄養士の指導のもと、メンバーたちが食育講座と、お買い物体験を実施しました。
食育講座では、炭水化物、たんぱく質、ビタミン・ミネラルの3色のバランスをとったご飯を食べる大切さについて学びました。
メンバーたちは、普段何気なく食べているご飯にさまざまな栄養素が含まれていることを再認識し、健康な体づくりには欠かせない知識を身につけることができました。
続いて行われたお買い物体験では、「愛知県産の野菜とカレーの材料をお得に買うミッション」に挑戦しました。
店頭で並ぶ数多くの野菜の中から地元産のものを見つけ、値段や鮮度を比べながら必要な食材をそろえる過程は、ただ買い物をするだけでなく「買い物上手」になるコツを学べる場にもなりました。
また、購入した野菜を手探りで当てるゲームでは、形や大きさ、質感など五感を使うことで、メンバーたちは改めて食材そのものに興味を持ち、学びを深められたようです。
これらの体験を通して、メンバーたちは栄養バランスを意識した食生活の大切さや、産地を意識して買い物をする楽しさを実感しました。
イオン チアーズ農園での活動
茨城県牛久市の牛久チアーズ農園や、宮城大学 坪沼農場の宮城大学チアーズ農園など各地の農園において、種まきから収穫までの一連の作業を通じて農作物を育てる大変さや楽しさを体感しながら、自然環境や食べ物の大切さを学んでいます。
こうした体験を通じて、自分たちの手で苗から育てた作物を実際に収穫することで、「食べ物がどのように生まれ、どんな手間ひまをかけて私たちの食卓に届くのか」という視点を身近に感じることができるのも大きな魅力です。
メンバーたちにとって、食のありがたみをあらためて実感し、自然の恵みへの感謝の気持ちを深める貴重な機会となっています。
この他にも、イオン チアーズクラブではさまざまな活動を行っています。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、10月16日の世界食料デーについて、制定の背景や現状まで含めて解説しました。
世界食料デーは、国連が制定した「世界の食料問題を考える日」です。
世界では、十分な食料が生産されているにもかかわらず、紛争や貧困、気候変動などの影響で今も多くの人が飢餓や栄養不足に苦しんでいます。
こうした状況に目を向けて「私たちにできること」を考え、小さなことからでも行動を起こすことが大切です。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。