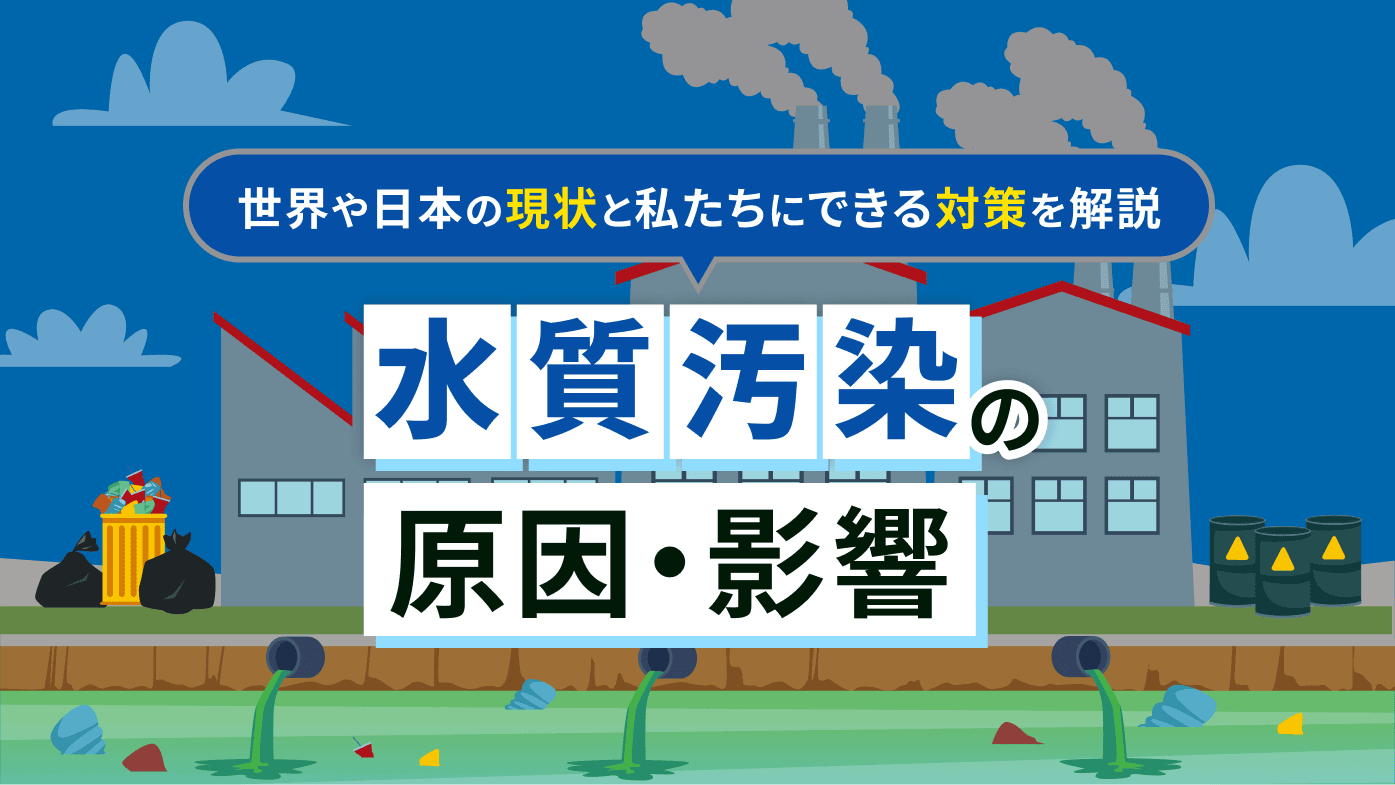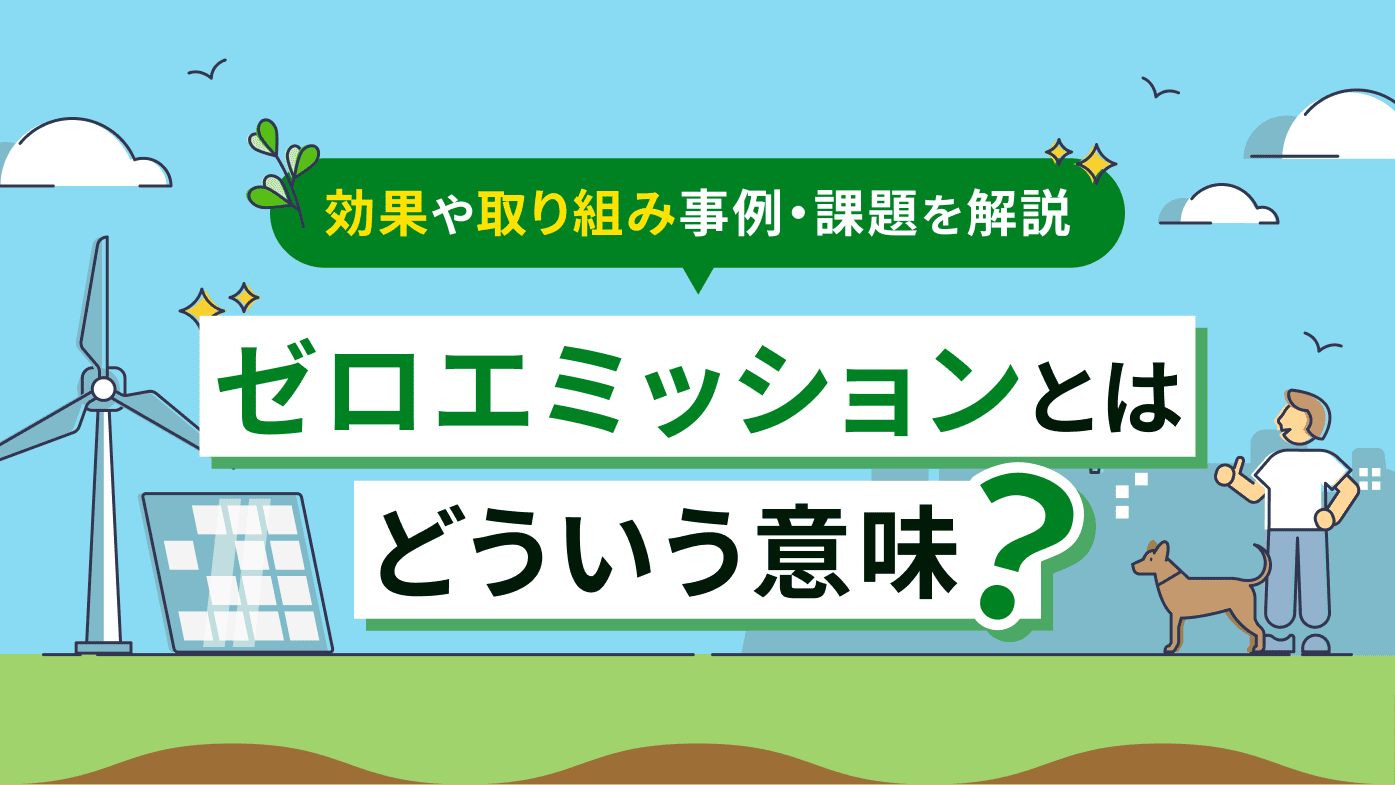2025.09.09
子どもの貧困問題とは?日本や世界の現状と原因について解説
「子どもの貧困」と聞くと、どこか遠い国の話のように感じる方もいるかもしれません。しかし実際には、日本でもおよそ9人に1人の子どもが貧困と呼ばれる状況に置かれています。
このコラムでは、「子どもの貧困」とはどのような状態なのか、その背景にある原因、日本や世界で進められている対策、そして私たちにできる支援の方法まで、わかりやすく解説していきます。
問題の本質を知ることが、子どもたちの未来を支える第一歩になります。
目次
子どもの貧困の定義とは?

「子どもの貧困」とは、単にお金がない状態を指すだけではありません。学ぶ機会や心の安定、社会とのつながりといった、子どもが健やかに成長するために必要な要素が不足している状態も含まれます。
ここでは、まず「子どもの貧困」の基本的な定義と、日本における実態について解説します。
子どもの貧困とは「生活や学びに必要なものが足りない状態」
子どもの貧困とは、子どもが健康に育ち、安心して学べるために必要な環境や機会が十分にそろっていない状態を指します。
これは、食べ物や住まいといった目にみえる「モノ」の不足だけではありません。勉強や医療、人との関わり、文化的な経験など、子どもの成長に必要な多くのことが足りていないという広い意味を含んでいます。
例えば、次のような状態は「子どもの貧困」にあたります。
- 経済的な理由で進学をあきらめている
- 1日のなかで、栄養バランスのとれた食事が給食だけになっている
- 子どもだけで過ごす時間が多く、保健衛生などの知識や生活習慣が身につきにくい
このような状態が長く続くと、毎日の生活が不安定になるだけでなく、将来の夢や選択肢にも影響が出てしまう可能性があります。
今、注目が集まっているのは「子どもの相対的貧困」

「貧困」と聞いたとき、多くの方は「食べ物がない」「住む家がない」といった「絶対的貧困」を想像するかと思います。
これに対して、日本で特に注目されているのが「子どもの相対的貧困」です。
これは見た目では生活に困っていないようでも、他の子どもたちと比べて不利な状況に置かれていることを指します。
ここでは、「絶対的貧困」と「相対的貧困」の違いや、日本における相対的貧困の実態について解説します。
「絶対的貧困」と「相対的貧困」の違い
貧困には「絶対的貧困」と「相対的貧困」の2つの考え方があります。
絶対的貧困とは、衣食住など人が生きていくうえで必要最低限の生活さえできない状態のことです。
一方、相対的貧困とは、その国や地域の平均的な生活水準と比べて、明らかに不利な状況にあることを指します。
例えば、経済的な理由で進学をあきらめている、将来に希望を持てず学ぶ意欲を失っている、人とのつながりが少なく孤立している、といった状況は、相対的貧困にあたります。
日本は世界のなかでも豊かな国ですが、目に見えにくい相対的貧困の割合は高い傾向にあり、社会における大きな課題となっています。
日本は子どもの相対的貧困率が高水準だと言われている
日本の子どもの相対的貧困率は、先進国のなかでも比較的高い水準にあるとされています。
厚生労働省の2021年の「国民基礎調査」によると、18歳未満の子どものうち約11.5%が相対的貧困状態にあると報告されています。
これは、およそ9人に1人の子どもが経済的に厳しい状況に置かれていることを意味します。
この背景には、いくつかの要因が複雑に絡んでいます。
例えば、ひとり親家庭の増加や、非正規雇用の拡大、社会保障制度による支援が十分に行き届いていないことなどが挙げられます。
相対的貧困は、見た目ではわかりにくく、支援が届きにくいという特性があります。そのため、こうした現状への理解と関心を深めることが求められています。
子どもが相対的貧困に陥る原因

子どもが「相対的貧困」に陥る背景には、家庭の事情だけでなく、社会全体の仕組みに関わる問題が複雑に関係しています。
ここでは、日本の現状に照らしながら、子どもの貧困につながる代表的な3つの要因をご紹介します。
①ひとり親家庭の増加と非正規雇用の広がり
ひとり親家庭は、2人以上の大人が支える家庭と比べて、経済的に不安定になりやすい傾向があります。特に母子家庭では、パートやアルバイトなどの「非正規の仕事」に就いている方が多く、収入が限られるケースが少なくありません。
また、一人で家事や育児をこなす必要があるため、働ける時間が限られてしまい、十分な収入を得るのが難しくなることもあります。
その結果、子どもに必要な学習環境を整えにくくなったり、進学の選択肢が狭まってしまったりと、子どもの生活にも影響が出やすくなっています。
②教育格差と情報格差
経済的に厳しい家庭では、塾や習い事に通わせることが難しかったり、パソコンやWi-Fiといった学習環境を整えるのが難しいことがあります。
その結果、家庭によって子どもたちの教育の機会に差が出てしまい、進学や将来の選択肢にも大きな影響が出ることがあります。
また、保護者が教育や支援制度についての情報を知らない・知る手段がないというケースもあり、必要な支援が受けられずに困っている家庭も少なくありません。
このように、経済的な格差により教育格差と情報格差が起こり子どもたちの「可能性の差」につながってしまうこともあります。
③支援の手が届きにくい
子どもの貧困を支える制度や仕組みは存在していても、それを本当に必要としている家庭に届いていないケースも少なくありません。
例えば、制度の存在自体を知らなかったり、周囲の目を気にして支援の利用を控える家庭もあり、本来受けられるはずのサポートを受けられずにいることもあります。
さらに、学校や地域とのつながりが薄い家庭では、困っていることが外から見えにくく、誰にも相談できないまま孤立してしまうことがあります。
こうした「支援の届かなさ」は、貧困の状態が長く続いてしまう原因にもなります。
子どもが絶対的貧困に陥る原因

世界に目を向けると、開発途上国などでは子どもたちが「絶対的貧困」に陥るケースも少なくありません。
ここでは、その主な要因について、3つの視点から解説します。
①自然災害による農業被害
干ばつや洪水、地震といった自然災害は、地域の暮らしや産業に大きな被害をもたらします。
特に農業に依存している地域では、作物が育たずに収入が減ったり、食べ物が手に入りにくくなったりして、家庭の生活が不安定になります。
その影響で、子どもが十分な食事をとれなかったり、学用品がそろえられず学校に通えなくなったりすることもあります。
さらに、支援が行き届きにくい地域では、子どもたちが健康や命の危険にさらされる深刻な状況になることも少なくありません。
②紛争や治安の悪化
戦争や政治の混乱が続く地域では、子どもたちが安心して暮らすことが非常に難しくなります。
例えば、学校や病院が閉鎖されたり、食べ物や水が手に入りにくくなったりして、平和であれば当たり前に受けられる教育や医療が受けられなくなってしまいます。
また、戦争や避難の影響で難民となる子どもたちも多く、そのなかで親と離れ離れになり、頼れる大人がいないまま一人で過ごさなくてはいけなくなることもあるでしょう。
このような状況では、子どもたちが自分の力で生活を立て直したり、将来の夢に向かって進んだりすることが難しくなってしまいます。
③インフラや医療・教育制度の未整備
開発途上国のなかには、医療や教育、交通など、生活の基盤となる設備や制度が整っていない地域が多く存在します。
例えば、「学校が遠くて通えない」「医師の不足や医療費の負担が大きいことなどから、病気になっても治療が受けられない」といった状況です。こうした環境では、子どもたちが健康に育ち、学ぶために必要な機会が十分に得られません。
その結果、教育を受けられないと技術や知識が身に付かず、安定した収入を得られません。収入が得られないと栄養のある食事をとることも難しくなり栄養状態が悪くなってしまいます。病気などにかかるとなかなか治らないため、親や年長の家族が病気になれば、代わりに子どもが働く必要があり、教育を受けられない、という負の連鎖が起こっているのです。
子どもの貧困が与える影響

子どもの貧困は、今この瞬間の暮らしを苦しくするだけでなく、将来にも深刻な影響を与える可能性があります。
まず、経済的な理由で塾や習い事に通えなかったりすると、学力や進学の機会に差が生じやすくなります。
こうした教育格差は、将来の就職先や収入にもつながりやすく、長い目で見た「生き方の選択肢」を狭めてしまうことがあります。
また、栄養バランスの取れた食事がとれなかったり、病気になってもすぐに病院にかかれなかったりすることで、健康状態が悪くなるケースもあります。
さらに、周りとの「違い」に敏感になってしまい、自分に自信が持てなくなる、友達とうまく関われなくなるなど、心の面での影響も少なくありません。こうして人とのつながりが薄れ、孤立してしまうこともあるのです。
このように、子どもの貧困は「生活・健康・学び・心」などさまざまな面に影響を与える複雑な課題です。だからこそ、早い段階からの支援と、周囲の理解・協力が大切なのです。
日本や世界が行っている子どもの貧困対策とは

子どもの貧困は、日本だけでなく、世界中で共通する社会課題です。各国では、教育や生活を支えるためのさまざまな取り組みが進められています。
ここでは、日本国内と海外の主な対策や支援の傾向についてご紹介します。
日本における対策・取り組みの傾向
日本では、2014年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、国をあげた支援が本格的に始まりました。
現在、主に次のような取り組みが行われています。
- 経済的に困難な家庭への「就学援助」(学用品費や給食費の補助)
- 無料または低額で食事を提供する「子ども食堂」への支援
- 放課後の「学習支援事業」や、勉強を教えるボランティアの派遣
- 「スクールソーシャルワーカー」(学校における相談員)の配置
- NPOや地域団体と連携した「居場所づくり」や生活支援
こうした取り組みにより、子どもが孤立せず、安心して学び・育つ環境を整える努力が進められています。
ただし、自治体ごとに支援の内容や充実度には差があり、必要な支援が届かないケースもあるのが現状です。今後は、支援を継続的に行える体制づくりと、子ども一人ひとりに応じたきめ細かな対応が求められています。
世界における対策・取り組みの傾向
世界でも多くの国が、子どもの貧困解消に向けた取り組みをしており、特に教育や医療をすべての子どもが受けられるようにする支援が重視されています。
例えば、ヨーロッパ諸国では、無償の教育制度や学校給食が普及しており、低所得世帯の子どもでも平等に学べる仕組みが整っています。
また、国連が掲げる「SDGs(持続可能な開発目標)」においても、子どもの貧困解消は重要な課題の一つとしてされており、国際社会全体での取り組みが求められています。
世界各地では、国際NGOが、次のような支援活動を展開しています。
- 教育資材や給食の提供
- 子ども向けの保健医療サービス
- 災害・紛争地域での緊急支援
- 職業訓練や自立支援プログラムの実施
このように、各国や国際機関が連携しながら、子どもたちの命と未来を守るための取り組みが広がっています。
子どもの貧困に対して私たちができる支援

子どもの貧困は「知って終わり」ではなく、「行動で支える」ことが大切です。私たち一人ひとりにも、身近なところから支援に関わる方法があります。
ここでは、日々の生活のなかで参加できる2つの具体的な支援方法をご紹介します。
寄付や募金をする
子どもの貧困支援のなかでも、もっとも気軽に始められて効果的なのが、寄付や募金です。少額からでも始められ、継続的な支援も可能です。
支援を受けて活動しているNPOや団体では、集まった寄付金をもとに、学習支援・食事支援・居場所づくりなど、子どもたちに直接届く取り組みを行っています。
最近では、「クラウドファンディング※」や、買い物などでたまったポイントを使って寄付ができる「ポイント募金」、古本や書き損じはがきを活用した寄付など、気軽に参加できる支援の仕組みが広がっています。
無理のない範囲で、自分に合った方法を選べるのも大きな魅力です。
※ 活動や想いに共感した人からWebサイトを通じて資金を集める仕組み
ボランティアに参加する
時間やスキルを活かしたボランティア活動は、子どもの貧困を支える大切な手段の一つです。
例えば、食事提供を行う施設での調理や配膳の手伝い、学習支援教室での宿題サポート、仕事やスポーツなどに関するイベントのサポートなど、活動内容は多岐にわたります。
最近では、オンラインでの家庭教師や、NPOの広報活動を支援するなど、家に居ながらでも参加できるボランティアも増えています。
できるときに、できる範囲で関わることが大切であり、子どもたちとのふれあいを通じて、自分自身にも多くの気づきや学びが生まれます。
公益財団法人イオン1%クラブの取り組み「イオン ユニセフ セーフウォーターキャンペーン」について

公益財団法人イオン1%クラブでは、カンボジア等の子どもたちに安全な水を供給するため、全国から寄せられた募金と当財団からの拠出金を、公益財団法人日本ユニセフ協会を通じて寄付しています。
このキャンペーンは、2010年からカンボジア・ラオス等の水・衛生事業を支援するためにスタートしました。
遠方への水汲みに時間をとられ、学校の授業に参加できない子どもたちや、健康を害する恐れのある物質を含む地下水を生活用水として使う子どもたちを給水施設の設置等により、教育・健康の両面でサポートしています。
安全な水と衛生環境は、子どもたちの命を守り、健やかな成長を支える基盤です。
公益財団法人イオン1%クラブでは、今後もイオン ユニセフ セーフウォーターキャンペーンを通じて世界が抱える水問題の解決に取り組んでいきます。
公益財団法人イオン1%クラブのイオン ユニセフ セーフウォーターキャンペーンについて、さらに詳しく知りたい方は、下記のURLからご覧ください。
イオン ユニセフ セーフウォーターキャンペーンについて詳しく知りたい方はこちら
まとめ
このコラムでは、子どもの貧困問題について解説しました。
子どもの貧困は、私たちの暮らす日本でも実際に起きています。見た目ではわかりにくくても、学ぶ機会や安心できる環境が整えられていない子どもたちは、身近に存在しているのです。
この問題を理解し、関心を持つことが、子どもたちの未来を守る第一歩です。
「知ること」「気にかけること」「できることから始めてみること」が、支援の大きな力になります。
まずは、今日から身近なところに目を向けてみませんか?
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。