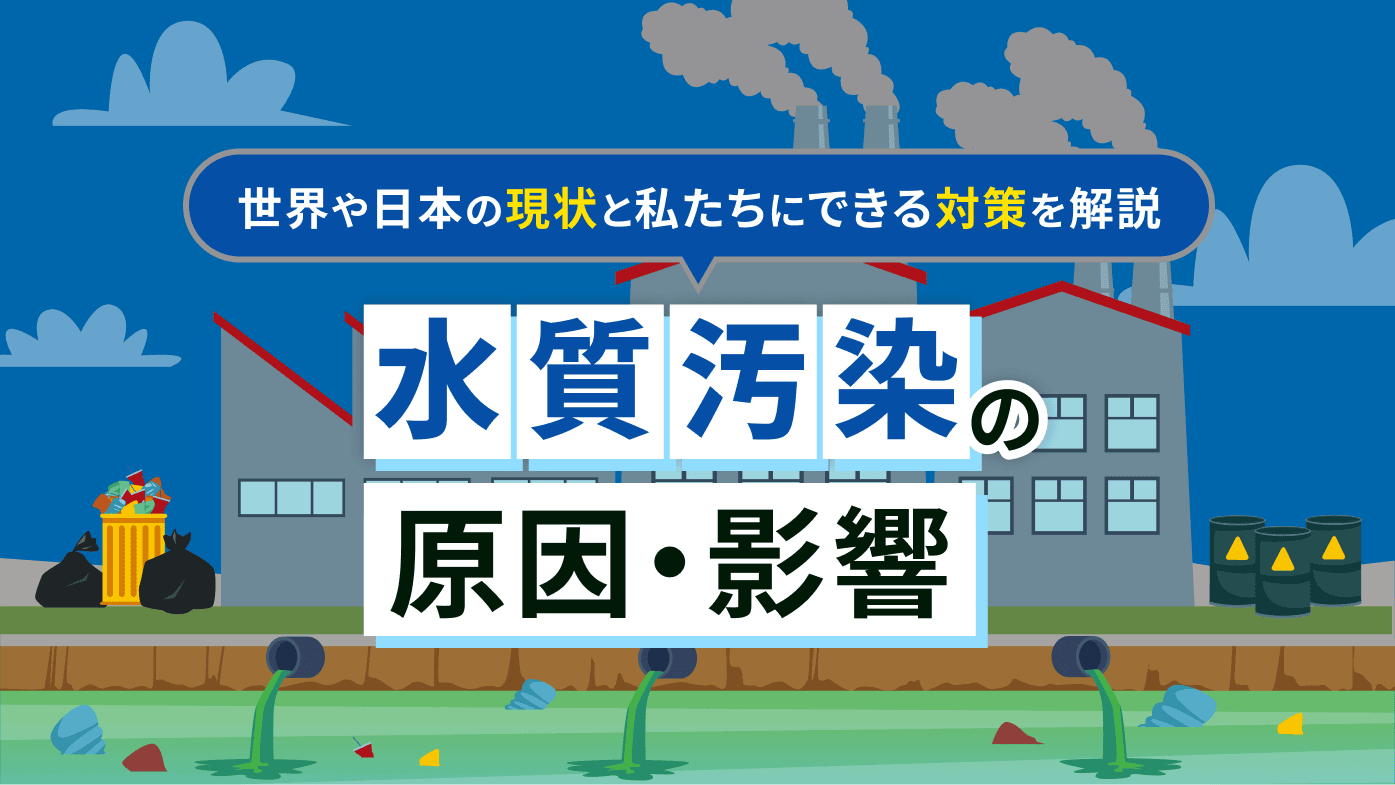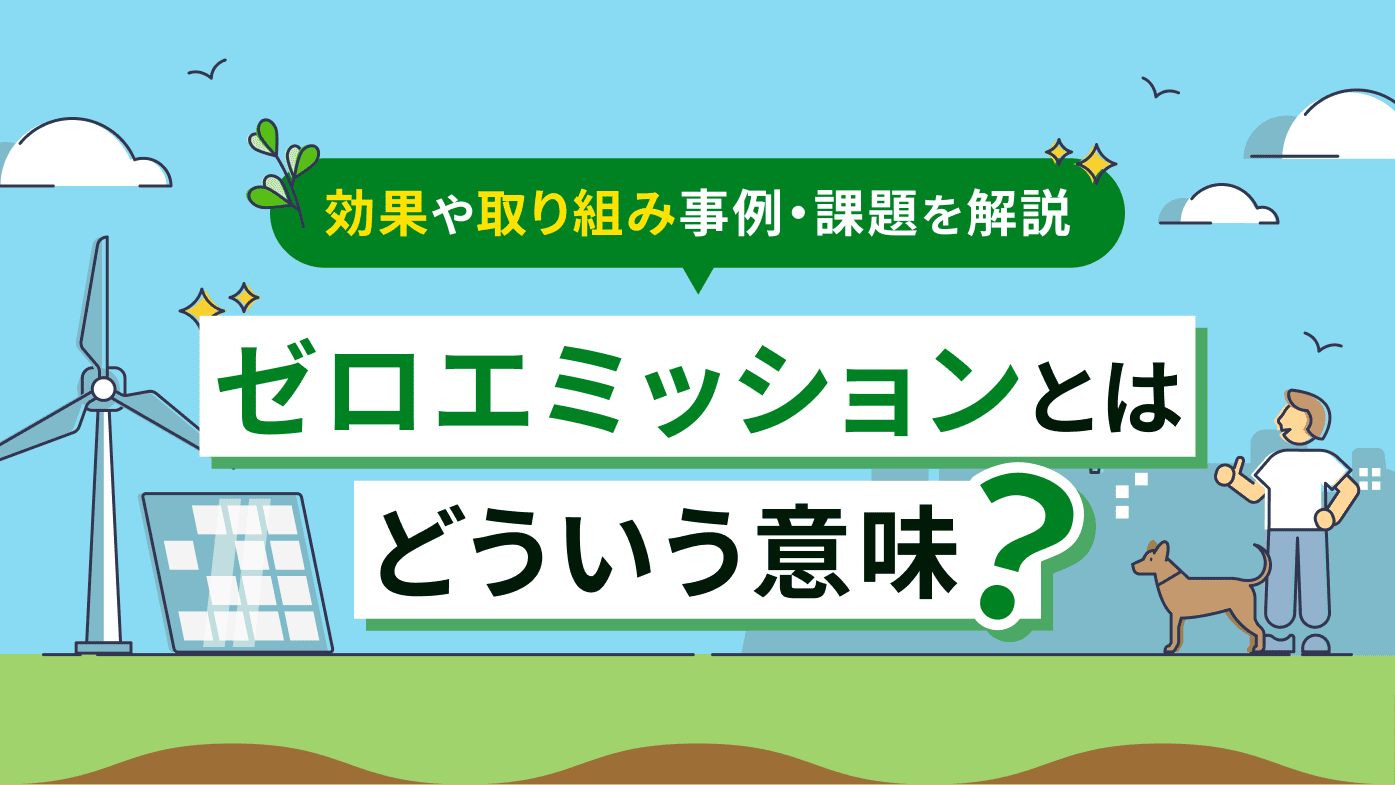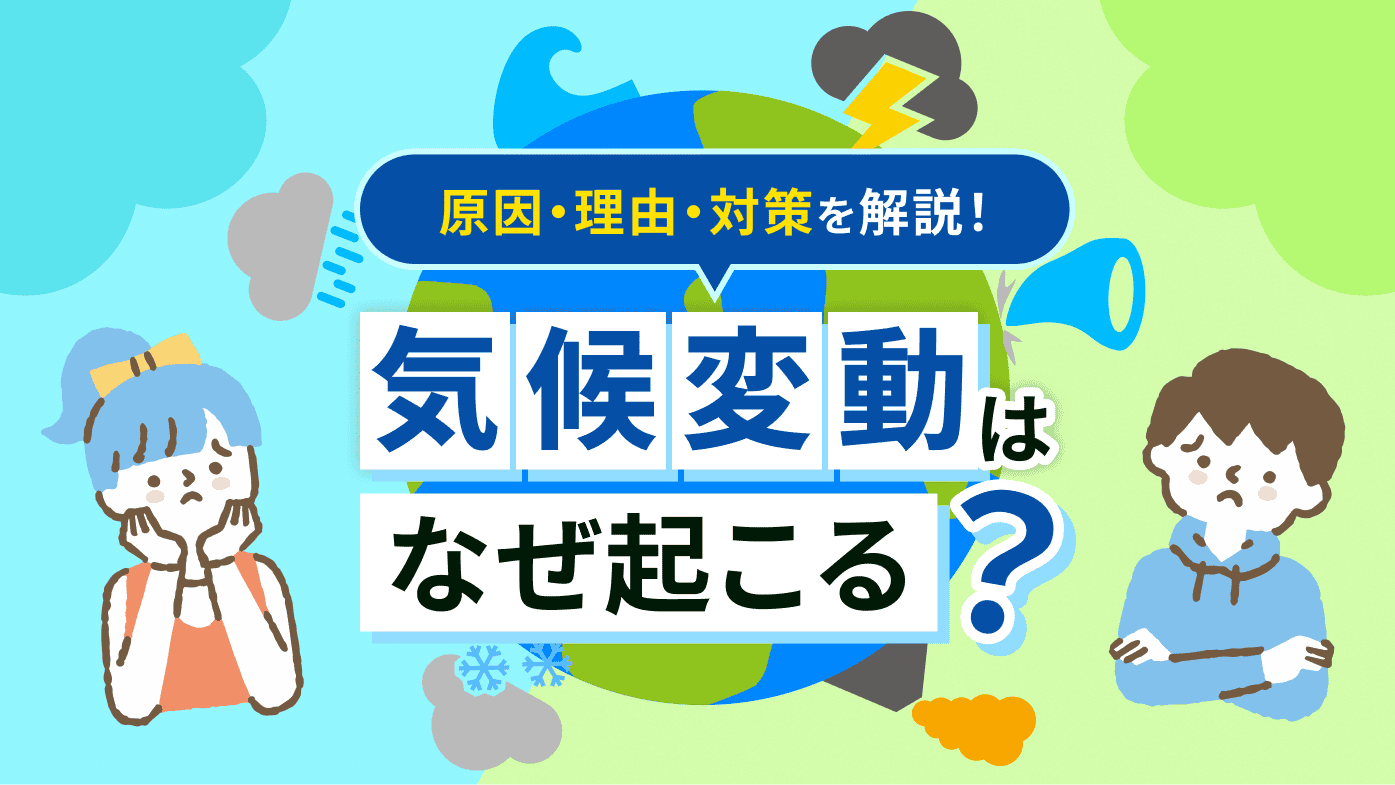
2025.09.25
気候変動の原因とは?気候変動がなぜ起こるか、理由と対策も合わせて解説!
近年、「気候変動」と呼ばれる、気温や気象パターンが長きにわたって変化し続けていることが問題となっています。
気候変動は自然の要因だけでなく、人間の活動によっても引き起こされており、その影響は年々深刻さを増していることをご存じでしょうか。
本コラムでは、気候変動の原因や、私たちにできる対策について解説します。
目次
気候変動とは?現状や地球温暖化との関係は?

気候変動とは、気温や降水量など大気の状態が、長期間にわたって変化していくことです。
気候変動は自然現象としても起こりますが、1800年代以降は人々の活動によって生じる温室効果ガスの過剰な発生が主な原因だと言われています。
温室効果ガスはその名前の通り、温室のように地球を包み込み、太陽の熱を閉じ込める効果を持っています。
このような温室効果ガスの働きは、地球の環境を保つうえで必要な働きです。しかし、過剰発生にまでなると地球温暖化を進行させ、気候変動を引き起こしてしまいます。
気候変動は地球上の生き物すべての命にかかわる重要な問題
気候変動では気温に限らず、大気全体に変化が起こります。結果、地球上では次のようなさまざまな問題が起こっています。
- 雨が極端に降らず干ばつが起こり、水不足や森林火災に悩まされる地域が増えている
- 極度の大雨による河川の氾濫(はんらん)、洪水に悩まされる地域が増えている
- 北極などの氷が溶け、海面が上昇している など
これらの問題は人々だけでなく、地球上の生き物すべての生命をおびやかしています。
気候変動を完全に止めることはできませんが、少しでもそのスピードを緩やかにする努力が早急に求められています。
繰り返しになりますが、気候変動の主な原因は、私たち人間の活動による温室効果ガスの過剰発生です。
私たち一人ひとりが地球環境を考え、意識や行動を改める必要があるでしょう。
気候変動の人為的な原因

先述でも述べた通り、気候変動は火山噴火をはじめとした自然要因でも起こりますが、現代において問題になっているのは、人々の活動によるものです。
そこで、ここでは人々の活動のうち、何が気候変動を引き起こしているのかを具体的に解説します。
化石燃料を使った発電
化石燃料を使った発電は、気候変動の大きな原因です。
電気エネルギーをつくるために化石燃料を燃やすと、地球温暖化を引き起こす二酸化炭素や亜酸化窒素(あさんかちっそ)が多く発生するためです。
日本では化石燃料のうち、石炭を発電によく使っています。安全性が高く、量も確保しやすいので安く、安定して供給しやすいといった理由があるためです。
しかし、石炭はほかの化石燃料と比べても、多くの二酸化炭素を発生させてしまいます。
昔に比べると発電技術が良くなり、少ない石炭量で多くのエネルギーを生み出せるようにはなってきました。
また、太陽光や風力、地熱といった地球上の二酸化炭素を増加させない再生可能エネルギーの開発も進んでいます。
とはいえ、日本をはじめ世界でもまだまだ化石燃料に頼らざるを得ない現状のため、さらなる技術開発および一人ひとりの節電に対する意識改革が必要です。
モノの大量生産と大量消費
先進国を筆頭にモノの大量生産・大量消費が繰り返されています。これもまた、気候変動の原因です。
モノの生産にはエネルギーが必要で、エネルギー源として主に使われているのは発電同様、化石燃料です。
エネルギーをつくるときに、二酸化炭素や亜酸化窒素(あさんかちっそ)が発生し、気候変動を引き起こす地球温暖化が進行します。
モノの大量生産・大量消費は、経済発展においては必要であったかもしれません。しかし、多くのものを作ればつくるほど、二酸化炭素や亜酸化窒素は多く発生します。
未来の地球環境を守るためには、生産と消費の在り方を見つめ直す必要があるでしょう。
過剰な森林伐採
過剰な森林伐採は、気候変動の原因だと言われています。
木々をはじめ植物は光合成をするときに二酸化炭素を吸収し、貯蔵しています。その量は、きちんと手入れされたスギの場合で、1ヘクタールあたり約304トンにもなるそうです。
木々を伐採すると、貯蔵された炭素が空気中に放出されます。また、森林が減少すれば、二酸化炭素を吸収する自然の力も弱まってしまいます。
よって、過剰な森林伐採は地球温暖化を招き、気候変動を引き起こしてしまうのです。
計画的かつ適切な森林伐採は、人々の生活において必要不可欠です。しかし、実際には、違法伐採や急激な人口増加に伴う農地開拓などにより、無茶な伐採が多く行われています。
過剰な森林伐採を防ぎ、植樹をはじめとした森を再生するための取り組みが求められています。
食料の生産・供給
モノだけでなく、食料の生産・供給においても、多くの二酸化炭素や亜酸化窒素が排出され、気候変動の原因となっています。
食料の生産・供給において、温室効果ガスが発生・増加するのは、次のような影響によるものです。
- 農地や牧場をつくるための過程で森林を過剰に伐採
- 化学肥料の使用※
- 収穫に使う機具、漁船などを動かすエネルギーとして化石燃料を使用
- 配送に使う自動車やトラックなどを動かすエネルギーとして化石燃料を使用 など
私たちが生きていくうえで食料は欠かせないので、生産・供給に伴う温室効果ガスの発生をゼロにはできません。
しかし、「フードロスを防ぐ」や「地産地消を心がける」ことで、気候変動を現在よりもゆるやかにすることはできるでしょう。
※ 化学肥料の生産には化石燃料が使用されており、使った畑から温室効果ガスが発生することが報告されている
気候変動の自然的な原因

地球の気候は、人間の活動とは関係なく、自然の要因によっても変動を繰り返してきました。
ここでは、自然の働きが地球の気候にどのように関係しているのかを解説します。
地球の公転軌道・自転軸の変化
地球の公転と自転は、気候に影響を与える要因の一つです。
地球は太陽の周囲を回り(公転)続けていますが、その軌道はきれいな円ではありません。
よって地球と太陽の距離は常に一定ではないので、太陽から受ける気候への影響にも差が出るのです。
また、地球はぐるぐると回転(自転)していますが、回転の中心にある地軸の傾きは一定ではありません。これによってもまた、太陽との距離関係は変化します。
ただし、これらの変化に伴う気候変動は、数万年単位で起こるものだと言われています。
火山の噴火
火山の噴火は、周辺地域に大きな被害をもたらすだけでなく、気候にも影響を与えることがあります。
火山が噴火したとき、二酸化硫黄と呼ばれるガスが多量に発生します。
二酸化硫黄は大気中で酸化し、硫酸エアロゾルと呼ばれるものに変化します。硫酸エアロゾルは、直径わずか0.1~0.2ミクロンのとても小さな物質です。
小さいからこそ、1~2年、長いときではさらに数年にわたって大気中に残り続けるのだと言います。
硫酸エアロゾルは、太陽光を受けたとき、散乱する働きを持ちます。そのため、大気中の硫酸エアロゾルが多いと、太陽放射を反射してしまい太陽の熱が地表に届きづらくなるのです。
結果、気温の低下という気候変動が起こるという訳です。
急激な気候変動を防ぐため私たちにできる行動

気候変動の大きな原因である地球温暖化を防ぐには、私たち一人ひとりによる日々の心掛けも重要だと言われています。
そこでここでは、今日から始められる「急激な気候変動を防ぐためのエコ活動」をご紹介します。
節電
急激な気候変動を防ぐために私たちにできることの一つが、節電です。
節電をすると、発電の際に発生する温室効果ガスの排出量を抑えられるため、気候変動の緩和につながります。
具体的な節電方法を家電別にチェックしてみましょう。
エアコン
夏にエアコンを使用するときは、室内温度が28度になるように設定するのがおすすめです。26度の場合と比べると、1.6~5.4%の節電につながると言われています。
エアコンのこまめな掃除で冷却効果を保つことも大切です。
ただし、夏場は熱中症の危険性もあるので、我慢のしすぎには気を付けましょう。
冷蔵庫
冷蔵庫に入れる食品は、適量を目指しましょう。あまり多くの食品を詰め込むと、冷却により多くの電力を必要とするほか、扉を開ける時間も増えてしまいます。
また、冷蔵庫の排熱がどこから行われているのかを確認し、その箇所は壁と密着しないようにしておきましょう。排熱がスムーズであるほど、消費電力は少なくなります。
そのほか家電全般
使わない家電のプラグは、コンセントから抜いておきましょう。待機電力を使わないことによる節電が可能です。
ゴミの削減
ゴミを減らせば、燃やすときに出る温室効果ガスの発生を抑えられます。
ゴミを減らすための行動としてまず挙げられるのは、モノを大切に使用することです。
例えば、詰め替えがあるモノはそちらを積極的に購入し、容器を繰り返し使うのが良いでしょう。
マイバッグやマイ箸などを持ち歩く習慣をつけて、レジ袋やプラスチック食器など、使い捨てされるものの使用を避けるのもおすすめです。
リサイクルに意識を向けることも大切です。リサイクル可能なゴミは、適切に分別し、回収に出しましょう。
なお、中身が残っていたり、汚れがひどいゴミは、リサイクルできない可能性があります。ゴミに出す前に、できるだけきれいにするように心がけましょう。
このようなゴミを削減するための取り組みは、「5R(リサイクル・リデュース・リユース・リフューズ・リペア)」の一環です。
5Rについて詳しく知りたい方は、次の記事もご覧ください。
リサイクル・リデュース・リユースを含む5つのRとは?日常生活での取り組み例も紹介
移動手段の見直し
気候変動の進行を抑えるためには、環境に優しい移動手段を選ぶことが大切です。
具体的には、化石燃料を必要としない徒歩や自転車といった方法がおすすめです。
徒歩や自転車では厳しい長距離移動のときには、公共交通機関の利用を検討してみましょう。
電車やバスは多くの人を一度に運べるため、自動車に比べると温室効果ガスの発生を抑えられます。
とはいえ、車がなくては生活に困る地域もあるでしょう。
その場合には、通常の自動車よりも温室効果ガスの発生が少ない電気自動車を検討する、アクセルは急に踏み込まない・離さないといった燃費を高める運転を心掛けるなどで対策してみましょう。
公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

公益財団法人イオン1%クラブが運営する「イオン チアーズクラブ」は、全国の小学校1年生から中学校3年生までを対象とした活動団体です。
イオン チアーズクラブでは、環境や社会に対して興味・関心を持ち、考える力を育むため、さまざまな体験学習を実施しています。
体験学習では子どもたちがメンバーで協力し合い、一丸となって活動に取り組むため、集団行動における社会的なルールやマナーも学べます。
「楽しみながら環境や社会について学んでほしい」と考えている保護者の方は、ぜひお子さまのイオン チアーズクラブへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
この他にも、イオン チアーズクラブではさまざまな活動を行っています。
イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。
子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!
まとめ
本コラムでは、気候変動の原因について解説しました。
気候変動は自然要因でも起こりますが、それはとても緩やかなもので、短期的に問題を引き起こすことはあまりありません。
一方、発電や過剰な森林伐採など、人々の営みは、急激な気候変動を引き起こします。結果、地球は傷つき、人もそのほかの動植物も生活することが難しい地域が増えています。
気候変動はすぐに解決できるものではなく、節電やゴミの削減といった一人ひとりの意識および行動改革が必要です。
少しでも地球を守りたい気持ちを抱いたなら、簡単にできることから行動を始めてみましょう。
公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
「子どもたちの健全な育成」事業の一つである「イオン チアーズクラブ」では、小学生を中心に、環境や社会貢献活動に興味・関心を持ち、考える力を育む場として体験学習を全国で行っています。
また、中学生が環境に関する社会問題をテーマに、自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境保全や社会貢献に関する活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」など、さまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLから詳細をご覧ください。